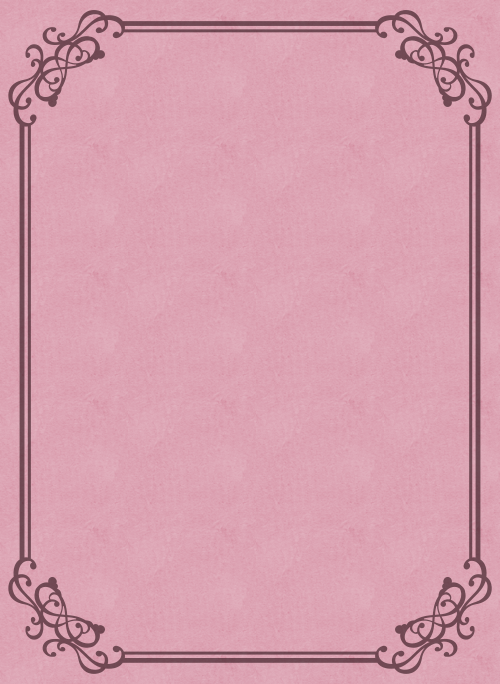小林君を見て察したのか、遥貴さんはすみませんと小声で言う。
「疲れて寝てしまったみたいなの。だから、起こさないであげて」
「かしこまりました」
遥貴さんは、持っていた洋菓子と紅茶をのせたおぼんをそっと床に置く。
「……このまま今日は、泊めてあげましょうか」
「……そうね」
部屋も空きがあるし、泊めるのには何の問題もない。
それに、小林君はただでさえ家の事で疲れているはずだ。授業中に寝ているのも、多分それが原因だろう。
……いつも、ご飯はどうしているのだろうか?一人で小林君が食べている様子を想像すると、何だか悲しくなった。
小林君だって、辛くて寂しかったのかもしれない。
気づかなかった自分が少し情けなく思えてくる。
「……小林君、一人暮らししてるみたいなの。だから、こんな日ぐらい休ませてあげないと」
「そうだったのですね……」
遥貴さんは少し暗い顔をする。
……自分の過去に、重ね合わせているのかもしれない。
遥貴さんにとって、一人になるということは、悲しい事でしかなかったのだから。
私は遥貴さんの手を握った。
「遥貴さん、大丈夫だよ。小林君も遥貴さんも、もう一人ではないのだから」
「お嬢様……すみません、少し過去の事を思い出してしまいました。ですが、私は平気です。心配して下さり、ありがとうございます」
「……そっか」
私はほっとして、遥貴さんから手を離す。
それでもまだ、遥貴さんの表情はどこか悲しげに見えたんだ。