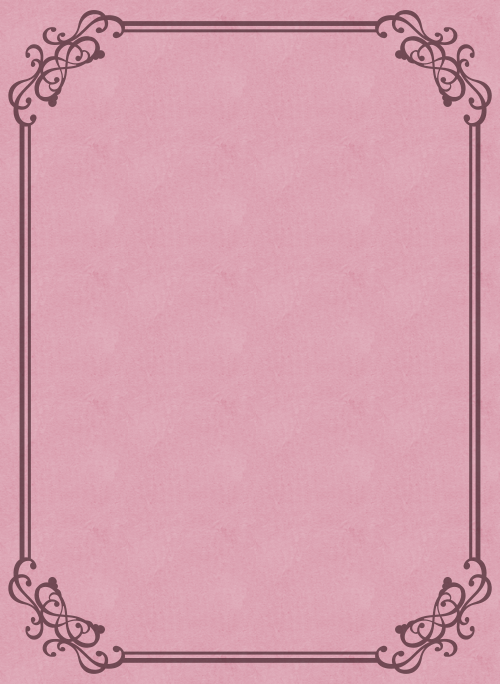「何で笑ってるんだよ」
「だって、小林君がおかしいから。真面目な顔してとぼけているようなことを言うから、おかしくって」
小林君は驚いていた。……あぁ、久しぶりに笑いすぎてお腹痛い。
「……なんだ。ちゃんと幸音も、そんな風に笑えるんだな。良かったよ」
「えっ?」
小林君は私と目が合うと、何故かすぐに目を逸らした。……よく見ると、小林君の頬が薄らと赤くなっていた。
「……もしかして、体調悪いの?顔赤いけど、熱があるんじゃ……」
私が小林君のおでこに触れようとした時、彼は私のその手をパシッと掴んだ。
「……熱なんてねぇから、気にするな。それと……」
小林君は、掴んでいる手をグイッと引っ張り、私に顔を近づけてきた。
「幸音は、笑顔が似合うな」
小林君は私に向かって微笑む。
私には、その笑顔が眩しかった。
この前までは、もう一生笑えないのかと思っていたのに、今はもう……何故か笑えてる。やっぱり、それは小林君のおかげだと思った。
「……ありがとう」
考え方も、人との関わり方も前とは少し変わっている。
それが、私にとってすごく嬉しかった。
黙々とやっているうちに、いつの間にか日が暮れて外は薄暗くなっていた。
「小林君、そろそろ終わ……」
私は言いかけて、途中で言うのを辞めた。
小林君は、びっしり自分で書いたノートの上にぐっすりと眠っていた。
「……お疲れ様」
起こさないように、そっと近くにあった膝掛けを小林君にかける。
コンコンコン
「失礼します。お嬢様……」
入ってきた遥貴さんに、小さな声で静かに、と言う。