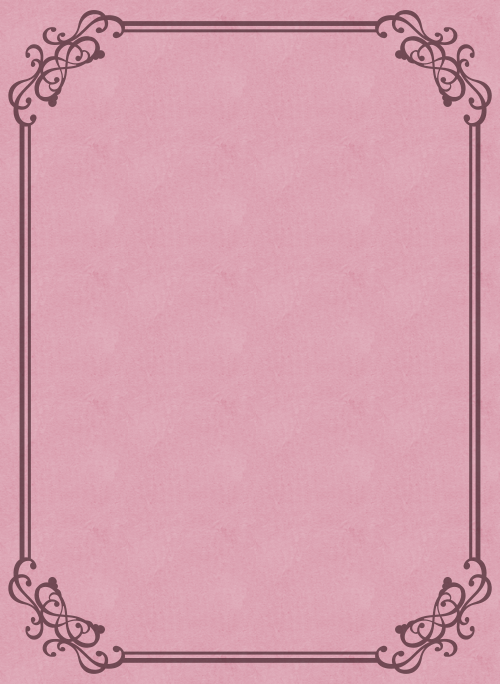遥貴さんはテーブルの上にそれを置くと、私の持っている楽譜を見た。
「曲を決めているのですか?」
「……うん。だけど、自分にあった曲が分からないの」
「そうですか……」
今思えば、私はコンクールで明るい曲しか弾いてこなかった。
……でも、今の私は弾けない気がする。
「お嬢様は、いつも明るい曲を弾いていましたが……今回はあえて真逆のものを弾いてみてはいかがですか?」
「真逆のもの……」
「お嬢様は、寂しさや悲しみ、そして苦しみ……そういう感情が伝わる曲を観客の方に聞いてもらった方がいいです」
そういう曲は、私があまり好まない曲だ。
コンクールでは、私の弾いた曲で皆が笑顔になってくれるものが良かったから。
……でも、今回は一度そういうものにしてみてもいいかもしれない。
「お嬢様」
急に呼ばれて、私は思わず遥貴さんの方を見る。
「人は、どんなに辛くても誰かにその悲しみを伝えるだけで、少し心が楽になるのです。ですから、お嬢様も間接的にはなりますが、ピアノの音でそれを伝えてみてはどうでしょうか」
「私の……この気持ちを、皆に?」
そんな事、考えてもみなかった。
ピアノで私の悲しみを伝えるなんて。
でも、音楽家は皆、自分の気持ちを音で表すものだ。
……それを表す曲は、あの曲しかない。
「……遥貴さんの言う通りだね。おかげで、私の弾きたい曲決まったわ。ありがとう、遥貴さん」
「いいえ。お役に立てて嬉しい限りです。……お嬢様は私にとって、命の恩人であり大切な人ですから……」
遥貴さんは微笑みながら、右手で私の頬に触れる。
「だから、お嬢様には今みたいに笑っていてほしいのです」
「……遥貴さん」
心が温かくなった。こんなにも優しくて、格好良くて私のことを大事にしてくれる執事なんて、きっと他にいないだろう。