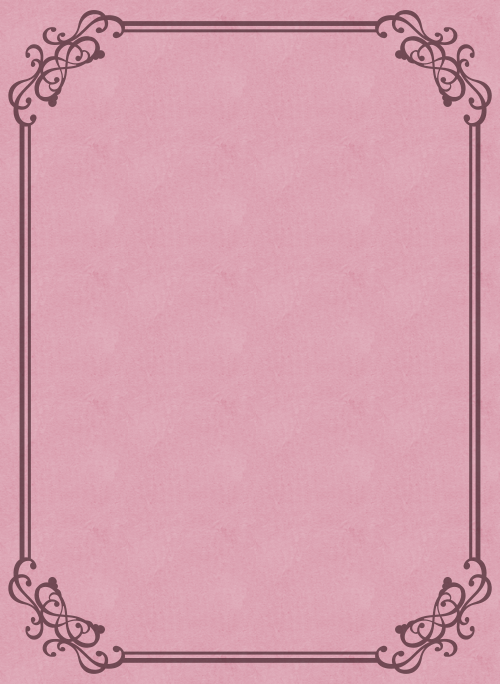だけど……観客から送られてくる拍手は、すごく小さくて、皆私の事なんて興味無さそうに私を見ていた。
……結果はいつも通り一位。けれど、誰にも喜ばれなかった演奏をしておいて一位を貰ったところで、私は全然嬉しくなかった。
その日を境に、私はコンクールに出場する事を辞めたんだ。そして、音ヶ崎学園からも逃げた。
だから今、この学校に通っている。……決してピアノが嫌いになった訳じゃない。だけど……私はただ、またコンクールに出て前のようになったらどうしようって怯えているだけだ。
「俺もあの日、コンクールを観に行っていた。……俺でも思ったが、如月の番の時だけ、妙に観客が酷かった。多分、誰かが如月の悪い噂でも流したんだろうが……」
ピアノ業界で、私の事をよく思わない人は多いだろう。だから、あの時あんな空気になったんだって今なら分かる。
小林君が言ってる事も……何となく心当たりがあった。
「如月」
小林君から名前を呼ばれて、彼の方へと視線を向ける。
「如月のピアノは、人の心を動かす力がある。だから、三年前のコンクールはただ周りが酷かっただけであって、如月の演奏はそんなに悪かった訳じゃない」
小林君は一度話を止めて、またゆっくりと話し出す。
「でも、観客側の反応っていうのも、プロの世界ではすごく大切な事だ。如月が深くショックを受けるのも分かる。けど……」
彼は私の方を見る。
「それがあったからこそ、皆が自分の演奏で喜んでくれた時、すげぇ気持ちいいと思わないか?」
その言葉に、私は目を見開いた。
……そんな事、考えた事がなかった。
私は今まで、反省だけをしてきてそれをどう改善するかなんて、考える余裕がなかった。
要するに、自分のピアノをもっと磨けばよかっただけの話なのかもしれない。
コンクールに出なかったこの三年間も、ピアノは家で弾いていた。