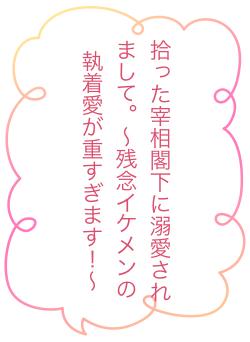冷えた夜風が、優しく頬を撫でる。長く湯に浸かって火照った体には、それがちょうどいい。
神官として与えられた自室のベッドにひとり腰掛けて、メリフェトスはぼんやりと窓の外--夜空に浮かぶ月を眺めている。
ぼうと輝く月を囲むように、白い光の輪が二重、三重に浮かんでいる。それを青紫色の瞳でなんとなしに眺めつつ、メリフェトスは無意識のうちに、ぽつりと呟いた。
「あとどれくらい、一緒にいられるんだろうな」
呟いてから後悔した。今更何を女々しいことを。アーク・ゴルドで、勇者カイバーンの放つ白い光に包まれたあの時、自分は既に終わっていたのだ。忌々しい人間の身体とはいえ、こうしてアリギュラの近くにいられるだけで奇跡。それ以上を望むなど、贅沢にもほどがあるというのに。
けれども。
人差し指で、そっと唇に触れる。触れ合ったあと、顔を真っ赤にしてすぐにそむけてしまう主の姿が瞼の裏に蘇り、メリフェトスの表情は自然と緩んでしまう。