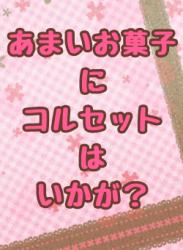人目を避けテラス席に移動したステファンとアリシアは、ランチを摂りながら互いに沈黙する。
気まずい訳ではないが、気持ちが乱れているので落ち着くのを待っているのだ。
冷静さを取り戻したアリシアは、ステファンに気付かれないように好みを聞き出すという大切な目標を思い出したのだが、彼の素敵さを再確認した今、そんな悠長なことをしている場合ではないのだと焦りだした。
「――あのね、ステファンに相談したいことがあるの」
アリシアの真剣な眼差しにステファンの心臓が早鐘を打つ。
「ステファンのこと、大好きなのにね、私、なにも知らなかったの」
ぽろぽろと泣き出したアリシアに、ステファンは慌ててハンカチを取り出した。
「どうしたの、アリシア」
渡されたハンカチは、アリシアがイニシャルを刺繍してプレゼントしたものだった。
(これだって、本に出てきたデザインを真似してステファンのイニシャルで作ったものだわ)
大切に持ち歩いてくれているハンカチも、彼の好みを思って作ったものでないことに悲しくなった。
「アリシア泣かないで。話してくれないと分かってあげられないよ」
「わ、わたし、ステファンのことをね、知らないって気付いたの。覚えているのは本の登場人物の好みばかりで。だから、こっそり聞き出そうとしたけど上手く質問できなくて。こんな婚約者でごめんね、ステファン」
(アリシアが僕のことで泣いている? ちょっと前に怒っていたのは、やっぱり僕のことなのか?)
諦めていた願いが目の前で急に叶っても、人はその現実を受け入れられず疑心暗鬼になるものである。
ステファンは、アリシアの心に触れた感触が信じられずに、事実を検証するのに忙しい。
全てに動揺した脳内では、手慣れたヒーロー語録から手頃な言葉が提供された。
「僕はどんなアリシアでも受け入れるよ。君のことが好きだからね」
引用元が直ぐに分かったアリシアは、しょんぼりと肩を落とす。
どうにかヒーローたちを突破したくて、ステファンの横に移動し彼の手をしっかりと握りしめて心からのお願いをした。
「私は自分の気持ちも上手く伝えられないのね。こんな私でも嫌いにならないでね」
「っ!……ならないよ。――なるわけ、ないよ。そんなこと」
やっと出てきた本音は、なんだか拙くて格好悪く思えてしまい、ステファンはいつもの言葉を使いたくて仕方ないのだった。
――本の世界から出てきた二人が、自分たちの物語を歩み始めるのは、ここからである
気まずい訳ではないが、気持ちが乱れているので落ち着くのを待っているのだ。
冷静さを取り戻したアリシアは、ステファンに気付かれないように好みを聞き出すという大切な目標を思い出したのだが、彼の素敵さを再確認した今、そんな悠長なことをしている場合ではないのだと焦りだした。
「――あのね、ステファンに相談したいことがあるの」
アリシアの真剣な眼差しにステファンの心臓が早鐘を打つ。
「ステファンのこと、大好きなのにね、私、なにも知らなかったの」
ぽろぽろと泣き出したアリシアに、ステファンは慌ててハンカチを取り出した。
「どうしたの、アリシア」
渡されたハンカチは、アリシアがイニシャルを刺繍してプレゼントしたものだった。
(これだって、本に出てきたデザインを真似してステファンのイニシャルで作ったものだわ)
大切に持ち歩いてくれているハンカチも、彼の好みを思って作ったものでないことに悲しくなった。
「アリシア泣かないで。話してくれないと分かってあげられないよ」
「わ、わたし、ステファンのことをね、知らないって気付いたの。覚えているのは本の登場人物の好みばかりで。だから、こっそり聞き出そうとしたけど上手く質問できなくて。こんな婚約者でごめんね、ステファン」
(アリシアが僕のことで泣いている? ちょっと前に怒っていたのは、やっぱり僕のことなのか?)
諦めていた願いが目の前で急に叶っても、人はその現実を受け入れられず疑心暗鬼になるものである。
ステファンは、アリシアの心に触れた感触が信じられずに、事実を検証するのに忙しい。
全てに動揺した脳内では、手慣れたヒーロー語録から手頃な言葉が提供された。
「僕はどんなアリシアでも受け入れるよ。君のことが好きだからね」
引用元が直ぐに分かったアリシアは、しょんぼりと肩を落とす。
どうにかヒーローたちを突破したくて、ステファンの横に移動し彼の手をしっかりと握りしめて心からのお願いをした。
「私は自分の気持ちも上手く伝えられないのね。こんな私でも嫌いにならないでね」
「っ!……ならないよ。――なるわけ、ないよ。そんなこと」
やっと出てきた本音は、なんだか拙くて格好悪く思えてしまい、ステファンはいつもの言葉を使いたくて仕方ないのだった。
――本の世界から出てきた二人が、自分たちの物語を歩み始めるのは、ここからである