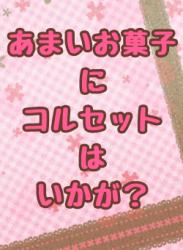昼、いつも通りに席を確保してステファンが来るのを待っていたアリシアの元に、ウルスラが現れる。
「ごきげんよう、アリシアさん。体調はもうよろしいのかしら?」
「ごきげんよう、殿下。はい、もう大丈夫です」
よかったわ、とウルスラが安堵したことに、アリシアは首を傾げる。
「実は、婚約者のいる殿方と踊ったことを近しい方々から注意されてしまったの。軽率だったと今では反省しているわ。わたくしがお願いしたら誰も断れないものね。申し訳ないことをしてしまったわね」
「い、いいえ。私こそ舞踏会に支障を出してしまい、申し訳ありませんでした」
アリシアが謝罪を受け入れて自らの失態を謝ると、ウルスラも笑ってくれたのだが、そこへキルヤ公爵子息のルーカスが割って入ったことで一気に緊張感が高まる。
「ウルスラ殿下、今度は一体なにをしようとしているのですか?」
「わたくしは、別に。――あなたには関係ありませんわ」
顔を逸らし立ち去ろうとしたウルスラの腕を、ルーカスは掴んで引き留めた。
「答えになっていない。先日、私も殿下も注意されたばかりでしょう。私はあなたの奔放さを諫めるよう国王陛下にお叱りを受けたんだ。せめて暫くは大人しくしてもらわなければ困る」
「っ! 一緒にいたのですから、わかっているわよ!」
ウルスラの声が思いのほか大きくて、周囲はしんと静まり返る。
「アリシア、なにがあったの?」
ランチを購入し戻ってきたステファンは、心配そうにアリシアに声を掛けた。
「丁度いい。ステファンにも言っておく。殿下の我儘につき合わせたことは申し訳なく思うが、そちらも婚約者がいる身なら安易になんでも引き受けるような行動は慎んでくれ」
「ちょっと、ルーカス! これは全てわたくしの配慮不足だと説明したでしょう。ステファンに非は無いのよ!」
「取り乱すのも感心しないし、そもそもステファンを庇うのも、周囲にいらない詮索を生むだろう」
ウルスラの顔が盛大に歪む。二人の仲がこじれているのは傍目に見ても明白であった。
気持ちを遠慮なくぶつけ合う姿に、周囲からは驚きと好奇の視線が向けられる。
その空気の変化すら気にする余裕のない二人に、ステファンは苛ついた。
「ルーカス様、殿下につらく当たらないでください。僕と踊っていたとき、殿下はずっとあなたが嫉妬してくれるか期待してばかりでしたから、お心は常にルーカス様に向いていらっしゃいます。ルーカス様がいらない詮索をする必要はありませんよ」
「「!」」
素直になれない気持ちを暴露されたウルスラと、嫉妬を隠し他者を語って牽制したことを見抜かれたルーカスは、二人そろって顔を赤くし動揺する。
「お、お前のような軽薄な者に、指摘されるようないわれはない。これは彼女と私の問題だ!」
どんな悪口も、ステファンには響かない。
嫉妬に嫌悪に羞恥心に。相手を試して本心を知りたがるウルスラがいじらしく、その仕打ちを喰らって怒るルーカスが羨ましくて仕方ないのだ。
「お、お言葉ですが。ステファンは軽薄ではありません。優しくて誠実で――。私の婚約者を悪く言わないでください!」
アリシアが、ステファンの手をしっかりと握ってルーカスの失礼な言葉に怒りをぶつけた。
好みも趣向もなにも知らないけれど、ステファンが優しくて素晴らしい人だということだけは、一緒に過ごした年月分だけアリシアが一番良く知っていたからだ。
「――すまない。少々言い過ぎた」
「これからはちゃんと気を付けるわ」
ルーカスとウルスラは行き過ぎた行動を反省した。
けれどその謝罪は、アリシアの言動に動揺したステファンと、怒鳴ってしまったことに驚いたアリシアには、全く届いていなかったのだった。
「ごきげんよう、アリシアさん。体調はもうよろしいのかしら?」
「ごきげんよう、殿下。はい、もう大丈夫です」
よかったわ、とウルスラが安堵したことに、アリシアは首を傾げる。
「実は、婚約者のいる殿方と踊ったことを近しい方々から注意されてしまったの。軽率だったと今では反省しているわ。わたくしがお願いしたら誰も断れないものね。申し訳ないことをしてしまったわね」
「い、いいえ。私こそ舞踏会に支障を出してしまい、申し訳ありませんでした」
アリシアが謝罪を受け入れて自らの失態を謝ると、ウルスラも笑ってくれたのだが、そこへキルヤ公爵子息のルーカスが割って入ったことで一気に緊張感が高まる。
「ウルスラ殿下、今度は一体なにをしようとしているのですか?」
「わたくしは、別に。――あなたには関係ありませんわ」
顔を逸らし立ち去ろうとしたウルスラの腕を、ルーカスは掴んで引き留めた。
「答えになっていない。先日、私も殿下も注意されたばかりでしょう。私はあなたの奔放さを諫めるよう国王陛下にお叱りを受けたんだ。せめて暫くは大人しくしてもらわなければ困る」
「っ! 一緒にいたのですから、わかっているわよ!」
ウルスラの声が思いのほか大きくて、周囲はしんと静まり返る。
「アリシア、なにがあったの?」
ランチを購入し戻ってきたステファンは、心配そうにアリシアに声を掛けた。
「丁度いい。ステファンにも言っておく。殿下の我儘につき合わせたことは申し訳なく思うが、そちらも婚約者がいる身なら安易になんでも引き受けるような行動は慎んでくれ」
「ちょっと、ルーカス! これは全てわたくしの配慮不足だと説明したでしょう。ステファンに非は無いのよ!」
「取り乱すのも感心しないし、そもそもステファンを庇うのも、周囲にいらない詮索を生むだろう」
ウルスラの顔が盛大に歪む。二人の仲がこじれているのは傍目に見ても明白であった。
気持ちを遠慮なくぶつけ合う姿に、周囲からは驚きと好奇の視線が向けられる。
その空気の変化すら気にする余裕のない二人に、ステファンは苛ついた。
「ルーカス様、殿下につらく当たらないでください。僕と踊っていたとき、殿下はずっとあなたが嫉妬してくれるか期待してばかりでしたから、お心は常にルーカス様に向いていらっしゃいます。ルーカス様がいらない詮索をする必要はありませんよ」
「「!」」
素直になれない気持ちを暴露されたウルスラと、嫉妬を隠し他者を語って牽制したことを見抜かれたルーカスは、二人そろって顔を赤くし動揺する。
「お、お前のような軽薄な者に、指摘されるようないわれはない。これは彼女と私の問題だ!」
どんな悪口も、ステファンには響かない。
嫉妬に嫌悪に羞恥心に。相手を試して本心を知りたがるウルスラがいじらしく、その仕打ちを喰らって怒るルーカスが羨ましくて仕方ないのだ。
「お、お言葉ですが。ステファンは軽薄ではありません。優しくて誠実で――。私の婚約者を悪く言わないでください!」
アリシアが、ステファンの手をしっかりと握ってルーカスの失礼な言葉に怒りをぶつけた。
好みも趣向もなにも知らないけれど、ステファンが優しくて素晴らしい人だということだけは、一緒に過ごした年月分だけアリシアが一番良く知っていたからだ。
「――すまない。少々言い過ぎた」
「これからはちゃんと気を付けるわ」
ルーカスとウルスラは行き過ぎた行動を反省した。
けれどその謝罪は、アリシアの言動に動揺したステファンと、怒鳴ってしまったことに驚いたアリシアには、全く届いていなかったのだった。