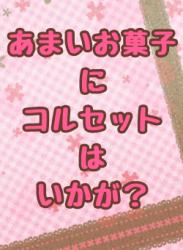アリシアが登校を再開した日、変わらずステファンは彼女を迎えに邸へ立ち寄り、二人は馬車に乗って学園へと向かう。
途中、アリシアが本を持っていないことに気付いたステファンが心配して声をかけた。
「アリシア、今日は本を持っていないけど大丈夫なの? 忘れたなら取りに戻ろうか?」
「ううん、大丈夫よ。読書は暫くお休みすることにしたの」
いつだって何処に行くのにも、絶対にお気に入りの本を手に持っていたアリシアが本を手放したことに、ステファンは驚愕する。
「どういう心境の変化? もしかして帰りに新しい本を買いに行きたいとか?」
「違うわ」
「なら、昔のお気に入りが再熱したけど見つけられなかったとか?」
「違うわよ! もっと、大切なことを優先することにしたの」
(大切なこと? アリシアが本より大切に思うことって、なんだ?!)
ステファンは内心激しく動揺したが、表面上はいつも通りに穏やかに取り繕う。
この五年間、多種多様なヒーローを演じ続けた彼は、その努力の先に高度な演技力を身に着けていたのだ。
「それでね、ステファンに聞きたいことがあるの」
「うん、なんでも聞いて。なんでも話して欲しいな」
彼が演じた数多のヒーローは、ヒロインに向けるべき優しい語彙力をステファンに授けてもいた。
アリシアの全てを受け止めるべく、ステファンは過去に培った令嬢の理想を総動員して向き合うことにした。
「す、好きなものって、なんだっけ? ほら、お菓子とか、色とか」
「――そうだね。この前アリシアと一緒に食べに行ったフルーツタルトは気に入ったかな。色は特にこだわりはないけど、灰色を良く選んでしまう。アリシアの瞳の色と同じせいだね」
途端にアリシアの顔から表情が滑り落ちる。
(なんで? どうして! なにその反応?!)
前半は『また一緒に行きたい』とヒロインがおねだりをし、後半はヒロインが照れる流れである。
アリシアは、それらの引用元が分かったので、欲しい答えを聞き出せなかったのだと理解し絶望したのだった。
(ヒーローたちが予想以上に手強い。ステファンが遠いわ。――ううん。弱気になってはダメよ!)
気を取り直したアリシアは、再びステファンに質問したのだが、学園に着くまでの短い時間では、なにひとつ答えを得ることはできなかったのだった。
途中、アリシアが本を持っていないことに気付いたステファンが心配して声をかけた。
「アリシア、今日は本を持っていないけど大丈夫なの? 忘れたなら取りに戻ろうか?」
「ううん、大丈夫よ。読書は暫くお休みすることにしたの」
いつだって何処に行くのにも、絶対にお気に入りの本を手に持っていたアリシアが本を手放したことに、ステファンは驚愕する。
「どういう心境の変化? もしかして帰りに新しい本を買いに行きたいとか?」
「違うわ」
「なら、昔のお気に入りが再熱したけど見つけられなかったとか?」
「違うわよ! もっと、大切なことを優先することにしたの」
(大切なこと? アリシアが本より大切に思うことって、なんだ?!)
ステファンは内心激しく動揺したが、表面上はいつも通りに穏やかに取り繕う。
この五年間、多種多様なヒーローを演じ続けた彼は、その努力の先に高度な演技力を身に着けていたのだ。
「それでね、ステファンに聞きたいことがあるの」
「うん、なんでも聞いて。なんでも話して欲しいな」
彼が演じた数多のヒーローは、ヒロインに向けるべき優しい語彙力をステファンに授けてもいた。
アリシアの全てを受け止めるべく、ステファンは過去に培った令嬢の理想を総動員して向き合うことにした。
「す、好きなものって、なんだっけ? ほら、お菓子とか、色とか」
「――そうだね。この前アリシアと一緒に食べに行ったフルーツタルトは気に入ったかな。色は特にこだわりはないけど、灰色を良く選んでしまう。アリシアの瞳の色と同じせいだね」
途端にアリシアの顔から表情が滑り落ちる。
(なんで? どうして! なにその反応?!)
前半は『また一緒に行きたい』とヒロインがおねだりをし、後半はヒロインが照れる流れである。
アリシアは、それらの引用元が分かったので、欲しい答えを聞き出せなかったのだと理解し絶望したのだった。
(ヒーローたちが予想以上に手強い。ステファンが遠いわ。――ううん。弱気になってはダメよ!)
気を取り直したアリシアは、再びステファンに質問したのだが、学園に着くまでの短い時間では、なにひとつ答えを得ることはできなかったのだった。