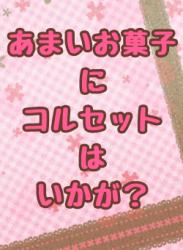昼、ステファンとアリシアは待ち合わせをしてカフェテリアで一緒にランチを摂る。
「私はAランチが食べたいわ」
「分かった。いつも通り席を確保して待っていてくれ」
言われた通りに席を確保したアリシアは、ステファンが戻ってくるまで持ってきた本を開いて読書する。
「ごきげんよう、カルツィ伯爵のご令嬢さん。少しお時間よろしいかしら?」
声をかけたのは、第一王女のウルスラであった。
「ごきげんよう、殿下」
「あなたはステファンの婚約者なのよね? ちょっとお願いしたいことがあるのだけど――」
アリシアの憧れる金髪に緩く巻かれたカールが軽やかに弾む。その美しい水色の瞳に見惚れたアリシアは、思わずコクリと頷いた。
「お待たせ、アリシア。ウルスラ殿下、どうして――」
「ステファンが婚約者を気にしていたから直接交渉に来たのです。彼女は快く引き受けてくれたわ」
その言葉に、ステファンは少しだけ眉根を寄せた。本当は思い切り顔を顰めたい衝動に駆られたのだが、相手が王女殿下ではそうはいかない。
「では、お二人に招待状をお渡ししますわ。当日のダンスのパートナーをよろしくお願いしますね」
差し出された二通の封筒を、アリシアは躊躇いなく受け取った。
ウルスラが立ち去ったあと、ステファンは我慢できずに愚痴をこぼした。
「どうして引き受けたんだい。せめて僕が戻るまで待ってくれたらよかったのに」
「だって、殿下のダンスのお相手をするだけでしょ? 殿下がね、この本のファンだって言っていたの。ヒーローがステファンにそっくりで、一度だけダンスを踊りたいからってお願いされたのよ」
笑顔のアリシアは、ステファンが他の女性とダンスを踊ることに全く感情を揺さぶられないらしい。
それどころか、ウルスラがアリシアと同じ本を好きだと知って喜んでいるのだ。
「本当に、アリシアはそれでいいの?」
「? ええ。ウルスラ殿下ってヒロインの姿にそっくりよね。当日が楽しみだわ」
本の世界を纏ったままのアリシアは、起こる出来事の全てを物語に当てはめて心を守り続けている。
それをよく知るステファンは、これ以上彼女の考えを否定できないのだ。
(僕は、アリシアの本の世界の一部でしかないんだな。――どこで間違えたんだろう)
こういったことは初めてではない。そのたびにステファンは言いようのない悲しみに襲われる。
自責の念に駆られて無駄と知りつつ記憶を遡っては、己の過ちをずっと探していた。
けれどあの日、閉じた心が開け放たれて笑顔を取り戻したアリシアの記憶が、間違えてなどいないと全てを肯定するのだった。