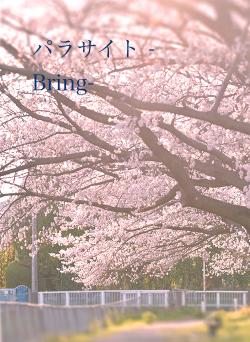いわゆる『神話』と呼ばれるものであろう話を、考えるそぶりも見せずに淡々と話す彼の姿は、まるでそれを見てきたかのようだった。いっさいの事柄を知っている…いや、知るべきだったのだろうか?それとも、必然として覚えたのか。聞きたい気持ちを抑えながら彼の目を見た。
「そんな…ことがあったなんて。でも、それほどならもっと有名になってもいいのに」
「今でもじゅうぶん人気で有名ですよ。母数を見てはいけません」
いまの壮大な話を聞いていると、もう自分が軽く潰されそうな勢いだと感じる。
「人間って…ちっぽけだね」
「神から見たらそうですね。虫ケラというか」
存外、思ったことははっきり言うタイプらしい。でも、変に小難しい話を延々とされるよりはいい。それに、彼は早口だから余計に。
「そうだ、つい話が長くなってしまったので、これをどうぞ」
「…これは?」
「お守りです。その鈴、綺麗な音色だと思いませんか?」
チリン、と鳴らしてしばらく見つめてみる。ふつうのお守りに見える。
が、そのときだれかの影が目に映った。見覚えはないが、懐かしい雰囲気をまとっていた。
「これは…」
「あなたがいま、会いたいひとを映し出すお守りです。同じお守りを持っているひとを映すと、そのひとが来てくれたり、行けたりします」
会いたいひと。私がいまこの瞬間、会いたいひと。それで繋がった。父の『会いたい人と会える』という言葉。間違いではなかったのだ。
「本当だったんだ…」
「え?」
鈴には懐かしい面影の女性が映り込んでいる。しかし、顔までは分からなかった。私はこの旨を説明した。すると、彼は驚いた表情をした。
「それは、この村の人間でなければ知らないはずですが…」
また彼は考え込んだ。その深い青の瞳を宿しながら。
日が暖かい色を持ち始めたとき、境内の奥から厳格な雰囲気をまとう男性が歩いてきた。
「君が、この村に越してきたのか」
「…父と一緒に、ふたりで」
「なるほど。物好きな連中だな」
低く威厳のあるその声は、地震でも起こせそうなほど太い芯があった。そして、どこか見覚えのある雰囲気だった。偶然なのかもしれない。でも、少し聞いてみたい気持ちもある。
結局、その日はその雰囲気に圧倒されて、何も言えずに帰ってしまった。
「そんな…ことがあったなんて。でも、それほどならもっと有名になってもいいのに」
「今でもじゅうぶん人気で有名ですよ。母数を見てはいけません」
いまの壮大な話を聞いていると、もう自分が軽く潰されそうな勢いだと感じる。
「人間って…ちっぽけだね」
「神から見たらそうですね。虫ケラというか」
存外、思ったことははっきり言うタイプらしい。でも、変に小難しい話を延々とされるよりはいい。それに、彼は早口だから余計に。
「そうだ、つい話が長くなってしまったので、これをどうぞ」
「…これは?」
「お守りです。その鈴、綺麗な音色だと思いませんか?」
チリン、と鳴らしてしばらく見つめてみる。ふつうのお守りに見える。
が、そのときだれかの影が目に映った。見覚えはないが、懐かしい雰囲気をまとっていた。
「これは…」
「あなたがいま、会いたいひとを映し出すお守りです。同じお守りを持っているひとを映すと、そのひとが来てくれたり、行けたりします」
会いたいひと。私がいまこの瞬間、会いたいひと。それで繋がった。父の『会いたい人と会える』という言葉。間違いではなかったのだ。
「本当だったんだ…」
「え?」
鈴には懐かしい面影の女性が映り込んでいる。しかし、顔までは分からなかった。私はこの旨を説明した。すると、彼は驚いた表情をした。
「それは、この村の人間でなければ知らないはずですが…」
また彼は考え込んだ。その深い青の瞳を宿しながら。
日が暖かい色を持ち始めたとき、境内の奥から厳格な雰囲気をまとう男性が歩いてきた。
「君が、この村に越してきたのか」
「…父と一緒に、ふたりで」
「なるほど。物好きな連中だな」
低く威厳のあるその声は、地震でも起こせそうなほど太い芯があった。そして、どこか見覚えのある雰囲気だった。偶然なのかもしれない。でも、少し聞いてみたい気持ちもある。
結局、その日はその雰囲気に圧倒されて、何も言えずに帰ってしまった。