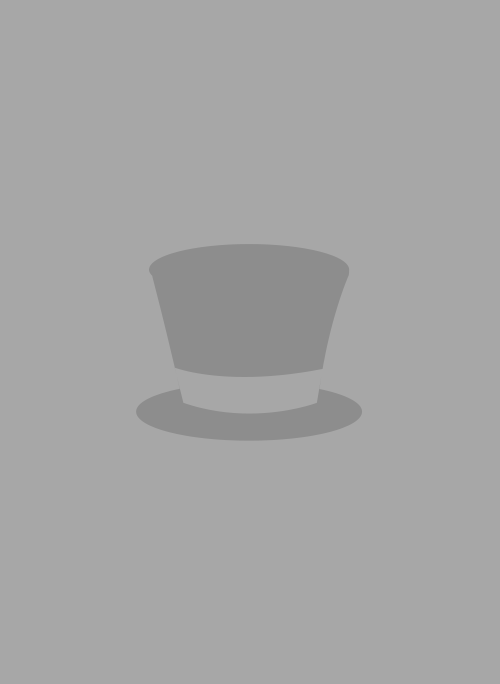葬儀が終わり独りきっりになった。
謹慎したままで何処にも行けない俺はアパートに引き籠るようになっていた。
俺はずっと妻が亡くなった場所の上で横になっていた。
彼女がどんな思いで死んでいったのか知りたくなったんだ。
第一発見者は俺だ。
だから彼女がどの方向を見ていたのか解るのだ。
その場所に何があるのか?
最期に何を見たのか気になった。
俺は妻が非番の時、何をやっているのか知らない。
警察官の勤務体制は概ね日勤と宿直の後の開けと非番の繰返しだ。
六日毎にそれを繰返し、一週間で換算すると休みの曜日が一日ずつズレていく仕組みだった。
だからなかなか休みが交わらないのだ。
ふとワンピースに目が止まった。
それは初めてのデートの時に着用した物だった。
腰のあたりからふんわり広がり、裾の部分で狭まるデザイン。
彼女が見た目だけで選んだって言ってた。
可愛いらしさを演出するためのようだ。
でもそんなことをしなくても彼女は充分可愛いかった。
でもそれは実用的ではなかった。
裾が思ってた以上に広がらなかったのだ。
確かに可愛い。
可愛いすぎた。
だから彼女は足が縺れて階段から落ちたのだ。
彼女から言わせると、俺が強引に手を引いたから体毎持って行かれたそうだ。
幸い下には俺がいたから怪我はなかった。
だから俺は彼女の言い分が正しいと本当は感じていたのだ。
でも認めたくなくて、ワンピースのせいにしてしまったのだった。
おっちょこちょいの慌てん棒だと勝手に判断して、全身全霊で彼女を守っていくことを誓った。
それなのに彼女は殺されてしまったのだ。
もし俺と結婚さえしなかったら、彼女はまだ生きていたのかも知れない。
俺があの日。
埼玉県警の連絡を受けた時彼女のミニパトに乗り込まなかったら、こんな悲劇は起こらなかったのだ。
そう、アイツはラジオとして俺に逮捕されていたはずなのだ。
俺だけ恨まれれば済む話だったのだ。
四十九日が終わるまで遺影も祭壇もそのままになるはずだった。
でもお別れになる日が札を一枚返す毎に近付いてくる現実が怖かった。
立て看板の様な枠の中に戒名が書いてある塔婆を小さくした板が刺さっている。
それを初七日、二七日、三七日と続き最後が七七日の四十九日になるのだ。
連れ合いを亡くした母は姉一家と暮らしている。
だから生家に戻っても誰も居ないのだ。
ただ、お墓だけはある。
妻は其処に入る予定だった。
ふと屈託のない笑顔を思い出した。
その途端に涙が溢れ出した。
俺は泣けていなかったのだ。
あまりにも突然で……、何をすることも出来なかったのだ。
泣くことも忘れただ呆然としていただけだった。
ただアイツを逮捕することだけを考えていた。
彼女の傍で見守ることもしないでただ犯人逮捕のことだけを頭においた。
何て薄情な男だろう?
俺は自問自答しながら妻の片身となったワンピースを抱き締めていた。
ふと、遺影が目に止まった。
(彼女が見ている。だらしない俺の姿を……)
俺は居たたまれなくなって押し入れに入った。
その時玄関のドアを開ける音がした。
『あれっ、誰も居ないわね』
その声は姉貴だった。
(ヤバい、此処から出られない)
俺は縮こまって時間が流れていくことだけを祈っていた。
「あっ、叔父ちゃんめっけ」
いきなり押し入れが開いて瑞穂が入ってきた。
「シッ!!」
俺は唇に指を立てた。
「叔父ちゃん泣いていたの?」
あどけない瑞穂が悪気のない質問をする。
俺は何も言えないでただ瑞穂を黙らせようとしていた。
『悪い、瑞穂を頼むわ。私は買い物に行ってくるわね』
姉貴はそう言いながら出掛けて行った。
『瑞穂、オジちゃんとかくれんぼしていてね』
出掛けたと思って安心していたら、突然声を掛けられて俺の心臓は止まりそうになった。
「なぁんだ叔父ちゃんかくれんぼだったのか?」
瑞穂はそう言ってくれた。本当は知っているのだと思っていたのだ。
こんな小さな体で俺を気遣ってくれる瑞穂。
俺はこの小さな相棒のためにも強く生きて行かなければならないと思っていた。
俺は警察を辞める決意をした。
勿論アイツを逮捕したくて仕方ない。
だけど、蚊帳の外に出されて何も出来ない状態だったからだ。
アイツに悔しさをぶつけたいのに、無実だと結論着けられて手も足も出せない状態だったのだ。
(アイツの無実を俺は証明した。それなのに服役させておいて、今度は事件とは無関係だと言い張る。あの事件の時ちゃんと捜査をしてくれれていたら、俺の女房は殺されてなくても済んだのだ)
俺は又腸を煮え繰り返していた。
実はあの後アイツは行方をくらませたのだ。
だから本当の犯人だと俺は睨んでいたのだ。
そんな奴を放っておく警察が信じられなくなっていたのだ。
(妻を殺したのは絶対にアイツだ。なのに……)
俺は自分が押さえられなくなっていたのだ。
本当は解っていた。アイツに妻が殺せるはずがないってことが……
それでも頭の中では犯人だと決め付けていたのだ。
何故妻を殺したのか?
その理由を知りたかった。
でも此処にいたら何も出来ないと思っていた。
誰かに胸の内を解ってもらいたくて、先輩の住む家に行き愚痴を吐いた。
迷惑千万だと思う。でも先輩はそんな俺を暖かく迎えてくれた。
「実は辞表出してきました」
「又思い切ったことを……夢はどうする? 警視庁の捜査一課に入るんじゃなかったのか? ま、それもあの事件以来夢と消えたか?」
先輩はそれ以上言わなかった。
「これから警備員の職でも探してみます。俺一人だったら何処でも暮らしていけますから……」
頭を下げて帰ろうとしたとこだった。
「探偵って道もあるぞ。お前さんはきっとそのラジオを追うつもりなんだろう?」
俺の痛いとこを突く先輩。
やはり俺の本音は見破られていたのだった。
「探偵になるのに特別な資格はいらないよ。専門学校もあることにはあるが、そんな勉強しなくても探偵になれる。届けは警察の中にある公安だ」
その話は聞いていた。
でも探偵になろうとは考えてもいなかったのだ。
「尾行や張り込みは刑事だったんだから職業柄身に付いているんだろう? それを活かしてみたらどうだ?」
先輩は俺に適した職業だと言ってくれていたのだ。
先輩の助言を受けて、確かに改めて訓練は必要ないと思い始めていた。
開業するには公安委員会に届けを出さなければいけない。
そのやり方を先輩から伝授され、俺は地元の警察を尋ねた。
通路側に開くドア。
靴置き場のみある玄関。
その横に広がる、洋間が事務所だ。
其処で探偵としての仕事を請け負うことにした。
でもその前に、実地訓練が必要だった。
いくら資格はいらないと言われても、やはりキャリアが物を言う仕事だと思った。
探偵の仕事は地味で地道な捜査だそうだ。
でもそれは刑事のそれと大差ないように思われた。
とは言え、迷子のペット探しは別物だった。
時間が経てば経つほど捜せなくなるのは当たり前。
でもそんな状態になったからの依頼も良くあることらしい。
猫の顔写真だけで見つけ出すのは至難の技だ。
飼い主からの特徴などの情報と良く見比べて確保しなければならない。
それ以外の動物だったら盗まれたとして訴えられることだろうから。
浮気の調査はプライバシー保護の観点からも慎重を擁す。
実際の探偵業は地味で浮気調査や人探しなどで占められているようだ。
最初の仕事は迷子の子猫探しだった。
普通の猫がシャム猫のみたいな仔猫を産んだ。
それを親戚の子供が欲しいと言ってきたそうだ。
「乳離れしたら取りに来ることになっているのだけど……」
そう言った依頼人の脇で仔猫がジャレていた。
「この猫ではないのですか?」
俺の質問に首を振った。
「姿格好は同じです。でもその子が気に入ったのが居なくなったもう一匹の方でして……」
「それじゃ、これと同じ猫を探せば良いのですね?」
俺の質問に依頼人は頷いた。
俺は早速、依頼人宅の後にある畑から捜索を始めた。
少し行ってみて、畑の脇に線路があることに気付いた。
断崖の下にあったから気付かなかったのだ。
その横には橋が架かっていた。
(此処で落ちて電車に轢かれていたら……)
そうも思い目を凝らしたけどそれらしい物は何もなかった。
そんな時にとある目撃情報が入った。
「迷子の猫を知人が保護していますが……」
「その方を教えていただけますか?」
「いえ、私から聞いてみます」
その人はそう言うと、線路の上に架かる橋を渡り始めた。
「『迷子の猫を預かっているの』お友達の子供がそう言っていたのよ。シャム猫のようだなって思ったの」
(間違いない)
俺はほくそ笑んでいた。
「『ママが迷子の猫だって言ってたの。飼い主が現れたら返すんだって言ってたよ』その子はハッキリとそう言ったわ。だから私から聞いてみますね」
その家の脇に立って、行為に甘えることにした。
俺は警察官だった癖が抜けきれずに、聞き耳を立てていた。
『昨日お宅で見た猫なんだけど、迷子なんですってね。実は、公園の前の家の猫らしいの』
その人は俺のことは一切出さずに言ってくれた。
『その家の人に、家に居るって言っちゃたの?』
言葉を遮るようにその家の人が言った。
『言ってないよ。ただ心当たりがあるって……』
『それが、言っちゃったってことよ。それであの人は何て?』
『あっ、ごめんだから言ったのはあのじゃなくて』
『じゃあ誰よ!?』
何故か雲行きが怪しくなってきた。
『アンタのお陰であの猫返さなくてはいけなくなっちゃったじゃない!!』
後日、俺がお礼に伺った時のことだ。
あのシャム猫を保護してくれていた方が怒鳴り込んで来た。
『何で、何で黙っていなかったの!!』
その剣幕は物凄くてあの時受けた印象とは違っていた。
その後も協力者に罵声を浴びせた。
『だから私は別に……』
その人本当に何も言ってなかった。
その人は誰も傷付かないようにと最大限の配慮をしたのだ。
俺は怖くなった。
迷子の猫が可愛くなって、隠して飼う気だと知ったからだ。
子供の前では保護したと言っていても、それが本音とは限らないと解ったからだ。
探偵になったばかりの俺は物凄く貴重な体験をさせてもらったのかも知れない。
ただ、あの奥さんだけは気の毒な思いさせたと思っている。
基本的に飼い猫の場合、何かに追われたりしていなければ近くに居るのが原則だ。
だから俺は近所の人に声を掛けたのだ。
まさかこんなことになろうとは思ってもいなかったのだ。
怒鳴り込んで来た奥さんは依頼者の裏の畑で遊んでいた仔猫を連れて帰ったのだ。
迷子か捨てられた猫だと思い込み、奪ったのだ。
知らなかったとは言え、それは立派な犯罪行為なのだ。
謹慎したままで何処にも行けない俺はアパートに引き籠るようになっていた。
俺はずっと妻が亡くなった場所の上で横になっていた。
彼女がどんな思いで死んでいったのか知りたくなったんだ。
第一発見者は俺だ。
だから彼女がどの方向を見ていたのか解るのだ。
その場所に何があるのか?
最期に何を見たのか気になった。
俺は妻が非番の時、何をやっているのか知らない。
警察官の勤務体制は概ね日勤と宿直の後の開けと非番の繰返しだ。
六日毎にそれを繰返し、一週間で換算すると休みの曜日が一日ずつズレていく仕組みだった。
だからなかなか休みが交わらないのだ。
ふとワンピースに目が止まった。
それは初めてのデートの時に着用した物だった。
腰のあたりからふんわり広がり、裾の部分で狭まるデザイン。
彼女が見た目だけで選んだって言ってた。
可愛いらしさを演出するためのようだ。
でもそんなことをしなくても彼女は充分可愛いかった。
でもそれは実用的ではなかった。
裾が思ってた以上に広がらなかったのだ。
確かに可愛い。
可愛いすぎた。
だから彼女は足が縺れて階段から落ちたのだ。
彼女から言わせると、俺が強引に手を引いたから体毎持って行かれたそうだ。
幸い下には俺がいたから怪我はなかった。
だから俺は彼女の言い分が正しいと本当は感じていたのだ。
でも認めたくなくて、ワンピースのせいにしてしまったのだった。
おっちょこちょいの慌てん棒だと勝手に判断して、全身全霊で彼女を守っていくことを誓った。
それなのに彼女は殺されてしまったのだ。
もし俺と結婚さえしなかったら、彼女はまだ生きていたのかも知れない。
俺があの日。
埼玉県警の連絡を受けた時彼女のミニパトに乗り込まなかったら、こんな悲劇は起こらなかったのだ。
そう、アイツはラジオとして俺に逮捕されていたはずなのだ。
俺だけ恨まれれば済む話だったのだ。
四十九日が終わるまで遺影も祭壇もそのままになるはずだった。
でもお別れになる日が札を一枚返す毎に近付いてくる現実が怖かった。
立て看板の様な枠の中に戒名が書いてある塔婆を小さくした板が刺さっている。
それを初七日、二七日、三七日と続き最後が七七日の四十九日になるのだ。
連れ合いを亡くした母は姉一家と暮らしている。
だから生家に戻っても誰も居ないのだ。
ただ、お墓だけはある。
妻は其処に入る予定だった。
ふと屈託のない笑顔を思い出した。
その途端に涙が溢れ出した。
俺は泣けていなかったのだ。
あまりにも突然で……、何をすることも出来なかったのだ。
泣くことも忘れただ呆然としていただけだった。
ただアイツを逮捕することだけを考えていた。
彼女の傍で見守ることもしないでただ犯人逮捕のことだけを頭においた。
何て薄情な男だろう?
俺は自問自答しながら妻の片身となったワンピースを抱き締めていた。
ふと、遺影が目に止まった。
(彼女が見ている。だらしない俺の姿を……)
俺は居たたまれなくなって押し入れに入った。
その時玄関のドアを開ける音がした。
『あれっ、誰も居ないわね』
その声は姉貴だった。
(ヤバい、此処から出られない)
俺は縮こまって時間が流れていくことだけを祈っていた。
「あっ、叔父ちゃんめっけ」
いきなり押し入れが開いて瑞穂が入ってきた。
「シッ!!」
俺は唇に指を立てた。
「叔父ちゃん泣いていたの?」
あどけない瑞穂が悪気のない質問をする。
俺は何も言えないでただ瑞穂を黙らせようとしていた。
『悪い、瑞穂を頼むわ。私は買い物に行ってくるわね』
姉貴はそう言いながら出掛けて行った。
『瑞穂、オジちゃんとかくれんぼしていてね』
出掛けたと思って安心していたら、突然声を掛けられて俺の心臓は止まりそうになった。
「なぁんだ叔父ちゃんかくれんぼだったのか?」
瑞穂はそう言ってくれた。本当は知っているのだと思っていたのだ。
こんな小さな体で俺を気遣ってくれる瑞穂。
俺はこの小さな相棒のためにも強く生きて行かなければならないと思っていた。
俺は警察を辞める決意をした。
勿論アイツを逮捕したくて仕方ない。
だけど、蚊帳の外に出されて何も出来ない状態だったからだ。
アイツに悔しさをぶつけたいのに、無実だと結論着けられて手も足も出せない状態だったのだ。
(アイツの無実を俺は証明した。それなのに服役させておいて、今度は事件とは無関係だと言い張る。あの事件の時ちゃんと捜査をしてくれれていたら、俺の女房は殺されてなくても済んだのだ)
俺は又腸を煮え繰り返していた。
実はあの後アイツは行方をくらませたのだ。
だから本当の犯人だと俺は睨んでいたのだ。
そんな奴を放っておく警察が信じられなくなっていたのだ。
(妻を殺したのは絶対にアイツだ。なのに……)
俺は自分が押さえられなくなっていたのだ。
本当は解っていた。アイツに妻が殺せるはずがないってことが……
それでも頭の中では犯人だと決め付けていたのだ。
何故妻を殺したのか?
その理由を知りたかった。
でも此処にいたら何も出来ないと思っていた。
誰かに胸の内を解ってもらいたくて、先輩の住む家に行き愚痴を吐いた。
迷惑千万だと思う。でも先輩はそんな俺を暖かく迎えてくれた。
「実は辞表出してきました」
「又思い切ったことを……夢はどうする? 警視庁の捜査一課に入るんじゃなかったのか? ま、それもあの事件以来夢と消えたか?」
先輩はそれ以上言わなかった。
「これから警備員の職でも探してみます。俺一人だったら何処でも暮らしていけますから……」
頭を下げて帰ろうとしたとこだった。
「探偵って道もあるぞ。お前さんはきっとそのラジオを追うつもりなんだろう?」
俺の痛いとこを突く先輩。
やはり俺の本音は見破られていたのだった。
「探偵になるのに特別な資格はいらないよ。専門学校もあることにはあるが、そんな勉強しなくても探偵になれる。届けは警察の中にある公安だ」
その話は聞いていた。
でも探偵になろうとは考えてもいなかったのだ。
「尾行や張り込みは刑事だったんだから職業柄身に付いているんだろう? それを活かしてみたらどうだ?」
先輩は俺に適した職業だと言ってくれていたのだ。
先輩の助言を受けて、確かに改めて訓練は必要ないと思い始めていた。
開業するには公安委員会に届けを出さなければいけない。
そのやり方を先輩から伝授され、俺は地元の警察を尋ねた。
通路側に開くドア。
靴置き場のみある玄関。
その横に広がる、洋間が事務所だ。
其処で探偵としての仕事を請け負うことにした。
でもその前に、実地訓練が必要だった。
いくら資格はいらないと言われても、やはりキャリアが物を言う仕事だと思った。
探偵の仕事は地味で地道な捜査だそうだ。
でもそれは刑事のそれと大差ないように思われた。
とは言え、迷子のペット探しは別物だった。
時間が経てば経つほど捜せなくなるのは当たり前。
でもそんな状態になったからの依頼も良くあることらしい。
猫の顔写真だけで見つけ出すのは至難の技だ。
飼い主からの特徴などの情報と良く見比べて確保しなければならない。
それ以外の動物だったら盗まれたとして訴えられることだろうから。
浮気の調査はプライバシー保護の観点からも慎重を擁す。
実際の探偵業は地味で浮気調査や人探しなどで占められているようだ。
最初の仕事は迷子の子猫探しだった。
普通の猫がシャム猫のみたいな仔猫を産んだ。
それを親戚の子供が欲しいと言ってきたそうだ。
「乳離れしたら取りに来ることになっているのだけど……」
そう言った依頼人の脇で仔猫がジャレていた。
「この猫ではないのですか?」
俺の質問に首を振った。
「姿格好は同じです。でもその子が気に入ったのが居なくなったもう一匹の方でして……」
「それじゃ、これと同じ猫を探せば良いのですね?」
俺の質問に依頼人は頷いた。
俺は早速、依頼人宅の後にある畑から捜索を始めた。
少し行ってみて、畑の脇に線路があることに気付いた。
断崖の下にあったから気付かなかったのだ。
その横には橋が架かっていた。
(此処で落ちて電車に轢かれていたら……)
そうも思い目を凝らしたけどそれらしい物は何もなかった。
そんな時にとある目撃情報が入った。
「迷子の猫を知人が保護していますが……」
「その方を教えていただけますか?」
「いえ、私から聞いてみます」
その人はそう言うと、線路の上に架かる橋を渡り始めた。
「『迷子の猫を預かっているの』お友達の子供がそう言っていたのよ。シャム猫のようだなって思ったの」
(間違いない)
俺はほくそ笑んでいた。
「『ママが迷子の猫だって言ってたの。飼い主が現れたら返すんだって言ってたよ』その子はハッキリとそう言ったわ。だから私から聞いてみますね」
その家の脇に立って、行為に甘えることにした。
俺は警察官だった癖が抜けきれずに、聞き耳を立てていた。
『昨日お宅で見た猫なんだけど、迷子なんですってね。実は、公園の前の家の猫らしいの』
その人は俺のことは一切出さずに言ってくれた。
『その家の人に、家に居るって言っちゃたの?』
言葉を遮るようにその家の人が言った。
『言ってないよ。ただ心当たりがあるって……』
『それが、言っちゃったってことよ。それであの人は何て?』
『あっ、ごめんだから言ったのはあのじゃなくて』
『じゃあ誰よ!?』
何故か雲行きが怪しくなってきた。
『アンタのお陰であの猫返さなくてはいけなくなっちゃったじゃない!!』
後日、俺がお礼に伺った時のことだ。
あのシャム猫を保護してくれていた方が怒鳴り込んで来た。
『何で、何で黙っていなかったの!!』
その剣幕は物凄くてあの時受けた印象とは違っていた。
その後も協力者に罵声を浴びせた。
『だから私は別に……』
その人本当に何も言ってなかった。
その人は誰も傷付かないようにと最大限の配慮をしたのだ。
俺は怖くなった。
迷子の猫が可愛くなって、隠して飼う気だと知ったからだ。
子供の前では保護したと言っていても、それが本音とは限らないと解ったからだ。
探偵になったばかりの俺は物凄く貴重な体験をさせてもらったのかも知れない。
ただ、あの奥さんだけは気の毒な思いさせたと思っている。
基本的に飼い猫の場合、何かに追われたりしていなければ近くに居るのが原則だ。
だから俺は近所の人に声を掛けたのだ。
まさかこんなことになろうとは思ってもいなかったのだ。
怒鳴り込んで来た奥さんは依頼者の裏の畑で遊んでいた仔猫を連れて帰ったのだ。
迷子か捨てられた猫だと思い込み、奪ったのだ。
知らなかったとは言え、それは立派な犯罪行為なのだ。