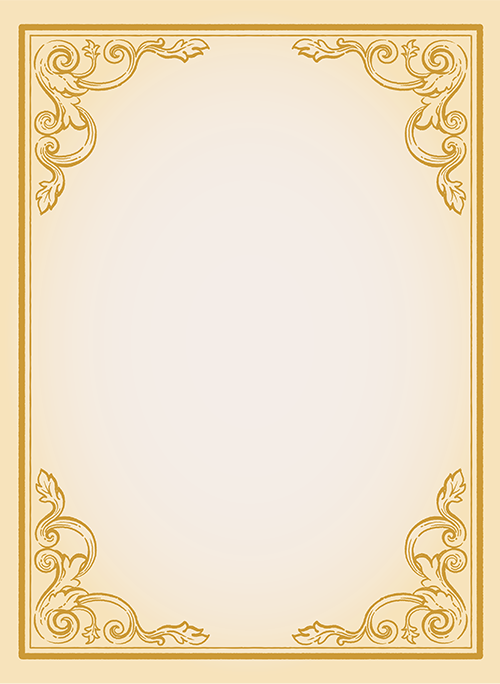「ありがとうございましたー!」
最後のお客を見送り、フィアナは扉の横で元気に頭を下げた。すっかり酔って気持ちよくなった二人連れの客たちは、ひらひらと手を振りながら夜の町へと消えていく。完全に見えなくなったとき、フィアナは鼻をかすめた香りにあっと息を呑んだ。
(春のにおいだ)
ほんのりと香る、春の訪れを告げる花のにおい。今日は日中あたたかかったから、どこかで蕾がほころびたのだろう。肌にあたる夜風の冷たさあって、ひと月ほど前に比べれば少しも気にならない。
もう少し暖かくなってくれば、一晩そとで過ごしたとしても風邪をひく心配もないだろう。そんな夜であったなら、わざわざ『彼』を拾って家にあげてやることもなかったかもしれない。
なんとなくそんなことを思って、その『彼』が誰であったかに思い当たり、動きを止めた。
〝はいはーい。つらいのはわかりますけどー。ここ外。こんなところで寝ていたら、寒くて凍えちゃうか、誰かに身ぐるみひっぺがされちゃいますよー?〟
〝……わたしは、わたしはっ〟
〝あー、もう、だめだコレ。おにいさーん? ちょっと失礼しますよー。支えますから、立ってくださいね。せーの!〟