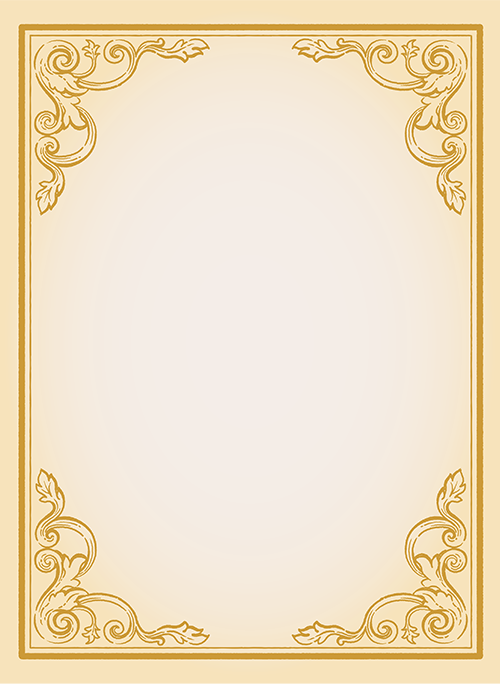「で、最初の質問に戻るけど……。エリアスちゃんが、本気でフィアナちゃんのことを好きなのかどうかって話よね?」
「はい」
ほんの少しばかり緊張しつつ、フィアナは頷く。けれども、恋愛マスター・キュリオの答えはひどくあっけらかんとしたものだった。
「ごめんなさーい。それは私にも、わっかんないのよねぇ~」
「え??」
「だってぇ。大真面目に言っているようにも見えるし、見ようによっては、フィアナちゃんをからかって遊んでいるようにも見えなくないものぉ」
「からか……っ、最悪じゃないですか!」
傍からみたら、そんな風に見えていたのか。そう憤慨するフィアナだったが、「ちがう、ちがう」とキュリオは人差し指を立てて首を振った。
「からかうって言っても、悪い意味じゃなくて。そうね。たとえるなら、5・6歳くらいの子供が、好きな子にわざといじわるして遊んじゃう、みたいな?」
「……はい?」
「ほら、フィアナちゃんって打てば響くと言うか、こう痒いところに手が届くような気持ちいい突っ込みをするじゃない? それが楽しくて、わざとちょっかいだしているようにも見えなくないのよねぇ~」
「それが本当だとしたら、結構いろいろと腹立たしいのですが」