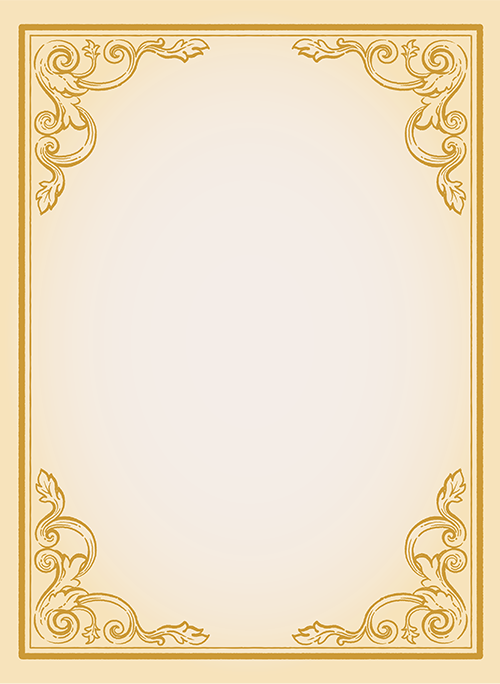「……けど。もし、本当にエリアスさんが私のことを好きでいてくれているんだったら、いつか、ちゃんとお断りしなきゃいけないのかなって、そう思います」
しょんぼりと告げたフィアナに、キュリオが目を瞠る。ややあって、カラコロと氷を遊ばせながら、彼は微笑んだ。
「フィアナちゃんは真面目ねえ。けど、あれだけ毎日塩対応しているんだもの。いまさら改まって、お断りする必要もないんじゃなーい? それにエリアスちゃんの場合、フラれたくらいじゃ、ちっともめげないような気がするけど」
「それは……」
確かに、とフィアナは嫌でも納得してしまう。というより、いい笑顔で「何度お断りされようが、この溢れる愛をフィアナさんにお伝えし続けますから!」などとのたまう姿が容易に想像できて、頭が痛い。
どんよりとため息を吐くフィアナに、キュリオはくすりと笑みを漏らした。
「いいじゃない。フィアナちゃんくらいの年だと、なんでも白黒はっきりつけたくなっちゃうかもだけど、それが正解とは限らないもの。エリアスちゃんがお客さんとして来ている間は気にしなくていいし、その先に踏み込もうとしてくるなら、そのときに考えればいーの」
「そんなもんでしょうか」
「そんなもんでいーのよ、所詮、男と女なんて」
そのように、キュリオははっきりきっぱり断言した。さすがはマダム、踏んできた場数が違う。若干首を傾げつつも、フィアナは彼に尊敬の目を向けた。