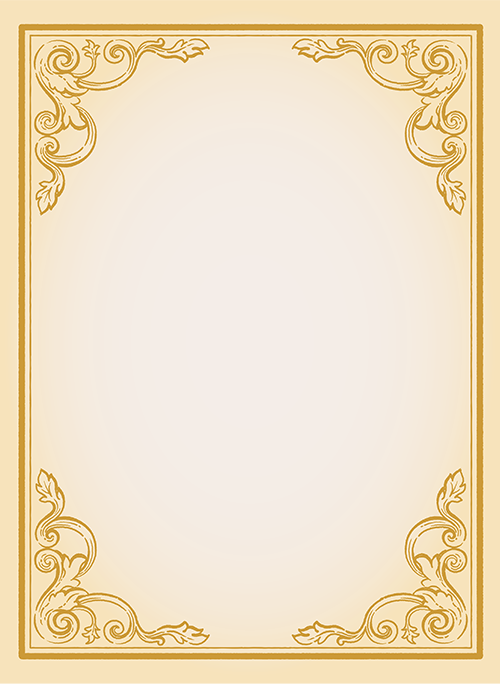「……ふーん。お前、ソイツにあれこれ言い寄られたりしているみたいだけど、そこはそんなに嫌じゃないんだ」
「え? 嫌だけど、普通に」
「即答かよ! 可哀そうだな!? って、そうじゃなくて。……そいつのこと、根本的に嫌いってわけじゃないんだなってこと」
微かに目を泳がせながら言われたその一言に、フィアナはきょとんと瞬きをした。
言われてみれば、「気持ち悪い」だの「面倒くさい」だの、これまで散々な反応を返してきたフィアナであるが、それはあくまでエリアスの言動に対して。エリアス本人に対して、嫌悪感を抱いたことは不思議となかった。
なにせ、悪い人間ではないのだ。斜め上の角度から好き好きアピールを惜しみなくしてくる以外は、エリアスは紳士だ。いわゆるイヤラシイ目を向けてくることもないし、無理やり触れて、なんてことも絶対にしない。
この間だって、不注意で転びそうになっていたところを受け止めてくれて――。
そこまで考えたところで、フィアナの顔はぽんと赤くなった。あの夜、月夜の下で後ろから引き寄せられ、熱の籠った大人の男の声で囁かれたことを思い出してしまったのである。