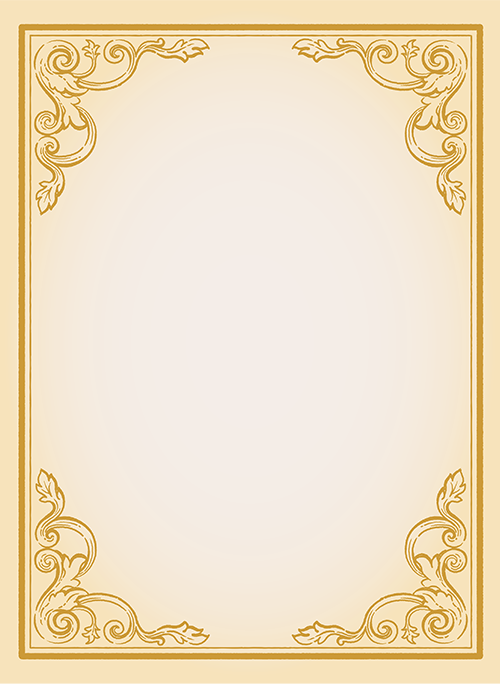その証拠に、もはや定位置となりつつあるカウンターの左端の席に座り、エリアスはうっとりとした眼差しをフィアナに向け続けていた。
「フィアナさん……。今日の貴女も、なんとお可愛い……」
頬を染め、色気を漂わせながら、エリアスが呟く。男も女も関わりなく、ほかの客の目がエリアスに釘付けとなるなか、フィアナだけは心底呆れた様子で頬杖をついた。
「あのですね。昨日も同じ場所で、同じように私を見ていたじゃないですか。毎日、毎日、私の顔ばかり眺めていて飽きないんですか?」
「飽きるなど、とんでもない! 昨日のフィアナさんは、昨日のフィアナさん。今日のフィアナさんは、今日のフィアナさんです! 明日も明後日もその先も、毎日新しい貴女の表情を瞼の奥に刻み込んでいきたいのです!」
「意味が分からない上に、若干気持ち悪いです」
「フィアナさんが虫けらを見るような目で私を……! しかし! そんな、新しい表情も、いい……っ!!」
「本格的に気持ち悪いですからね!? ……あーもう、好きにしてください。なにか注文あったら呼んでくださいね」
フィアナはくるりと背中を向け、無情にもすたすたと歩き去る。フィアナさーん、と情けない声が後ろから追いかけてくるが、ここは頑なに無視を決め込むことにした。