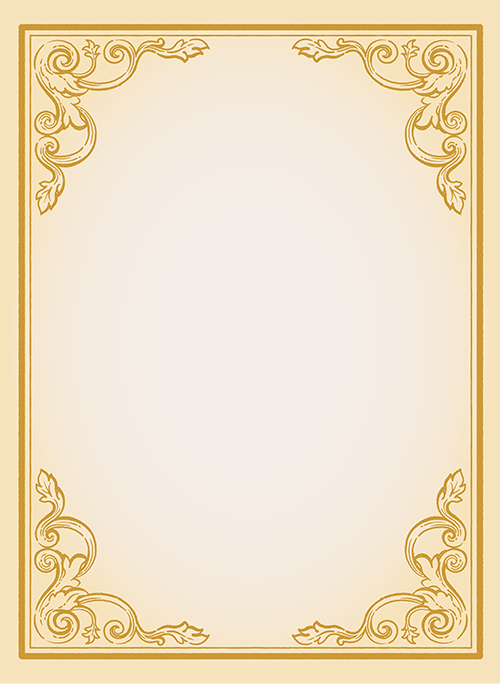それから数日の間。シャルツの計らいによりエリアスは政務を休んだが、3日を過ぎた頃から復帰をした。半年分の記憶がない以外は体に異常が見られず、登城しても問題がないだろうとの医者の判断が下ったからだ。
一方で、記憶を失ってからというもの、エリアスはグレダの酒場に通うのをぱたりとやめてしまった。
「記憶がないまま、皆さまにお会いするのが申し訳ない。エリアス様は、そのようにお考えのようです」
相変わらず買い物などの手伝いに来てくれながら、ダウスはそのようにフィアナに話した。ちなみに店周辺の警備隊のパトロールも、事件のある前と同じに強化されたままだ。その二つは、記憶を無くしても継続してくれたらしい。
主人に代わり、フィアナのことを案じてくれているのだろう。ダウスを始め、エリアスの家から来てくれるお手伝いの方は皆、フィアナを見るとエリアスの様子を話してくれる。
このところの彼は、まっすぐに家に帰っているということ。それでも忙しいのか、毎日帰りは遅いということ。家にも書類を持ち帰って何やら調べものをしていること。
そうやって無心になっているようで、時たまひどく寂しそうに虚空を眺めて、ため息を吐いているということ。
「おそらくエリアス様は、フィアナ様に会えないのが寂しいのでしょう」
「そんなはずは……。エリアスさん、私のこと覚えていないはずですから」
「潜在欲求というやつでしょうな」
フィアナが苦笑をすると、ダウスはお馴染みの皺を眉間にくっきり刻んだまま、やれやれと首を振った。
「詳しくは存じませんが、ハリネズミのキーホルダー。あれはフィアナ様とのお揃いなのでしょう。手を止めているときのエリアス様は、度々それを取り出して眺めていらっしゃいます。思い出すことは出来ずとも、刻まれた記憶が語り掛けるんでしょう」
――ダウスは何気なく言ったのかもしれないが、その一言にフィアナは支えられていた。
たとえ今は思い出せなくとも、ふたりの思い出が消えたわけじゃない。重ねてきた想いは、どこかにちゃんと眠っている。
フィアナがそのように信じて、今日も一日、グレダの酒場で頑張る一方。
「おっさん! 邪魔するぞ!」
そのように勢いよく、マルスはエリアスの屋敷を訪ねていた。ダウスからマルスの来訪を聞いて、迎えに来たのだろう。玄関扉まで出てきたエリアスは、仁王立ちをして自分を睨むマルスに苦笑をした。
「マルスくん……でしたよね。今週もいらっしゃったんですね」
「おっさんが俺たちのことを思い出すまで、毎週通うつもりだぜ。嫌だったら、さっさと記憶を取り戻すんだな」
ふんと鼻を鳴らすマルスに、エリアスはやれやれと肩を竦める。それでも中に入れてくれたのは、マルスが自分のために来てくれているのだという負い目のためだろう。
さて、先ほども話が出たように、マルスはエリアスが記憶をなくしてからというものの、安息日のたびに彼の屋敷を訪ねている。その目的は、エリアスの記憶を取り戻すこと。その糸口になればと、彼はこれまでのことやフィアナの近況など、思いつく限りのことをエリアスに話して聞かせていた。
普段と違って、エリアスはマルスを書斎に通した。ちょうど、ダウスが書斎にお茶の用意を整えたばかりだったらしい。様々な資料の並ぶ本棚に目を奪われながら部屋に入ったマルスは、ふと、エリアスの机の上に複数の紙が広げられていることに気づいた。
「悪い。仕事中だったか?」
こんなんでも、彼が一国の未来を背負う宰相であることを思い出し、マルスは素直に謝る。ところがエリアスは、マルスの視線の先にあるものに気づくと、緩やかに首を振った。
「いえ、こちらは……。個人的な調べもの、といったところでしょうか。とにかく仕事ではありませんので、気になさらず」
「ふうん」
あまり見られたくないものだったのだろう。それらの書類をさりげなく隠すように、エリアスが別の用紙をそれらの上にかぶせた。
エリアスはマルスにソファ席を勧めながら、にこにこと微笑んだ。
「さてさて。今日はどんな話をしてくれるんですか?」
「……来といてなんだけどさ。なんだってあんた、俺が来ると嬉しそうなんだよ」
「だって、マルスくんの話は楽しいですから。ニースさんに、キュリオさん。ベクターさんに、カーラさん。本当に、グレダの酒場に集まる方々は個性的で面白いです」
「そりゃ結構だ。俺としては、フィアナの話題に耳を傾けてほしいんだがな」
「フィアナさんは……」
その名を聞いた途端、エリアスのアイスブルーの瞳が微かに揺れた気がした。けれども、マルスがそれを確かめようとするよりも早く、エリアスは視線を伏せる。次にこちらを見たとき、彼はもとの柔らかな笑顔に戻っていた。
「もちろん、フィアナさんの話も興味深いです。まさか私が、街のお嬢さんとお付き合いをしているだなんて」
「てめえ……っ」
他人事のように話すエリアスに、思わずマルスは立ち上がりかける。しかし、気色ばむマルスを、意外にも鋭い視線でエリアスが射抜いた。
「マルスくんが私を訪ねてくれるのは、フィアナさんのため。そうですね?」
確信を持った、迷いのない目線。それを受け止めて、マルスも力強く頷いた。
「ああ、そうだ。おっさんの記憶を取り戻して、一日でも早くあいつのもとにおっさんを返す。それが俺の狙いだよ」
「やはり。しかし、いくら大切な幼馴染とはいえ、彼女のために毎週私のもとを訪ねてくださるとは。……よほど特別な幼馴染、なんですね」
ひやりとした空気が、部屋に満ちるのを感じた。どこか懐かしい感覚にマルスは囚われる。以前にもエリアスは、こういう目を自分に向けたことがあった。あれはいつのことだっただろうか。
ややあって、マルスはぷはっと噴き出した。
「おっさん、あからさまに威嚇しすぎ。ていうか、記憶がないのにそんなに威嚇するって、俺のことどれだけ警戒しているんだよ?」
「っ! すみません」
我に返ったように目を瞬かせたエリアスは、気まずそうに目を逸らす。そんな彼を見ながら、――自分も馬鹿なやつだと、マルスは思った。
だから、せめて。せめて、胸を張って。
「――おっさんの考える通りだよ。俺はフィアナが好きだ。幼馴染としてじゃなくて、女としてあいつを見ている」
まっすぐにエリアスを見据えてそう話すと、エリアスの切れ長の目がゆっくりと見開かれる。ややあって、彼は緊張が解けるように苦笑した。
「では、私はマルスくんにとって恋敵ですね」
「だな。だから俺は、おっさんが嫌いだ」
「いいんですか? こんな、恋敵に塩を送るような真似をして」
それな、と。マルスは胸の内で大きく頷いた。
このままエリアスの記憶が戻らなければ。そう思ったことは、一度や二度の騒ぎではない。それどころか、こうしてエリアスを訪ねているこの瞬間だって、そんな考えが鎌首をもたげてきてしまう。
だが、このままではダメだ。このままでは、フィアナが心から笑えないのだ。
「恋敵がどうとか、関係ない。あいつのため、――あいつの、笑顔のため。一日でも早く、あんたにはもと通りになってもらう。これが俺の、好きな女の守り方だ!」
堂々とエリアスを睨んで宣言すると、エリアスはただただ目を丸くしてマルスを見つめる。そんな彼に、マルスは「ただし!」と人差し指を突き付けた。
「記憶が戻ったあとは、油断するなよな。俺が手を出さないのは、あんたの隣にいるフィアナが笑っているからだ。もしもあいつを泣かせるようなことがあれば、一切遠慮しない。その時は全力であいつを奪いに行く。わかったな!」
「マルスくん……」
まぶしいものを見るようにエリアスが目を細める。けれども、それは一瞬のことで、すぐにエリアスはにこにこと内の読めない笑顔を浮かべた。
「君みたいな人、たまに登場しますよね。女性に人気のロマンス小説の、イイ人なんですけど報われない当て馬さんとかに」
「うるさい、はったおすぞ」
じろりと睨みつつ、薄々自覚のあるマルスは口をへの字に曲げる。そんな彼に「冗談です」とくすくす笑ってから、ふとエリアスは真剣な顔をした。
「……マルスくん。あなたにだけ、話しておきたいことがあります。聞いてくれますか」
少しの誤魔化しもない、まっすぐな声音に、マルスの背中は自然と伸びる。
「わかった」
わずかに緊張をはらませてマルスが頷くと、エリアスが微笑む。それから彼は、ゆっくりと唇を開いた――。