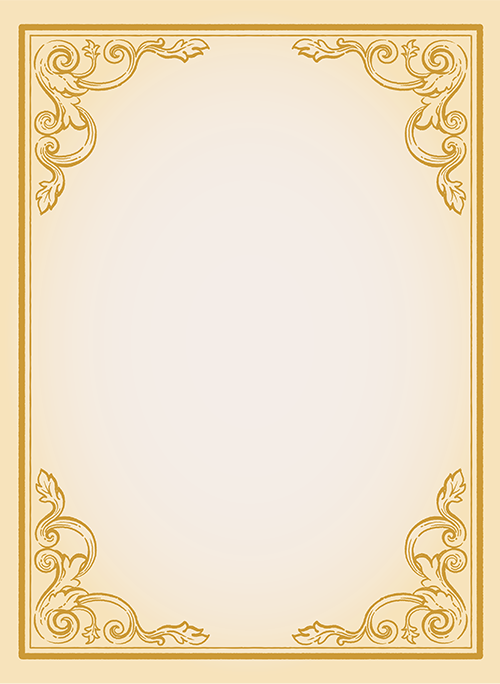「だはぁぁぁぁ……。ことごとく行く気が起きません」
眩い緑の葉が、一層の濃さを増した頃。いつものようにグレダの酒場に現れたエリアスは、カウンターに突っ伏してそのようにクダを巻いていた。
これまでも仕事の愚痴を漏らすことはあったが、ここまで露骨なのは初めてである。どこか体調でもおかしいのだろうか。……そもそも体調が悪いのに酒場にくるわけもないのだが、そのようにフィアナが心配していると、キュリオがカラコロと氷を鳴らしながら苦笑した。
「もしかして、どこぞのパーティに招かれたのかしら? そっか。今年ももう、そんな時期になったのね」
「お、社交シーズンってやつだな! お貴族様、お得意の!」
得意げにポテトを突き出したニースに、エリアスはますますペチョンと机に潰れた。
社交シーズン。それは主に春先から初夏にかけて最盛期を迎える、上流階級を対象とした浮かれポンチシーズンである。
その時期、上流階級の人々は、お互いの屋敷でパーティを催し交流を深める。優雅でやんごとなく見えるこの習慣だが、貴族の皆々様にとっては一種の陣取り合戦であり、同時に若い世代にとっては生涯のパートナーを見つけるための重要な場だ。
当たり前のことながら、フィアナはこれまで社交の場とやらとは縁もゆかりもなかったので、出席したことはない。けれども、その時期になるとキュリオの店がいそがしくなるので、漠然と知ってはいた。
だからフィアナは、ふわっとした知識のまま、首を傾げた。
「どうしてエリアスさんは、そんなに行きたくないんですか? パーティってきっと、美味しいものもたくさん食べれるんですよね?」
「もちろん!! 時間をゴリゴリとられるからですよ! 私はパーティなんか出席している暇があったら、こちらに来てフィアナさんを愛でていたんです!!」
「エリアスちゃん。今日も潔いくらいのブレなさねー」
悔しそうに両手を握りしめるエリアスの隣で、キュリオがのんびりと笑う。するとエリアスは、唇を尖らせて愚痴をつづけた。
「……それに、ああいう場は気が抜けないんですよ。みんな笑顔の下で腹の探り合いをしていて、誰に近づくのが益になるか値踏みしあっている。あそこでいただくお酒も料理も、ちっとも美味しく感じません」
「そんなに嫌だったら、断っちまえばいいんじゃないか?」
あっけらかんとそう言ったのは、ニースである。だがエリアスは、嫌そうに首を振った。
「それが、残念ながらそうもいかないんです。私も出来る限り、のらりくらりとかわしているんですが、さすがに陛下が出席するレベルのものはお断りするわけにもいかなくて」
「むしろエリアスちゃんレベルの立場のひとが、のらりくらりかわせてることのほうが驚きだわ」
呆れた顔で言ってから、キュリオは「きゃぴっ」と効果音がつきそうに、両手を顔の横で握りしめた。
「いいじゃない、お貴族様のパーティ! 私は好きよ? ファッションの流行の最先端が知れるし、なんといっても華やかだもの」
「キュリオさんもたまに、パーティに出席してますもんね」
「ふふふ、私はデザイナーだからね。依頼してくれたら、エリアスちゃんのことも飾り付けてあげるのに。エリアスちゃん綺麗だし、スタイルもいいもの。飾り甲斐があって、楽しそうだわ~」
声を弾ませるキュリオにフィアナは気づかされた。パーティとなれば、当然エリアスも着飾るはずだ。ただでさえ飛びぬけて容姿の優れたエリアスのことだ。正装をした姿はさぞ、似合っていることだろう。
(それはちょっと、見たいかも)
ぽっと顔を赤らめて、フィアナはエリアスを凝視する。それにすかさず気づいたのはキュリオだった。
「ほらほら~。フィアナちゃんも、素敵におしゃれしたエリアスちゃんが見たいって」
「きゅ、キュリオさん!」
「なっ、フィアナさん、それは本当ですか!?」
がたりと音を立てて、エリアスが飛び起きる。
「見たいんですか!? 見たいんですね!? そうだ、私のパートナーとして一緒にパーティに行きませんか!?」
「行きませんし行けません! 着ていけるような服もないですし……」
「あら? ドレスが心配なら、私がどうとでもするわよ? なんか面白そうだし」
「そこ、悪乗りしない! そもそも私が行ったところで、場違いすぎるって話ですよ」
「本当に……? 本当の、本当に、ダメですか……?」
「うっ」
捨てられた子犬のようにうるうると潤んだ一対の瞳に見つめられ、フィアナは答えに詰まる。はたから見れば、いい大人が小娘相手に何をしているんだという話だが、幸か不幸かフィアナには一定の効果を見せていた。
けれども最終的に、フィアナはぷいとエリアスの「お願いビーム」を振り切るようにそっぽを向いた。
「無理なものは無理です。どうしてもひとりが嫌だったら、キュリオさんを誘ってください」
「そこで私をチョイスするのはおかしくない……?」
「すみません、キュリオさん……。私、エスコートをするならフィアナさん以外にありえないと、前世の前世のそのまた前世くらいから胸に刻んでいまして……」
「いや別に、エスコートして頂戴なんて一言も言っていないからね??」
抗議をするキュリオをよそに、エリアスは再びペチョンとカウンターに潰れる。そして、「行きたくありません……、実に行きたくありません……」とうじうじ愚痴り始めた。
そんな風にエリアスが悪あがきをした、とある夜。
――彼らは知る由もなかったが、グレダの酒場の前で、ひとりの男が光の漏れ出る窓を眺めていた。
「へーえ? ここにあの、エリアスがね」
興味深げに呟いて、エリアスに負けず劣らず整った顔に、男は緩やかな笑みを浮かべる。
そうして彼は軽やかに地を蹴ると、愉快そうに踵を返した。
「――彼のいないときに、遊びに来るよ。待っていてね、可愛い子猫ちゃん」
人知れずそうほほ笑みかけると、男は足音も立てずに夜の街へと溶けていったのであった。