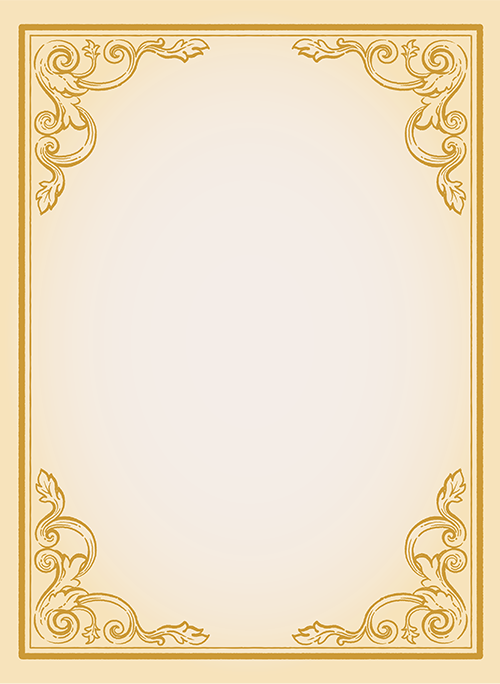さてギルベール儀典長について、ここで改めて復習をしておこう。
彼はメイス国のシャルツ王に仕える重鎮の最古参であり、国が公式で行う各式典の総まとめ役だ。そして、就任以来、儀典室に対し予算の見直しを要請してきたエリアスとは、一時は犬猿の仲とまで言われた老紳士である。
さて、そんなギルベール儀典長だが、当然彼もまた今日はお休みであった。仕立ての良いグレーのロングコートを羽織り、のんびりと公園散歩を謳歌していたと見える儀典長もまた、意外な場所で出会ったエリアスに驚いているようであった。
「閣下も、公園散歩ですかな」
どこか不思議そうな――言うなれば、「この男が、休日に散歩?」と疑ってかかるような――顔で、ギルベール儀典長が尋ねる。するとエリアスは、余所行きの笑顔を張り付けたまま、にこりと頷いた。
「はい。久しぶりに、動物園なんぞ覗いてみたりしていました」
「閣下が? 動物園?」
「ええ。大変に、有意義な時間を過ごせましたよ」
「はぁ」
狐につままれたような顔で、ギルベール儀典長は頷く。
「儀典長も、こちらにはお散歩に?」
「はい。孫が、動物園を見たいというものですから。先にジェラートを食べたいというものですから、いまは妻が、そこのカフェに孫たちと入っていまして」
「おや、ますます奇遇ですね。私たちも先ほどまで、あちらのカフェにいたのですよ」
「それは、それは……」
言いながら、ギルベール儀典長の目が控えめに泳ぐ。そして、エリアスの長身の後ろで出来るだけ気配を隠そうと頑張るフィアナに、ぴたりと向けられた。
「ところで、そちらのお嬢さんは……?」
(来た!!!!)
びくりと肩を震わせ、フィアナは青ざめた。このまま見なかったフリをしてくれたらと思ったが、やはり、そうは問屋が卸さない。
「ああ、彼女は……」
少しばかり表情を緩めて、エリアスがフィアナを見る。しかし、その唇が取り返しのつかない何かを言おうとするのを、フィアナは遮った。
「ばったり、公園で会ったんです!」
エリアスが虚を衝かれたように瞬きする。その隙に、フィアナは早口に続けた。
「両親が店をやっていて、たまにエリアスさんが食べに来てくださるんです。それでエリアスさんとは知り合いなんですが、さっき偶然そこのカフェの前で会って、ごちそうしてもらっちゃったんです」
「ほお。そういうわけでしたか」
なぜ庶民の娘が宰相と一緒にいるのか。そのように訝しんでいたのだろう。どこかほっとした様子で、ギルベール儀典長が頷く。根はやさしい人間なのか、理由に納得した途端、彼はフィアナににこにこと問いかけた。
「お店というのは、どちらにあるのですかな。閣下が通われるのですから、ご両親はさぞ、素晴らしい料理人なのでしょう」
「いえいえ。味には自信がありますが、店構えはしがない街の酒場です」
「なるほど! 大衆酒場ですか。それはいい。私も、若い頃は身分を隠して、あちこち飲み歩くのを楽しみとしたものです」
「本当ですか? エリアスさんのほかにも、市井でお酒を飲む方がいるんですね」
……小さな嘘の上に、虚構が組み立てられていく。そちらの方がよほど真実めいていて、本当に自分とエリアスとは、たまたま、偶然、この場所に居合わせたような気さえしてくる。
きしりと、胸の奥が軋む心地がする。それでも、フィアナは嘘を塗り固めていく。
その方が自然だから。その方が正しいから。
それこそが、本来あるべき自分とエリアスの距離だから。
――だが、そんなフィアナの手を、エリアスがぎゅっと握る。そして、あろうことかぐいと手を引き上げると、ギルベール儀典長に宣言するように見せつけた。
「申し訳ありません、ギルベール儀典長。私たちは偶然出会ったのではありません。私が彼女を誘い、この公園でデートをしていました。嘘を吐いてしまったことを謝ります」
「…………んん??」
「な、にゃ、にゃぁぁぁあ!?」
信じられない気持ちで、フィアナは叫んだ。せっかく誤魔化すことができたのに、いったい、この男は何を考えているのだろうか。そのように青ざめるフィアナをよそに、エリアスは澄ました顔で続ける。
「そういうわけですので、私たちはそろそろ失礼いたします。ギルベール儀典長も、奥さまとお孫さんとのお出かけ、どうぞ楽しんでくださいね。それでは、お互い良い休日を」
「は、はあ」
ぽかんと呆けた顔で見送るギルベール儀典長を置いて、エリアスがフィアナの手を引く。足早なエリアスに引きずられるようにして、フィアナは木漏れ日の下を小走りに駆けながら、前を行く背中に抗議した。
「ちょっと、エリアスさん!? どうして、あんなことを!?」
「…………」
「エリアスさん、待ってください!! 待ってってば……!」
その時、一際強く腕を引かれ、フィアナは軽く前につんのめった。そのままバランスを崩し、フィアナは倒れこむようにしてエリアスの胸のなかに抱きとめられた
「っ、え、エリアスさん!?」
仰天して暴れるフィアナが、捕えるエリアスの腕は一層の強さを増すばかりだ。
フィアナは慌てた。まだギルベール儀典長が近くにいるかもしれない。もしかしたら、ほかにもエリアスの同僚がいるかもしれない。こんな場面を見られたら、エリアスに迷惑をかけてしまうかもしれない。宰相としてのキャリアに、傷をつけてしまうかもしれない――。
「……わかっているんです。貴女が、私を庇ってくださろうとしたんだということ」
ぽつりと、フィアナの肩に顔を埋めたまま、エリアスが呟いた。表情は隠したまま、聞いたこともないような声で――まるで泣いているような声で、彼は呻いた。
「わかっていても、つらいんです、不甲斐ないんです。貴女に、嘘を吐かせてしまったこと」
「エリアス、さん……?」
「私たちの関係は、隠さなくてはいけないものですか?」
顔を上げ、切なげな色を湛えたアイスブルーの瞳が、まっすぐにフィアナを射抜いた。
――ああ、そうかと。フィアナの胸の中で、すとんと腑に落ちた。
立場とか、年齢とか、住む世界とか。他人の目が、どうとかではない。いろんな枠組みに自分たちを嵌めこんで、勝手に線引きをしていたのは自分だ。
エリアスは最初から、ただのひとりの人間として、フィアナに向き合ってくれていたのに。
「フィアナさん、私は何を、――何もかも捨てれば、ただの私を見てくれますか」
壊れものを扱うような慎重さで、エリアスの白い指がフィアナの頬を撫でる。強請るように顔を覗き込むと、かすかにフィアナを上向かせた。
そうやって、逃がさないように細い腰を抱き寄せながら、エリアスはゆっくりと身をかがめた――。
「………………むぎゅ」
「エリアスさん、ストップ! ストップ、です!」
エリアスの顔の下半分を手で覆って、フィアナは顔を真っ赤にしつつ睨む。もぞもぞと動いて拘束を逃れたエリアスは、ぷはっと息を吐きつつ「なぜですか」と唇を尖らせた。
「今の流れは、完全にキスする流れでしたのに」
「なんでもへったくれもありますか! ていうか、流れってなんですか。まさか全部計算ずくですか!?」
「本気も本気、がちがちに計算ずくですよ。当たり前でしょう、それが恋の駆け引きです」
「知らない常識持ち込まないでください!」
はあ、はあと肩で息をつくフィアナの前で、エリアスはぷいとそっぽを向く。その不満げな横顔は、本当に彼がこの状況をちゃっかり利用して、フィアナの唇を奪おうとしたように錯覚させる。
彼をよく知らない頃であったなら、その嘘にまんまと騙されただろう。
「フィアナさん?」
戸惑う彼の手を握りながら、フィアナは緊張を逃がすため息を吐いた。
事実、エリアスは不思議な男だ。冗談かと思えば本気だったり、本気かと思えばふざけて居たり。純情かと思えば強かだったり、強かかと思えばまっすぐだったり。彼を知ったような気になっていても、どこまでいっても完全には掴み切れない、そんな男。
けれども、今のはわかる。わかってしまう。
茶化して、はぐらかして、笑いに変えて。そうやって彼は、フィアナの何気ない気遣いに傷ついてしまったことを誤魔化そうとしている。そこに気が付くことで、フィアナが罪悪感を抱いてしまわないように。
器用に見えて不器用だ、この人は。
「見てますよ、エリアスさんのこと」
俯いたまま、フィアナは告げた。
「ていうか、目に入らないわけないじゃないですか。これだけ毎日会っていて、飽きずに好きだ好きだと言ってもらって。しかも、お店のピンチまで救ってもらったんですよ。ひとの心にズカズカ入り込んでおいて、今更何をひよっているんですか。意識しないわけないじゃないですか。そうじゃなきゃ、今日だってOKしませんよ!」
「……それって」
「けど!! それとは別に、不安なんです」
ぎゅっとエリアスの手を握り、フィアナはつづけた。
「どんなに一緒にいるのが楽しくても、やっぱり、私はただの町娘なんです。エリアスさんの気持ちを疑うわけじゃないですけど……それでも、好きになっちゃいけない、違う世界の人なんだって。そう、思ってしまうのは止められません。だってエリアスさんは、この国の偉い人だから」
ふたりの手がゆっくりと離れる。一瞬だけ縋るように、エリアスの指の先がぴくりと動く。けれども、すぐにあきらめたように、力なくその手は下がる。
前髪がはらりと耳から零れ落ち、それが引き金になったように、彼は視線を落とした。
だが、うつむくエリアスの視界に、ずいとフィアナがソレを差し出した。
「だから、これが今の私の、精一杯です!」
フィアナの手に乗せられた二つのキーホルダーに、エリアスが目を瞠る。彼はそのうちのひとつを摘み上げると、目の前に掲げた。
「ハリネズミ、ですか?」
「です。色違いで売っていました」
ふたりの間に沈黙が流れる。ややあって、エリアスがふむと頷いた。
「お揃いのお土産。そう、理解して構いませんか?」
その一言に、フィアナはかぁと顔を赤くした。
だが、どんなに照れようがここで首を振ってはダメだ。想いは言葉にしなければ伝わらない。たくさんの想いを届けてくれた彼と同じように、今度は、自分も。
「今日はエリアスさんと私の、初めてのデートです。その記念を形に残したいと思いました」
今日という一日を、一緒に過ごした証に。
まっすぐに見上げるフィアナを、驚いたような顔で見下ろすエリアス。ややあって、彼はふっと息を吐くと、蕾が綻び、ゆっくり花びらが開くような笑みを浮かべた。
「どちらが私のですか?」
「あ、いまエリアスさんが持っている白い子が私のつもりで、こっちの茶色い子がエリアスさんのかなと……」
「そう」
小さく頷くと、エリアスはなぜかそのまま白いハリネズミのキーホルダーを口元へ運ぶ。それから、目をまん丸にするフィアナの前で、慈しむように口付けた。
「貴女は本当に、ひどい天使だ」
真っ赤になってフルフルと震えるフィアナに視線を流し、エリアスはくすりとほほ笑む。
「一瞬で地獄に突き落としたかと思えば、簡単に天国へと昇らせる。――私は随分、やっかいな女神に惚れてしまったようです」
はい、どうぞ、と。ご機嫌な様子で差し出す白ハリネズミのキーホルダーを、フィアナはやけっぱちになって彼から奪う。そして、くるんと彼に背を向けた。
「や、やっぱり、茶色の子もあげません! 両方とも私のにします!」
「えー。そんな意地悪言わないでくださいよ。照れちゃって可愛いですね、私の天使さま?」
「あ、取られた! こら、返しなさい、返せ!」
そうやって、ふたりでぎゃあぎゃあと騒ぎながら。
また、エリアスさんとどこかに行けたらいいなと。
フィアナはこっそり、そんなことを願ったのだった。