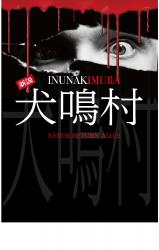どれくらい眺めていただろう。
二階のわたしの部屋の明かり。
その間も薫はただ黙ってアタシの手を優しく包んでいてくれた。
心が揺らいだ時、中からお母さんの声が聞こえた。
「お父さん、もうすぐ未来帰ってくるんよ。サッサと片付けてよ」と。
ーー知ってる…
知っててくれてる
亜紀ネエが薫に電話してくれ、薫がお母さんに話してくれたのだろう。
覚悟を決めてドアノブを回すと
ゆっくりとスローモーションのように
開いたドア。
ドアが開く音を聞いてお母さんが台所から小走りで来た。
顔を上げることもためらい、ただ足元をじっと見ていたアタシ。それでも長年暮らした場所。音だけで見なくても手に取るように分かる。
26にもなってまだ大人になれていない自分が恥ずかしい。東京に行って少しは変わった気になっていただけだった。
二階のわたしの部屋の明かり。
その間も薫はただ黙ってアタシの手を優しく包んでいてくれた。
心が揺らいだ時、中からお母さんの声が聞こえた。
「お父さん、もうすぐ未来帰ってくるんよ。サッサと片付けてよ」と。
ーー知ってる…
知っててくれてる
亜紀ネエが薫に電話してくれ、薫がお母さんに話してくれたのだろう。
覚悟を決めてドアノブを回すと
ゆっくりとスローモーションのように
開いたドア。
ドアが開く音を聞いてお母さんが台所から小走りで来た。
顔を上げることもためらい、ただ足元をじっと見ていたアタシ。それでも長年暮らした場所。音だけで見なくても手に取るように分かる。
26にもなってまだ大人になれていない自分が恥ずかしい。東京に行って少しは変わった気になっていただけだった。