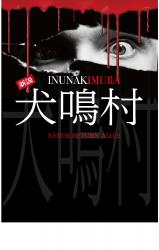「薫、未来どうやったん?」
そう鼻をほじりながら鴨居に手をかけて聞いてきたのは幼馴染で、薫の旦那の托。
「うん…微妙」
「微妙って?」
「クリスマスに期待はしてるとは思うんだけど…准に会えたら会えたで、怖いんじゃないかなあ」
「うん…あのこともあるからな」
「まさか托…アンタ、あのこと未来に話してなんかいないわよね!?」
「まっさか…言うわけねーだろ」
「それに言えねえよ。俺には…」
「何それ?アタシなら言えるっての?」
「いや…そういう意味じゃ…」
「とにかく…未来が帰ってくるといいな」
「そうね」
「でも…准の奴、どこで何してんだかな」
「買い物行ってくる」
四人の思いを弄ぶように、島の千年海岸に春の日の夕陽が傾いていた。
そう鼻をほじりながら鴨居に手をかけて聞いてきたのは幼馴染で、薫の旦那の托。
「うん…微妙」
「微妙って?」
「クリスマスに期待はしてるとは思うんだけど…准に会えたら会えたで、怖いんじゃないかなあ」
「うん…あのこともあるからな」
「まさか托…アンタ、あのこと未来に話してなんかいないわよね!?」
「まっさか…言うわけねーだろ」
「それに言えねえよ。俺には…」
「何それ?アタシなら言えるっての?」
「いや…そういう意味じゃ…」
「とにかく…未来が帰ってくるといいな」
「そうね」
「でも…准の奴、どこで何してんだかな」
「買い物行ってくる」
四人の思いを弄ぶように、島の千年海岸に春の日の夕陽が傾いていた。