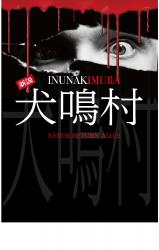その日の昼過ぎ、高吉は一旦家に戻り、嫁の純子にだけは話していた。
「よかか…純子…おらあ行くぞ。」
「准の病気を治してやるにゃ…俺が行くしかなか。」
高吉は純子の両肩を掴み、言い聞かせるように一言一言、噛み砕いた。
「じゃけんど…アンタは…大丈夫なん?」
「あの人喰い渦の近くなんやろ?アンタにもしもんこと…あったら…アタシと准だけでどげんしたらよかとよ!」
高吉はコンクリート造りの台所の裏口の傾きかけたドアの方を向いた。多分…懸命に涙を我慢しようとしていたはず。
「そん時は…」
「何ね?」
「横浜の姉ちゃんとこに准と二人で行け。姉ちゃんには話しとっから…純子…准のこと…頼むぞ。」
普段は強気な漁師の女であるはずの純子もさすがに、このことばかりは生きて帰れる望みがないことは長年、培われた経験と勘で嫌という程、分かっていた。
それでもそれを止められない自分が情けなくて、その場につっぷして泣き出した純子だった。
「よかか…純子…おらあ行くぞ。」
「准の病気を治してやるにゃ…俺が行くしかなか。」
高吉は純子の両肩を掴み、言い聞かせるように一言一言、噛み砕いた。
「じゃけんど…アンタは…大丈夫なん?」
「あの人喰い渦の近くなんやろ?アンタにもしもんこと…あったら…アタシと准だけでどげんしたらよかとよ!」
高吉はコンクリート造りの台所の裏口の傾きかけたドアの方を向いた。多分…懸命に涙を我慢しようとしていたはず。
「そん時は…」
「何ね?」
「横浜の姉ちゃんとこに准と二人で行け。姉ちゃんには話しとっから…純子…准のこと…頼むぞ。」
普段は強気な漁師の女であるはずの純子もさすがに、このことばかりは生きて帰れる望みがないことは長年、培われた経験と勘で嫌という程、分かっていた。
それでもそれを止められない自分が情けなくて、その場につっぷして泣き出した純子だった。