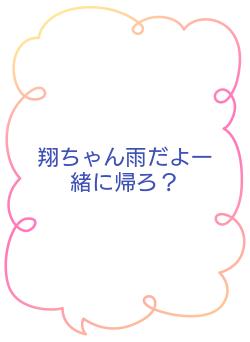身に付けている黒いレザーのチョーカーとバングルはお揃いでとてもオシャレだったけれど、久住君にそんなものが必要なんだろうか。茶髪はやけに大人びて見えて、他人を寄せ付けない感じさえした。
もしかしたら彼だって何か言いたい言葉を隠しているんじゃないかな。
虚しさに押し潰されそうなんじゃないかなって、そんなことを考えていつも勝手に悲しくなった。
結局何もできなくてただ黙り込むだけ。それが繰り返され毎日が過ぎていく。
戸田さんたちの悪意にさらされないよう、いつでもどこでもすぐに渡せるように、あの本はつねにそばに隠し持ってる。
つぶれてしまった角もできる限り修繕した。
あれは彼の大切なもの。
だから、早く返してあげたい。それなのに本はいつまでも冷たくて、時間だけが無慈悲に過ぎていった。
そんな日が続いた末の、最後の放課後のこと。もうチャンスはないと、意を決して席を立ったときだった。
「カラオケいくひとぉー!」
誰かの号令がかかって、やっぱりいつも通り強引に頭数に入れられた。
大勢でどこかへ行っても、私はだいたいいないものとして扱われている。
久しぶりに登校した日は、急な移動教室を知らなくて、教室にひとりだけ取り残された。
授業をさぼったと先生には叱られ、みんなは笑った。
「グループメールでちゃんと連絡まわしたじゃん、見てない人が悪くない?」
誰かがそう言っているのを耳にしたけど、そんなものがあることすら知らないし、誰からも招待されない人がいるってことを、想像すらしない人もいる。
和気あいあいとした空間で、そこから自分一人だけ疎外されること、存在自体を無視されること。
戸田さんたちはそれがいちばんの意地悪だということを、本能的に知っている。
彼女たちに連れ回された先では、カラカラの喉のままただ時間が過ぎるのを待つ。
大丈夫。
解散のときまでいて、お金さえ払えば置いていってくれる。
でも今日はメンバーに久住君がいる。
どうしよう、そんな透明人間みたいな姿を彼にはどうしても知られたくない。
「神崎さん次ね」
「えっ……」
部屋の隅でいつものように時間が経つのを待っていたのに、今日に限って歌うことを強いられた。
大勢でカラオケになんて行ったことがないし、何を歌えば正解かもわからない。声を出せる自信すらないのに……どうしよう。
もう前の人の歌が終わってしまう。
膝のあたりを握りしめていたら、斜め向かいに座っていた久住君に声をかけられた。
「鳴ってる」
「え」
すごく、びっくりした。
「スマホ。さっきから鳴ってる」
見るとスクールバッグのポケットから少しだけ顔を出したスマホが点滅していた。
「理人こっち来いって、ほらマイク!」
「俺いいって」
久住君が立ち上がったから、スマホを手にあわてて部屋を出た。
でも、電話の相手はわけのわからないことを喋りだしてパニックになった私は、一方的に電話を切ってしまった。
部屋に戻って落ち着きを取り戻そうとアイスティーを飲んだら、騒がしく盛り上がっている大ビジョンを背にして久住君が怪訝な顔をした。
「それ俺の」
「あっ、ご、ごめんなさい!」
そうだった、私の飲み物なんてここにはないんだった。
「まだ飲んでないからいいけど……」
「神崎さんはね、うちらに心を開こうとしないんだよね〜」
久住君の問いかけに、誰かがおどけて答えた。私はただ、口を固くぎゅっと結ぶだけ。
もしかしたら彼だって何か言いたい言葉を隠しているんじゃないかな。
虚しさに押し潰されそうなんじゃないかなって、そんなことを考えていつも勝手に悲しくなった。
結局何もできなくてただ黙り込むだけ。それが繰り返され毎日が過ぎていく。
戸田さんたちの悪意にさらされないよう、いつでもどこでもすぐに渡せるように、あの本はつねにそばに隠し持ってる。
つぶれてしまった角もできる限り修繕した。
あれは彼の大切なもの。
だから、早く返してあげたい。それなのに本はいつまでも冷たくて、時間だけが無慈悲に過ぎていった。
そんな日が続いた末の、最後の放課後のこと。もうチャンスはないと、意を決して席を立ったときだった。
「カラオケいくひとぉー!」
誰かの号令がかかって、やっぱりいつも通り強引に頭数に入れられた。
大勢でどこかへ行っても、私はだいたいいないものとして扱われている。
久しぶりに登校した日は、急な移動教室を知らなくて、教室にひとりだけ取り残された。
授業をさぼったと先生には叱られ、みんなは笑った。
「グループメールでちゃんと連絡まわしたじゃん、見てない人が悪くない?」
誰かがそう言っているのを耳にしたけど、そんなものがあることすら知らないし、誰からも招待されない人がいるってことを、想像すらしない人もいる。
和気あいあいとした空間で、そこから自分一人だけ疎外されること、存在自体を無視されること。
戸田さんたちはそれがいちばんの意地悪だということを、本能的に知っている。
彼女たちに連れ回された先では、カラカラの喉のままただ時間が過ぎるのを待つ。
大丈夫。
解散のときまでいて、お金さえ払えば置いていってくれる。
でも今日はメンバーに久住君がいる。
どうしよう、そんな透明人間みたいな姿を彼にはどうしても知られたくない。
「神崎さん次ね」
「えっ……」
部屋の隅でいつものように時間が経つのを待っていたのに、今日に限って歌うことを強いられた。
大勢でカラオケになんて行ったことがないし、何を歌えば正解かもわからない。声を出せる自信すらないのに……どうしよう。
もう前の人の歌が終わってしまう。
膝のあたりを握りしめていたら、斜め向かいに座っていた久住君に声をかけられた。
「鳴ってる」
「え」
すごく、びっくりした。
「スマホ。さっきから鳴ってる」
見るとスクールバッグのポケットから少しだけ顔を出したスマホが点滅していた。
「理人こっち来いって、ほらマイク!」
「俺いいって」
久住君が立ち上がったから、スマホを手にあわてて部屋を出た。
でも、電話の相手はわけのわからないことを喋りだしてパニックになった私は、一方的に電話を切ってしまった。
部屋に戻って落ち着きを取り戻そうとアイスティーを飲んだら、騒がしく盛り上がっている大ビジョンを背にして久住君が怪訝な顔をした。
「それ俺の」
「あっ、ご、ごめんなさい!」
そうだった、私の飲み物なんてここにはないんだった。
「まだ飲んでないからいいけど……」
「神崎さんはね、うちらに心を開こうとしないんだよね〜」
久住君の問いかけに、誰かがおどけて答えた。私はただ、口を固くぎゅっと結ぶだけ。