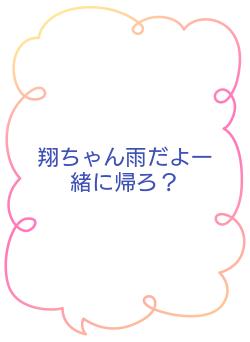お父さんと家に戻ったその日の夜、ノックもなく千絵梨が部屋に入ってきた。
私たちは無言で向き合って、同じタイミングで息を飲んだ。
何か言おうとしたのか、微かに開いた千絵梨の口からは大きな吐息が洩れた。でもそれを制したのは私。
「……謝りなよ」
沈黙を割ったのは、私の方だった。
「何を誰に?」
「久住君に。謝ってよ」
力を込めないと出せない重い声でそう言った。一度流れ出した感情の濁流を塞き止めることがもうできそうにない。
「わかってるよ……あんたに言われなくても!」
千絵梨の怒鳴り声で気持ちは更にたかぶった。
「なんで? なんで彼に伝える必要があったの? ここで私にだけ言えばいいじゃん!」
そしたら静かに死ねたのに。この部屋でひとりきりで首をつったのに。
心はずっと、そう悲鳴をあげていた。
「彼にはなんの非もないのに。彼女だったからってあんたになんの権利があるの?」
あふれだす言葉に歯止めはきかず、底意地の悪い、ヘドロみたいに汚い想いが嘔吐物のように喉からせりあがってきた。
「勝手に妹の罪かぶったりしないでよ! 勝手に傷ついたりしないでよ! お節介なんだよ!」
そう喚いたら、その言葉にまばゆいほどの既視感を覚えて目頭が熱くなった。
いつかどこかで読んだ、小説のワンフレーズだろうか。だけど声にしたとき、大事にしたくて胸のうちで反芻したことをはっきり思い出した。
『そういう時はケンカすればいいんだよ、姉妹なんだから』
優しい声が耳の奥で響いて、理由もなくボロボロに涙があふれた。
この声知ってる、誰だろう。
説明のつかない感情の大波が、理性とその声をさらっていった。
「あんたなんか大嫌い!」
彼が傷ついて行き場をなくして毎日を生きるのに不自由を感じるくらいなら、千絵梨でも私でも知らない誰かでも、世界中のみんなが身代わりになればいいと本気で思った。
千絵梨の肩を強く掴んで、そんな気持ちを理不尽に押し付けた。
「あたしだってあんたなんか大っ嫌いだよ!」
千絵梨も負けずに爪を立てた。
「千絵梨といると自分が惨めで仕方ない。いつだって消えたくなる!」
「あたしはそんなあんたにイラついてどうしようもなかったよ、ずっと!」
離れて暮らせば楽になれると思ったのに違った。たぶんそんなことに意味なんか何もなかった。
「つぼみがそんなんだから、お父さんもお母さんもあたしのことなんか全然眼中になかった! その上理人まで取ろうとするなんてあり得ないんだって!」
互いの苛立ちがウイルスのように増殖して蔓延して、叩いて引っ掻いて髪をひっぱりあって、まるで子供のケンカだった。
涙に濡れた頬にベッタリと髪が貼りつく。
暴言を吐いて暴力をふるいながら思った。
千絵梨はこれまでに何度だってケンカを売ってきたのに、私はいつだってひるんで逃げてきた。
もっと早くケンカすればよかったんだ。
ほんとうはずっと仲直りしたかったから。
私たちは無言で向き合って、同じタイミングで息を飲んだ。
何か言おうとしたのか、微かに開いた千絵梨の口からは大きな吐息が洩れた。でもそれを制したのは私。
「……謝りなよ」
沈黙を割ったのは、私の方だった。
「何を誰に?」
「久住君に。謝ってよ」
力を込めないと出せない重い声でそう言った。一度流れ出した感情の濁流を塞き止めることがもうできそうにない。
「わかってるよ……あんたに言われなくても!」
千絵梨の怒鳴り声で気持ちは更にたかぶった。
「なんで? なんで彼に伝える必要があったの? ここで私にだけ言えばいいじゃん!」
そしたら静かに死ねたのに。この部屋でひとりきりで首をつったのに。
心はずっと、そう悲鳴をあげていた。
「彼にはなんの非もないのに。彼女だったからってあんたになんの権利があるの?」
あふれだす言葉に歯止めはきかず、底意地の悪い、ヘドロみたいに汚い想いが嘔吐物のように喉からせりあがってきた。
「勝手に妹の罪かぶったりしないでよ! 勝手に傷ついたりしないでよ! お節介なんだよ!」
そう喚いたら、その言葉にまばゆいほどの既視感を覚えて目頭が熱くなった。
いつかどこかで読んだ、小説のワンフレーズだろうか。だけど声にしたとき、大事にしたくて胸のうちで反芻したことをはっきり思い出した。
『そういう時はケンカすればいいんだよ、姉妹なんだから』
優しい声が耳の奥で響いて、理由もなくボロボロに涙があふれた。
この声知ってる、誰だろう。
説明のつかない感情の大波が、理性とその声をさらっていった。
「あんたなんか大嫌い!」
彼が傷ついて行き場をなくして毎日を生きるのに不自由を感じるくらいなら、千絵梨でも私でも知らない誰かでも、世界中のみんなが身代わりになればいいと本気で思った。
千絵梨の肩を強く掴んで、そんな気持ちを理不尽に押し付けた。
「あたしだってあんたなんか大っ嫌いだよ!」
千絵梨も負けずに爪を立てた。
「千絵梨といると自分が惨めで仕方ない。いつだって消えたくなる!」
「あたしはそんなあんたにイラついてどうしようもなかったよ、ずっと!」
離れて暮らせば楽になれると思ったのに違った。たぶんそんなことに意味なんか何もなかった。
「つぼみがそんなんだから、お父さんもお母さんもあたしのことなんか全然眼中になかった! その上理人まで取ろうとするなんてあり得ないんだって!」
互いの苛立ちがウイルスのように増殖して蔓延して、叩いて引っ掻いて髪をひっぱりあって、まるで子供のケンカだった。
涙に濡れた頬にベッタリと髪が貼りつく。
暴言を吐いて暴力をふるいながら思った。
千絵梨はこれまでに何度だってケンカを売ってきたのに、私はいつだってひるんで逃げてきた。
もっと早くケンカすればよかったんだ。
ほんとうはずっと仲直りしたかったから。