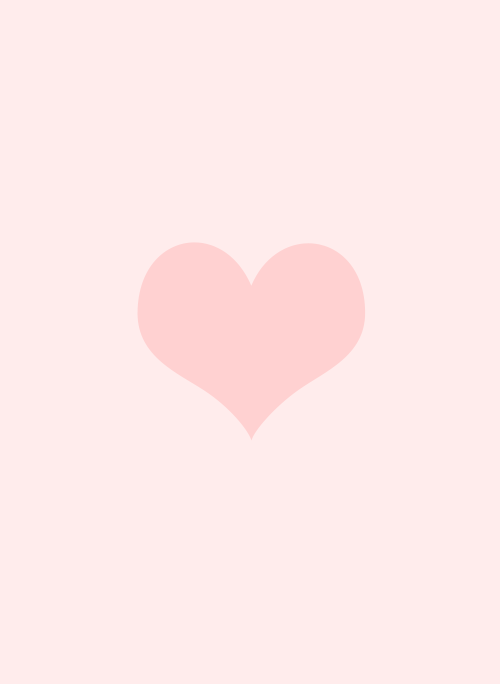「ありがとう。柚葉さんも。疲れてただろうに、俺の世話までさせてしまっていましたね。反省してます」
「ええ? お世話なんてしてませんよ」
「きみはあまやかすのが得意だから、つい俺も調子に乗るよ」
一度も言われたことのない言葉で、目をまるくしてしまった。
実家でもめいっぱいに愛情をもらって、あまくあまく、育ててもらっていたと思う。姉とも年齢も離れていたから、あまやかしてくれる人は多かった。
「……遼雅さんのほうが、さすが、あまやかしのプロだなと感じていますけど」
「そう? 俺はもうすこし、柚葉さんをあまやかしたいです」
「まだ先があるんですか」
「はは、ずっと先まで、あるだろうね」
恐ろしいことを聞いてしまった。もう一度目をまるくしたら、ちらりとこちらを確認した遼雅さんがいっそう楽しそうに笑っていた。
「おどろく顔も、かわいいね。俺がくるまでに攫われなくてよかった」
「それはかなり、おおげさですよ」
どこまで本気か、見極められない。
「遼雅さんは、今日のご飯は何が良いですか?」
「うーん、そうだな。柚葉さんの料理は全部好きだけど……。うん、今日は簡単にできるものが良い」
「簡単にできるもの、ですか?」
「たまに一緒に作ろうか」