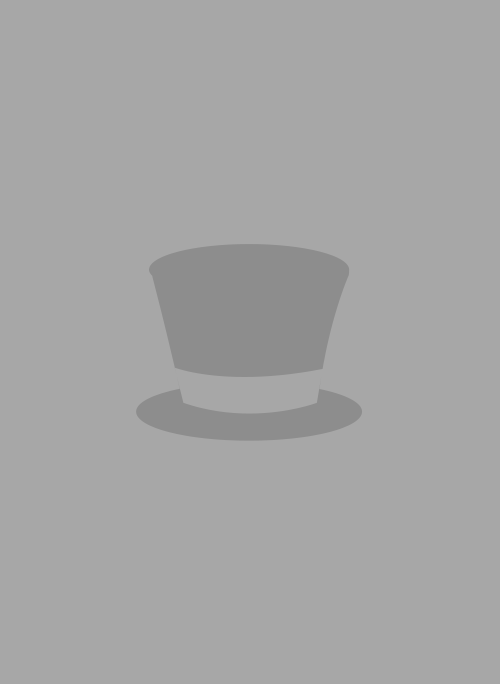「こら!」
大きな声ですぐに教諭がきたのを察知し、全員席に着いた。
「お前ら中学生になってもお化けの話なんって、幼稚すぎるぞ!」
中川厚教諭は四十代前半の数学担当だった。いつも髪を七三にきっちり分けて、鋭い眼光で生徒たちを威圧していた。
朝のホームルームも終わり、敏也の前に本賀正充が現れた。
「ほら、例の……」
正充は手のひらより少し大きい紙袋を差し出した。
「ありがとう」
敏也は周りを伺いながら包みを机の奥にしまった。
「明日、必ず持ってこいよ。忘れたら承知しないぞ」
正光に睨まれて、敏也はか細い声でうなずいた。
一時間目の授業が始まって、すぐに敏也は保健室に行った。
家を出るときは平気なのに、学校に来ると気分が悪くなる。
なぜか保健室の空間だけは落ち着けた。
しかし、今日は頭痛と吐き気を同時に感じ、とても耐えらなかった。気がついたときには早退していた。
大きな声ですぐに教諭がきたのを察知し、全員席に着いた。
「お前ら中学生になってもお化けの話なんって、幼稚すぎるぞ!」
中川厚教諭は四十代前半の数学担当だった。いつも髪を七三にきっちり分けて、鋭い眼光で生徒たちを威圧していた。
朝のホームルームも終わり、敏也の前に本賀正充が現れた。
「ほら、例の……」
正充は手のひらより少し大きい紙袋を差し出した。
「ありがとう」
敏也は周りを伺いながら包みを机の奥にしまった。
「明日、必ず持ってこいよ。忘れたら承知しないぞ」
正光に睨まれて、敏也はか細い声でうなずいた。
一時間目の授業が始まって、すぐに敏也は保健室に行った。
家を出るときは平気なのに、学校に来ると気分が悪くなる。
なぜか保健室の空間だけは落ち着けた。
しかし、今日は頭痛と吐き気を同時に感じ、とても耐えらなかった。気がついたときには早退していた。