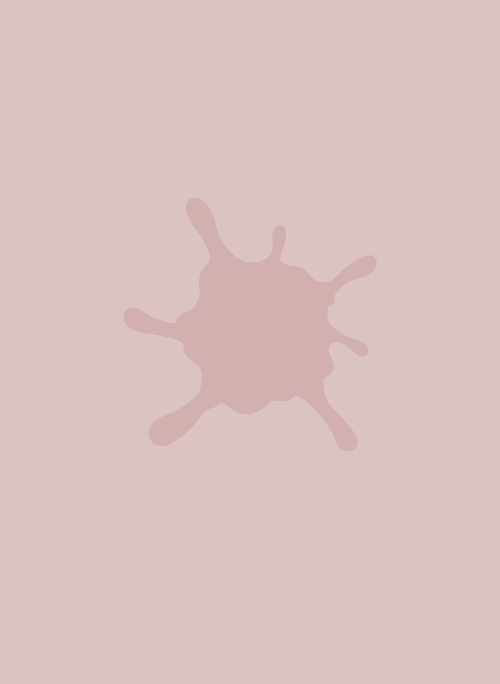少年は幼い頃から周りの子供とは違っていた。
6歳になるまでは、“それ”と会話することはなかった。
だが、小学校に通わせてもらえず、長い間家の中にいる生活を強制され始めてから、1人で喋り始めるようになったのだ。
彼には周りの者には聞こえない声が聞こえていたようだが、オカルトなど信じない親は少年を大層気味悪がった。
「ねぇ、あの子、今日も1人で喋り続けてるのよ。やっぱり外に出してあげたほうがいいのかしら」
「外に出すといっても、あれじゃあ周りの目が……」
「そうよね。夜だって人は少ないけどいつどこで見られるか……」
両親は頭を抱え毎日毎日同じ話をする。
しかし息子のことで精一杯の2人には、少年が隣の部屋でそれを聞いていることに気づけるはずもないだろう。
両親は少年を外に出すことを極端に嫌がっていた。
小学校に行かせなかったのもそのためである。
学校で教育を受けられない代わりに、母親は少年に文字の読み書きや、計算等を家で教え本を買い与え続けた。
だから少年の知識はある程度人並みにあったし、普段の生活で困ることもなかった。
6歳になるまでは、“それ”と会話することはなかった。
だが、小学校に通わせてもらえず、長い間家の中にいる生活を強制され始めてから、1人で喋り始めるようになったのだ。
彼には周りの者には聞こえない声が聞こえていたようだが、オカルトなど信じない親は少年を大層気味悪がった。
「ねぇ、あの子、今日も1人で喋り続けてるのよ。やっぱり外に出してあげたほうがいいのかしら」
「外に出すといっても、あれじゃあ周りの目が……」
「そうよね。夜だって人は少ないけどいつどこで見られるか……」
両親は頭を抱え毎日毎日同じ話をする。
しかし息子のことで精一杯の2人には、少年が隣の部屋でそれを聞いていることに気づけるはずもないだろう。
両親は少年を外に出すことを極端に嫌がっていた。
小学校に行かせなかったのもそのためである。
学校で教育を受けられない代わりに、母親は少年に文字の読み書きや、計算等を家で教え本を買い与え続けた。
だから少年の知識はある程度人並みにあったし、普段の生活で困ることもなかった。