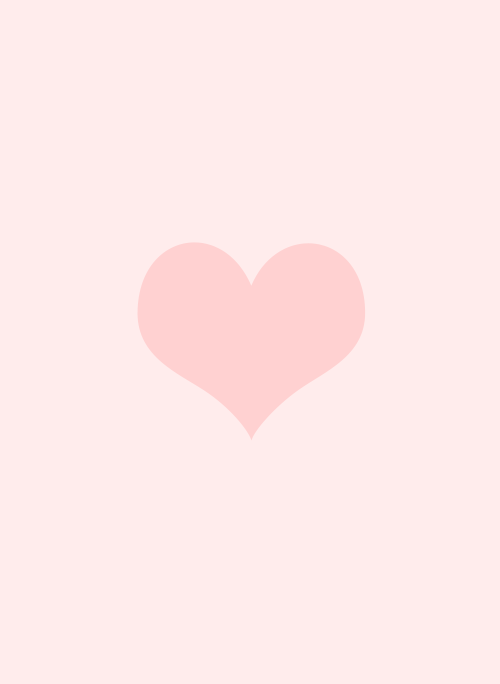そんなことはわかっている。
けど、でも。
「リナは少しでも長く俺といたいとは思わないの?」
わからない。
本当にわからない。
ふるふるとかぶりを振ると、遼はひどく驚いた顔をした。
「リナ!」
遼はまた、私の肩を強く揺する。
「なぁ、どうしたんだよ!? おばあちゃんが亡くなったから、弱気になってるだけだよな!? まさか本当に俺のことが嫌いになったわけじゃないよな!?」
嫌いじゃない。
だけどもう、好きだとも言えない。
その手を振りほどき、足を引いた。
「ごめん。とにかく今日はもう帰らせて」
言うが先か、私は逃げるようにきびすを返した。
遼は私のことが好きで、心配しているからこそ、あんな風に言ったのだろう。
遼の言っていたことは、ある意味では間違っていないと思う。
ただ、私とは考え方が違うだけ。
どちらが正しいとかではないからこそ、互いに相手の言い分を受け入れられないのだ。
私と遼の歯車は、もう完全に噛み合っていなかった。
けど、でも。
「リナは少しでも長く俺といたいとは思わないの?」
わからない。
本当にわからない。
ふるふるとかぶりを振ると、遼はひどく驚いた顔をした。
「リナ!」
遼はまた、私の肩を強く揺する。
「なぁ、どうしたんだよ!? おばあちゃんが亡くなったから、弱気になってるだけだよな!? まさか本当に俺のことが嫌いになったわけじゃないよな!?」
嫌いじゃない。
だけどもう、好きだとも言えない。
その手を振りほどき、足を引いた。
「ごめん。とにかく今日はもう帰らせて」
言うが先か、私は逃げるようにきびすを返した。
遼は私のことが好きで、心配しているからこそ、あんな風に言ったのだろう。
遼の言っていたことは、ある意味では間違っていないと思う。
ただ、私とは考え方が違うだけ。
どちらが正しいとかではないからこそ、互いに相手の言い分を受け入れられないのだ。
私と遼の歯車は、もう完全に噛み合っていなかった。