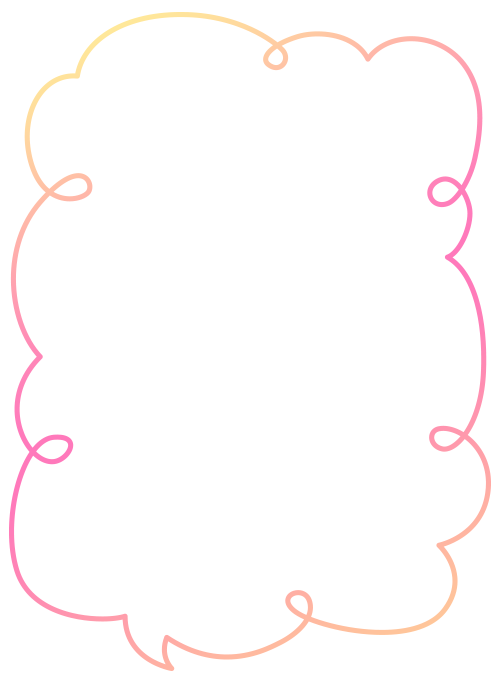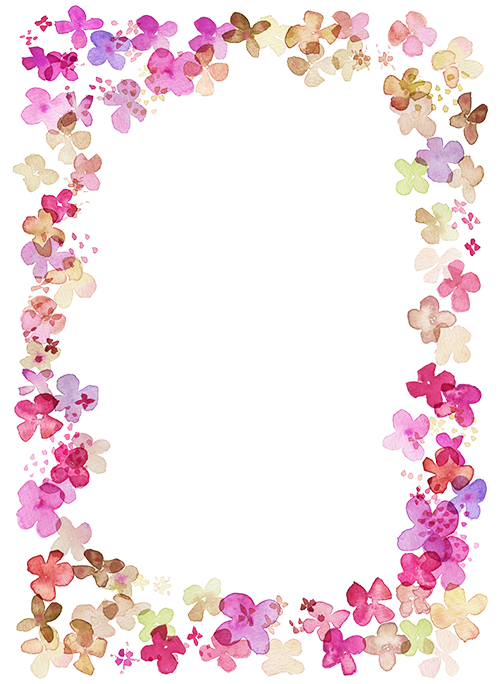「なんか……こうやってしゃべるの久しぶりだね。あたし、ずっと愛奈としゃべりたかったんだ」
真紀に連れられて廊下にやってきた。真紀が無理して明るくわたしに接しようとしていることが空気を通して伝わってくる。
それが妙に鼻についた。
「何?何か用?」
あえて冷たくそう言うと真紀は困ったように苦笑いを浮かべた。
「用って言うかね……あたしさ、前に愛奈のこと怒らせちゃったでしょ?あたし、鈍感なところとか空気読めないっていうか人の気持ちを考えるのが下手なところがあって。だから愛奈がどうして怒ってるのかとか全然分かんなくて。それで――」
「いいよ。もう分かってくれなくて」
「え?」
「だから、もういい。分かってほしいと思ってないから。わたしの気持ちを分かってくれる人ならもういるから」
「愛奈の気持ちを分かってくれる人……?」
「そう。エマちゃん。神宮寺エマちゃん」
「隣のクラスの可愛い女の子だよね。そっか。そんなに仲良くなったんだね。よかったね、愛奈!!」
真紀の言葉はわたしの心の深い部分を小さくえぐった。
どうしていつも真紀はこうなんだろう。こういう言い方をするんだろう。
どうしていつもわたしが求めている言葉をくれないの?
わたしは真紀がわたし以外の子と一緒に遊んだり友達になったりするたびに不安に押しつぶされそうになった。
ずっとずっと不安だった。わたしは真紀のことを親友だと思っていたけど、真紀がわたしのことをどう思っているのか分からなかったから。
真紀は誰とでも仲良くできるけど、わたしはそうじゃない。
真紀はわたしの特別だけど、わたしは真紀の特別なんかじゃない。
真紀に連れられて廊下にやってきた。真紀が無理して明るくわたしに接しようとしていることが空気を通して伝わってくる。
それが妙に鼻についた。
「何?何か用?」
あえて冷たくそう言うと真紀は困ったように苦笑いを浮かべた。
「用って言うかね……あたしさ、前に愛奈のこと怒らせちゃったでしょ?あたし、鈍感なところとか空気読めないっていうか人の気持ちを考えるのが下手なところがあって。だから愛奈がどうして怒ってるのかとか全然分かんなくて。それで――」
「いいよ。もう分かってくれなくて」
「え?」
「だから、もういい。分かってほしいと思ってないから。わたしの気持ちを分かってくれる人ならもういるから」
「愛奈の気持ちを分かってくれる人……?」
「そう。エマちゃん。神宮寺エマちゃん」
「隣のクラスの可愛い女の子だよね。そっか。そんなに仲良くなったんだね。よかったね、愛奈!!」
真紀の言葉はわたしの心の深い部分を小さくえぐった。
どうしていつも真紀はこうなんだろう。こういう言い方をするんだろう。
どうしていつもわたしが求めている言葉をくれないの?
わたしは真紀がわたし以外の子と一緒に遊んだり友達になったりするたびに不安に押しつぶされそうになった。
ずっとずっと不安だった。わたしは真紀のことを親友だと思っていたけど、真紀がわたしのことをどう思っているのか分からなかったから。
真紀は誰とでも仲良くできるけど、わたしはそうじゃない。
真紀はわたしの特別だけど、わたしは真紀の特別なんかじゃない。