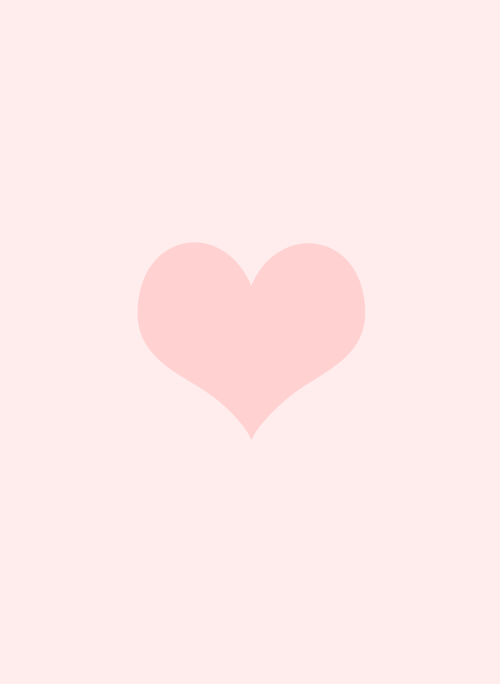泰士のものになるなんて、背伸びしたことを言ったものの、覚悟なんて決まるわけがなかった。
さすがに、今の私に何かをすることはないと思うけれど、その何かの扉を少し開けてしまったかもしれないと、落ち着かない。
『嘘つけ。泣き虫赤ちゃんのくせに。』
と言いながら、背中を子供を寝かせるようにトントンと叩く。
『赤ちゃんって、そんな言い方しなくても良いじゃん。』
『膝に乗って泣いてる子は赤ちゃんじゃないの?』
泰志を強い目つきでにらむ。
『涙目で睨まれても怖くないよ。』
『もういい。』
泰志の胸に再び顔をうずめて、温もりを感じる。
そんなやり取りをしているうちに、さっきまでのネガティブな気持ちは無くなって、まぶたが重くなった。
『おやすみ。』
と耳元でささやく声が聞こえた気がした。