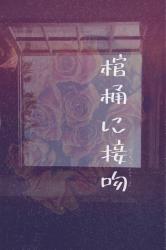どのくらい、時間が経ったのかぼやける目を擦った。
前に、誰か立っている。
まだ、ぼやけている両目を再度擦って、目を凝らした。
「...嘘」
思わず、声が震えた。
「なんで居るの?」
「君に会いたかった」
彼は、笑顔で言った。
何かが喉の奥に突っかかって、一言でも言葉を発すれば全て溢れてきそうだった。だから、私は、なにもしゃべれなかった。
「今日はね、君にこれを渡しに来たんだ」
夏の日差しに照らされて、それはキラリと輝いた。
「僕と、結婚してくれませんか」
「...っ...はい」
きっと、人生に一度きりのプロポーズだというのに、もう、他に言葉が出てこなくて、私の辞書からはい以外の言葉が消されていて、でも、涙っていうのは言葉が無くったって出てきてしまうもの。
本当に、よく分からない。
ただ、あなたにそんなことを言われたのが嬉しかったんだと、幸せだったんだとそう思うのだ。