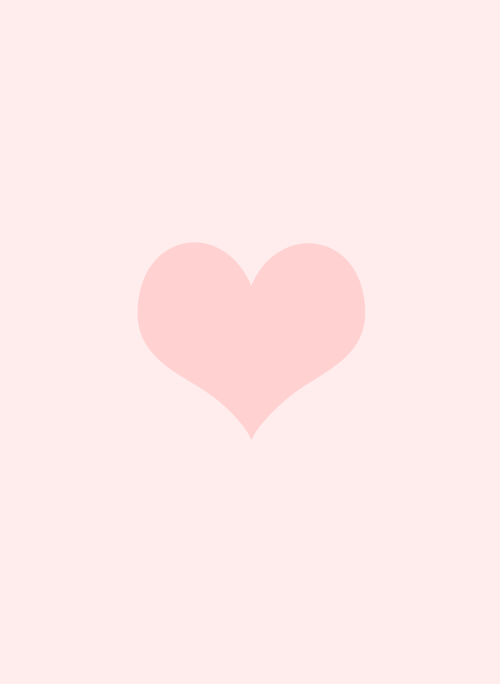久遠が結婚すれば子宝が授かり、神々の世界に大きな恵みをもたらす。
希少な白龍は、他の種族が持つ事の出来ない強大な『守りの力』を持つ。
外見も内面も大変魅力的で、他者と和を結べる忍耐強さを備えている者が、白龍からは多く輩出される。
あらゆる意味で神々は、白龍を絶滅させるわけにはいかなかった。
白龍の力無しでは到底、便利で楽な生き方を保てないというのも理由の一つ。
要するに多くの神々は、今以下の生き方を受け入れる事が出来ない。
自分達は我慢ができないので、我慢できる白龍に依存する。
だから白龍は、早急に結婚を迫られる。
成人する前から何度もうるさくしつこく結婚しろと言われ続けた久遠は、いい加減うんざりしていた。
父と母のように愛を伴った結婚生活は憧れであり、良いご縁があれば結婚はしたいのだが。
結婚するのもしないのも、正直なところ久遠の自由である。
赤の他人と生活を共にするのだ。
それに今まで一度も、久遠は白龍やそれ以外の女性に恋心を抱いた事が無い。
急いで相手を決めたところで、ろくな事にならないのでは無いか。
相手が『白龍』限定と定められていることが、事態を余計に困難にした。
その事以外にも、ずっと違和感を感じてモヤモヤしている事が一つある。
10歳になるくらいまでは両親に大切に育てられ、家族揃って生きてきたのに。
「あなたのご両親は事故に遇い、行方知れずになってしまいました」
と神々が無理やり口を揃えて言い切ったあの態度は、明らかに不自然だった。
父と母は本当に、事故に遇って行方知れずになったのだろうか。
久遠は18歳になるまで、両親不在の本当の理由について、何も知らされずにただ生きて来たのである。
いきなり幸せから引き離され、巨大な城の中で召使にかしずかれ、教育という名のもとに縛られるのが運命?
当時まだ子供だった久遠の不信感を煽りこそすれ、納得させてはくれなかった。
両親が謎の失踪を遂げてからというもの、親族を名乗る神々にチヤホヤされ続けてはきた。
だが久遠は自分を取り巻く環境の「何かがおかしい」と、薄々気がついていた。
誰も自分に真実を教えてくれようとしなかった事だけは、何となくわかる。
具体的に何がどうおかしいのか問われると、明確な答えは出せないのだが。
こじれてもつれて絡み合い、一言ではとても言い表せない。
愛するが故に厳しくあろうとする態度が、久遠の両親にはあったのに。
自分が得をするためだけに、神々は久遠をひどく甘やかそうとするのを感じる。
「アタシも『龍の目』探すの、手伝ってあげるよ」
白龍・清名は白髪を揺らしながら、にぱっと笑った。
清名はからっと明るくて憎めない所があり、真面目で融通のきかない久遠とは対照的な性格である。
だからこそ、どこかしら馬が合うらしく、仲はとても良かった。
清名が女性だったら良かったのに、と思った事もある。
「…………ありがとう。清名」
ここ天が原には、ほんのわずかだが死んだ白龍の『目』が、数ある石の中に紛れ込んでいる事がある。
「もし『龍の目』見つけたらさ、アタシと結婚してよ久遠ちゃん」
「嫌だ。何故そうなる。なら一人で探」
「ううん! ウソウソ! 一緒に探してあ・げ・る!」
清名は男性なので、一緒に暮らせたとしても子供が授からない。
同じ男性で本当に良かったと、今となっては思う。
ずっと仲良くしてもらいたい相手とは、些細なこじれ方をしたく無いものだ。
久遠と清名は、注意深く草に紛れた石の中に落ちている『龍の目』を探し続けた。
久遠は自分が求めている何らかの答えを、『龍の目』を覗き込む事で得られるような気がしている。
人間の世界が見えるといわれる『龍の目』は、久遠にとって希望の光そのものだ。
白龍は太古の昔、今よりもさらに栄華を極めていたらしい。
死んでいった過去の白龍の『目』が化石となり、現在も力を持ち続けている。
文字通り、遠い過去には本物の『龍の目』だったはずのモノなのだから。
きっと真実を示してくれる。
今の神々はその貴重さに気づかず、昔の白龍の『目』などよりも、今生きている白龍にしか、興味を示さなくなっている。
だから普通の石の中に、遠い過去の白龍達の『目』が無造作に埋もれていく。
「あーあ。久遠ちゃんと結婚出来るなら、楽しそうなのにな!」
「……」
久遠もそう思う事があるけれど。
残念なことに、女性以外と結婚する気が久遠には無かった。
清名が、いきなり地面を指さして大きな声を上げた。
「ほら久遠ちゃん! 見てごらん! ここに一つ落ちてるじゃない! 『龍の目』」
数ある石の中、透き通った紫色の小さな丸い石が鈍い光を放っている。
「……本当だ。龍の目に間違いない」
久遠は清名に笑顔を見せた。
「見つけてくれてありがとう、清名」
滅多に見せない久遠の柔らかな表情に胸を射抜かれ、清名はほんのりと頬を赤くして、デレデレと笑った。
「ううん…………いいのよう。どういたしましてぇ」
久遠は石を拾い上げ、二体はじっと注意深く覗き込んだ。
途端、久遠は驚いて息が止まりそうになった。
『龍の目』が全て、見せてくれた。
ずっと見たかった真実を。
久遠の両親がどうして、姿を消してしまったのか。
多くの神々が白龍を、久遠自身を、どんな風に利用しようとしていたのか。
細切れの情報が記号のように、パッパッと花火のように映し出され、鮮明に色づいて、久遠の脳内でワッと広がった。
戸惑ったが、久遠は決して目を逸らさなかった。
大体は予想していた。
この残酷さを見つめるためには、どれほどの覚悟が必要だったのかくらい。
優しかった父と母は、傲慢で自己中心的な神々の手によって消されたのである。
このショックは大きい。
いつも自分を守り、大切にしてくれた父と母。
なのに彼らに相応しくない、あんまりな、ひどい最期ではないか。
自分は何も知らないまま、のうのうと、父と母を守れないまま、生きて来た。
久遠の目に涙が溢れてくる。
これが真実。
なんと酷い。
さらに石を覗き込むと、神社に参拝する人々の姿が見えてくる。
龍の目とは、自分が本当に見たいものを、見せてくれる役割を果たす。
久遠が見たかったのは、この人達でもあったのだろうか。
清名も石を覗き込んだ。
「ここ『岩時神社』だね」
「…………え」
最強神・深名の命を受けて濁名という白龍が守ることになった、いわくつきの神社。
濁名は白龍だが、性格は黒龍と何ら変わらない。
元は清らかだったはずが、自身の弱さに負けて、とうとう黒龍と同じ邪悪さの中に心をすっぽり落としてしまった。
自分のために何かを奪い尽くす事に、喜びを見出す女になり果てたのである。
久遠が覗いた紫色の石は、岩時神社の拝殿に設置された鈴の上に描かれている、ドラゴンの瞳と繋がっていた。
のちに龍宮城に置かれることになるこの『龍の目』は、別なものも映し出した。
濁名が本殿の中で、人間をムシャムシャと夢中で食べている姿だ。
驚いたことに食われている人間の体からは、血が一滴も出ていない。
『まずい』
「ひぃっ!!」
町長をはじめとする町の人々は、震えあがって白龍・濁名を見つめている。
「濁名! あいつ…………また! 白龍の面汚しね」
「また?」
清名の言葉で、久遠は我に返った。
「人間を食べている?」
「うん。正確には、人間の『魂』を食べているの」
「────え」
「ほら見て。近くに霊水が置かれているでしょ? 濁名は何度も禁を犯している。深名様は一体、どうして濁名を放ったらかしにしているのかしら」
希少な白龍は、他の種族が持つ事の出来ない強大な『守りの力』を持つ。
外見も内面も大変魅力的で、他者と和を結べる忍耐強さを備えている者が、白龍からは多く輩出される。
あらゆる意味で神々は、白龍を絶滅させるわけにはいかなかった。
白龍の力無しでは到底、便利で楽な生き方を保てないというのも理由の一つ。
要するに多くの神々は、今以下の生き方を受け入れる事が出来ない。
自分達は我慢ができないので、我慢できる白龍に依存する。
だから白龍は、早急に結婚を迫られる。
成人する前から何度もうるさくしつこく結婚しろと言われ続けた久遠は、いい加減うんざりしていた。
父と母のように愛を伴った結婚生活は憧れであり、良いご縁があれば結婚はしたいのだが。
結婚するのもしないのも、正直なところ久遠の自由である。
赤の他人と生活を共にするのだ。
それに今まで一度も、久遠は白龍やそれ以外の女性に恋心を抱いた事が無い。
急いで相手を決めたところで、ろくな事にならないのでは無いか。
相手が『白龍』限定と定められていることが、事態を余計に困難にした。
その事以外にも、ずっと違和感を感じてモヤモヤしている事が一つある。
10歳になるくらいまでは両親に大切に育てられ、家族揃って生きてきたのに。
「あなたのご両親は事故に遇い、行方知れずになってしまいました」
と神々が無理やり口を揃えて言い切ったあの態度は、明らかに不自然だった。
父と母は本当に、事故に遇って行方知れずになったのだろうか。
久遠は18歳になるまで、両親不在の本当の理由について、何も知らされずにただ生きて来たのである。
いきなり幸せから引き離され、巨大な城の中で召使にかしずかれ、教育という名のもとに縛られるのが運命?
当時まだ子供だった久遠の不信感を煽りこそすれ、納得させてはくれなかった。
両親が謎の失踪を遂げてからというもの、親族を名乗る神々にチヤホヤされ続けてはきた。
だが久遠は自分を取り巻く環境の「何かがおかしい」と、薄々気がついていた。
誰も自分に真実を教えてくれようとしなかった事だけは、何となくわかる。
具体的に何がどうおかしいのか問われると、明確な答えは出せないのだが。
こじれてもつれて絡み合い、一言ではとても言い表せない。
愛するが故に厳しくあろうとする態度が、久遠の両親にはあったのに。
自分が得をするためだけに、神々は久遠をひどく甘やかそうとするのを感じる。
「アタシも『龍の目』探すの、手伝ってあげるよ」
白龍・清名は白髪を揺らしながら、にぱっと笑った。
清名はからっと明るくて憎めない所があり、真面目で融通のきかない久遠とは対照的な性格である。
だからこそ、どこかしら馬が合うらしく、仲はとても良かった。
清名が女性だったら良かったのに、と思った事もある。
「…………ありがとう。清名」
ここ天が原には、ほんのわずかだが死んだ白龍の『目』が、数ある石の中に紛れ込んでいる事がある。
「もし『龍の目』見つけたらさ、アタシと結婚してよ久遠ちゃん」
「嫌だ。何故そうなる。なら一人で探」
「ううん! ウソウソ! 一緒に探してあ・げ・る!」
清名は男性なので、一緒に暮らせたとしても子供が授からない。
同じ男性で本当に良かったと、今となっては思う。
ずっと仲良くしてもらいたい相手とは、些細なこじれ方をしたく無いものだ。
久遠と清名は、注意深く草に紛れた石の中に落ちている『龍の目』を探し続けた。
久遠は自分が求めている何らかの答えを、『龍の目』を覗き込む事で得られるような気がしている。
人間の世界が見えるといわれる『龍の目』は、久遠にとって希望の光そのものだ。
白龍は太古の昔、今よりもさらに栄華を極めていたらしい。
死んでいった過去の白龍の『目』が化石となり、現在も力を持ち続けている。
文字通り、遠い過去には本物の『龍の目』だったはずのモノなのだから。
きっと真実を示してくれる。
今の神々はその貴重さに気づかず、昔の白龍の『目』などよりも、今生きている白龍にしか、興味を示さなくなっている。
だから普通の石の中に、遠い過去の白龍達の『目』が無造作に埋もれていく。
「あーあ。久遠ちゃんと結婚出来るなら、楽しそうなのにな!」
「……」
久遠もそう思う事があるけれど。
残念なことに、女性以外と結婚する気が久遠には無かった。
清名が、いきなり地面を指さして大きな声を上げた。
「ほら久遠ちゃん! 見てごらん! ここに一つ落ちてるじゃない! 『龍の目』」
数ある石の中、透き通った紫色の小さな丸い石が鈍い光を放っている。
「……本当だ。龍の目に間違いない」
久遠は清名に笑顔を見せた。
「見つけてくれてありがとう、清名」
滅多に見せない久遠の柔らかな表情に胸を射抜かれ、清名はほんのりと頬を赤くして、デレデレと笑った。
「ううん…………いいのよう。どういたしましてぇ」
久遠は石を拾い上げ、二体はじっと注意深く覗き込んだ。
途端、久遠は驚いて息が止まりそうになった。
『龍の目』が全て、見せてくれた。
ずっと見たかった真実を。
久遠の両親がどうして、姿を消してしまったのか。
多くの神々が白龍を、久遠自身を、どんな風に利用しようとしていたのか。
細切れの情報が記号のように、パッパッと花火のように映し出され、鮮明に色づいて、久遠の脳内でワッと広がった。
戸惑ったが、久遠は決して目を逸らさなかった。
大体は予想していた。
この残酷さを見つめるためには、どれほどの覚悟が必要だったのかくらい。
優しかった父と母は、傲慢で自己中心的な神々の手によって消されたのである。
このショックは大きい。
いつも自分を守り、大切にしてくれた父と母。
なのに彼らに相応しくない、あんまりな、ひどい最期ではないか。
自分は何も知らないまま、のうのうと、父と母を守れないまま、生きて来た。
久遠の目に涙が溢れてくる。
これが真実。
なんと酷い。
さらに石を覗き込むと、神社に参拝する人々の姿が見えてくる。
龍の目とは、自分が本当に見たいものを、見せてくれる役割を果たす。
久遠が見たかったのは、この人達でもあったのだろうか。
清名も石を覗き込んだ。
「ここ『岩時神社』だね」
「…………え」
最強神・深名の命を受けて濁名という白龍が守ることになった、いわくつきの神社。
濁名は白龍だが、性格は黒龍と何ら変わらない。
元は清らかだったはずが、自身の弱さに負けて、とうとう黒龍と同じ邪悪さの中に心をすっぽり落としてしまった。
自分のために何かを奪い尽くす事に、喜びを見出す女になり果てたのである。
久遠が覗いた紫色の石は、岩時神社の拝殿に設置された鈴の上に描かれている、ドラゴンの瞳と繋がっていた。
のちに龍宮城に置かれることになるこの『龍の目』は、別なものも映し出した。
濁名が本殿の中で、人間をムシャムシャと夢中で食べている姿だ。
驚いたことに食われている人間の体からは、血が一滴も出ていない。
『まずい』
「ひぃっ!!」
町長をはじめとする町の人々は、震えあがって白龍・濁名を見つめている。
「濁名! あいつ…………また! 白龍の面汚しね」
「また?」
清名の言葉で、久遠は我に返った。
「人間を食べている?」
「うん。正確には、人間の『魂』を食べているの」
「────え」
「ほら見て。近くに霊水が置かれているでしょ? 濁名は何度も禁を犯している。深名様は一体、どうして濁名を放ったらかしにしているのかしら」