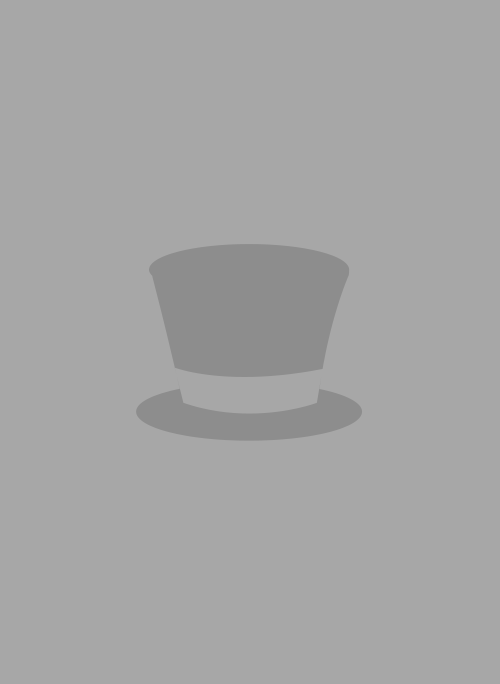「――――水樹、水樹蒼佳ー、いるか」
ーーーーあくる日の休み時間。
廊下の方の窓から鮫島先生に呼ばれた私は、友達との会話を止めて立ち上がる。
そばへ寄ると、先生は申し訳なさそうに片手をたてて言ってきた。
「放課後ちょっと職員室に寄ってくれるか? 昨日に続いて悪いんだが、また手伝ってほしいことがあってな…。すぐ終わることだから、頼まれてくれないか」
「あ、わかりました」
「すまん! 助かるよ!」
鮫島先生って、いつも忙しそうだな。
鮫島先生だけじゃないか。最近先生たちはみんな慌ただしい。
「どうしたの」
席に戻ると、私の机に肘をついて待っていた友人、南沢雅ちゃんが聞いてきた。
「放課後手伝ってほしいことがあるんだって。先生たち、みんなバタバタしてるね」
「テスト明日からだしね。生徒に点とらせるために必死なんでしょ」
無駄な足掻きだろうけど、と雅ちゃんはスマホを見ながら興味もなさそうに言った。
「雑用のあと、今日も残るの?」
「うん。テスト明日だし、勉強しなきゃ」
「蒼佳ならノー勉でも余裕だと思うけど。ほんと真面目なとこは抜けきらないんだね」
私は苦笑した。
雅ちゃんにそんなことを言われると恐縮しちゃう。
こんなこと言ってるけど、私よりも彼女のほうがずっと頭がいい。なにしろ中間テストや小テストに至るまで満点から欠けたことが一度もない人だ。
ここのテストが簡単であることは百も承知だ。だけど5~7問くらいはややこしい問題はある。出される問題も一応は高校生対象の問題だし、私も取れて90が最高だ。
それを国語・数学・化学・地理歴史うんぬんかんぬん…凡ミスもなしにオール100はさすがに私も無理だ。
「この学校のテストで満点でもなんの自慢にもならない」なんてこの人は執着なく言うけど、聞けば彼女の出身中学は、県内でも有名な偏差値トップに近い中学校なのだった。
その中学の首席だったという話だからさらに驚く。
そんな学校からなぜ底辺ともいえるこんな高校へ入学したのかと聞けば、「バカに囲まれて生活してみたかった」と彼女は平然と答えた。
詳しいことは私はまだ知らない。時々ふと思い出すようにその頃のことを毒づくことがあるけど、人間関係がかなり地獄だったみたいだというのは察している。
エリート揃いの学校となると、とりわけ競争心が強い人間が集まるようで、特に首席だった雅ちゃんには周りからの妬みが凄まじかったみたい。
私の中学も一応は進学校と言われてはいたけど、せいぜい中堅レベル。私は学年1位なんて取ったことがないし、むしろあの中では劣等生に近かった。だから雅ちゃんの苦悩も、私には想像することでしかわかってあげられない。
それでもお互いにどこか通じるものがあって、前後の席ということもあり私たちは入学して間もないうちから頻繁に話すようになったのだ。
「蒼佳って、もしかして勉強好きなんじゃないの?」
雅ちゃんはスマホから目を離し、足を組みなおして私にいった。
「でなきゃ毎日放課後残って勉強するなんて、モチベーション続かないよね」
「そうだね。今は勉強するの、結構楽しいかも」
「楽しい、ねえ。変わってるよね、あんた…」
そういう雅ちゃんは、もう勉強にはつくづく飽きてしまったらしい。
冒頭で私がグレ始めた頃の行動を少し話したけれど、起因となったのはこの子だ。
雅ちゃんだって私と同じく勉強に明け暮れた中学時代を送ったはずなのに、青春の遊び方というものをこれでもかというくらい知っている。
最初にカフェで一緒にお茶をしたとき、私は軽い罪悪感さえ覚えた。放課後に高校生の身分でこんなお洒落な場所で時間を使っていいのか?貴族にでもなったつもりか? 挙動不審にピーチティーしか頼めなかった私に対して、雅ちゃんはクリームがいっぱいのったコーヒーとタルトまで頼んで満喫していた。贅沢、そして大胆不敵!
……え? そんなの普通のことって?
はい、雅ちゃんにもそっくり同じことを言われました。
だってしょうがないじゃないか! 放課後の寄り道なんて今までしたことなかったんだもん!
超×50真面目だった私なんて、校則とか規則とか、そういうレールの上をはみ出すことなくまっすぐ歩いてきたような人間だ。逆に雅ちゃんはそんなに頭がいいのにいつ遊ぶ暇があったの? 全く不思議だ。
まあ、そんな彼女が遊びをリードしてくれたおかげで、私もめでたく女子高生として新しい生活を謳歌できるようになったわけだけど。
それにしても、頭もよくてクールで美人で、見た目はお姉さんなのに、カラオケで歌っていた曲は幼稚園の頃公共で放送していた少女アニメのオープニングテーマだったことは、未だに衝撃だ。
私のこと変わってるなんて言うけど、雅ちゃんのほうがよっぽど変わってみえるんだよなぁ。
大人びた仕草で茶髪の髪を後ろにはらう雅ちゃんをみて、私はウーンと首をひねらせた。
「そういえば、ちょっと気になってることがあんだけど」
ふと、急に真面目な顔になって雅ちゃんは私を見る。
こんなトーンで話してくる彼女は珍しい。
もしかして、何か悩みの相談?
「どうしたの?」
真剣な話だと思って、私は気合を入れるために水筒のお茶をひとくち口に含ませた。
「来栖となんかあった?」
「グフッ!!」
ぎりぎり吹き出さなかったけど、むせた。