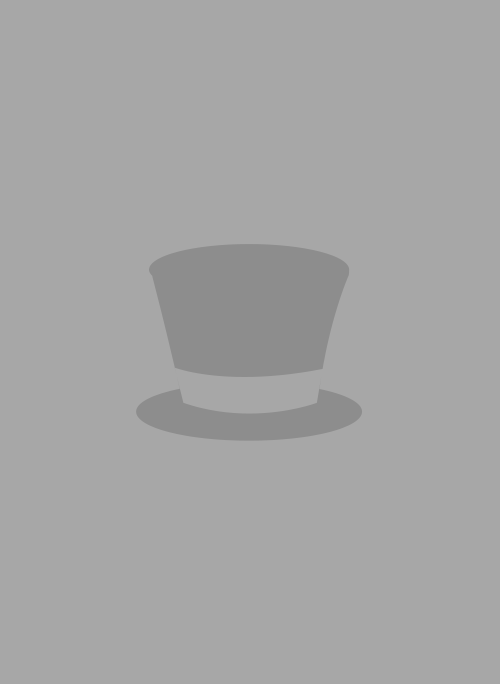眉間にピシッとシワができるのが見えた。
得体の知れないものでも見たように綺麗な顔が歪んでいく。
「お前……」
「あのね、来栖くん。私と話すことが、どうしても耐えられないくらい嫌だ!って来栖くんがいうなら、私も諦める。でも、もしも、少しでも私と話してもいいって思ってくれるなら、これからもこんなふうに話したい。友達みたいに。…だめ?」
何かを言おうと口を開きかける来栖くんに、私は慌てて重ねるようにして付け加えた。
「ヤクザであるとか、仕事としてやってることとか、理解できたわけじゃないんだ。けど、せっかくこんなふうに話せるようになったことがゼロに戻っちゃうのは、どうしても嫌だっていうか…勿体ないって思うの」
昨日の夜からずっと考えていた、一番もやもやしていたこと。
この壁。この境界線。何が邪魔してるんだろう? どうしてこんなに悩まなくちゃいけないんだろう? 「来栖くんともっと話したい」。それだけのことで。
「私の考え方って自分勝手でわがままなんだなって自覚はある。でも、もうこれっきり話さないっていうのは、やっぱり寂しい。同い年で、同じ学校で、同じクラスで、それだけの共通点で友達になれる人はたくさんいるよね? なのに私たちだけなれないって、そんなのおかしいよ。共通点だってもう一つ見つけられたのに」
「もう一つ…?」
私の言ったことが思い当たらないのか、来栖くんは怪訝そうに眉を寄せた。
私は少し得意になって笑う。
「この公園のこと! 私、この場所がすごく好きなんだけど、来栖くんも気に入ってくれたんだよね? …あのね、私がしたかった共有って、こういうことなんだ」
私は公園全体をぐるりと見渡してから、もう一度来栖くんの方に向き直る。
来栖くんは固まったまま、私を凝視して動かない。いつも澄まし顔だった彼が、驚きに満ちた表情で固まっているのは、なんだか可笑しくもあった。
「来栖くんがこの公園を気に入ってくれたこと、すごく嬉しかったんだ。だって私も好きだから。好きな場所が一緒で、しかもこうやって一緒に過ごせてることは、もっと嬉しい。やっと共有できた!って感じ。だからいま楽しい」
昨日からずっともやもやしっぱなしだったけど、やっと楽しいと思えるようになった。
ぎこちないままで終わらなくてよかったって、ほっとしてる。
「来栖くんは? 今、楽しい?」
横を見上げて、私を見下ろす僅かな戸惑いの滲んだ視線を受けとめた。
明確に「楽しい」と思わなくてもいい。なんとなくでも、気まぐれにでも、ここで過ごしている今が、来栖くんにとって「悪くない」ものであってほしい。
私の願いと期待を受けながらも、来栖くんは口を引き締めたまま開こうとしない。
無視しているわけじゃなく、考えている様子がなんとなく感じ取れて、私は黙って待った。
「……人の気も知らねえで…」
ぽつりと出てきたのは、不機嫌さが滲み出た不満。
「せっかくこっちから突き放してやろうってのに」
「どうして突き放すの?」
「お前みたいな能天気な奴、見たことねぇからだよ」
………あれ、もしかして、来栖くんが私に冷たくなったのって、私を気遣ってくれてたから?
来栖くんからしたら私の言ってること、「ヤクザと友達になりたい」とイコールにとらえてるみたいだったし…。
来栖くんの態度の意図が、今になってようやくわかって、ぽかんとしてしまう。
私の呆けた様子に、来栖くんはさらに苛立ったように舌打ちした。
「なのに、なんなんだよお前…。そこまで懐かれることしてねえぞ」
「な、懐くって!」
もうちょっと言い方があるんじゃないの!?
なんか尻尾をふった犬みたいな感じで恥ずかしくなってくる。
「だっ、だって……っ、気になっちゃうんだから仕方ないじゃん!! 自分でもよくわかんないけど、来栖くんのこと気になるの!!」
「……………」
あ、あれ。なんかいま、私変なこと言っちゃったような。
すごーーく、誤解を招くような言葉を軽々しく言っちゃったような………!
「あ…いや、違くて…! ううん、違わないけど今のは言葉の綾ってやつで……その、だから…うーーん……」
否定しなきゃいけないのに、ばっさり否定するのがなんだか躊躇われて、どう弁解しようかと頭を抱えた。
呻きながら悶えていると、ふっ、と小さな吐息が頭上から聞こえた。
それが笑いのために漏れた息だったことに、顔を上げて初めて気づいた。
来栖くんが笑ってる。
冷たくない。怖くもない。自然と頰が緩んでできた笑顔。
来栖くんの笑い方は晴れやかで豪快なものではなくて、笑うことに慣れていないような、少し苦笑に近い。
でも今目の前で笑ってくれている来栖くんの表情は、決して作り物ではないと直感できた。
「やっぱ、変な女だな、お前」
「………」
また、変って言われた。
反論したかったのに、来栖くんが笑っていることに気を取られて、咄嗟に何もいえなかった。
それでも反抗心に任せて声を絞り出す。
「私からしたら、来栖くんの方が、変わってるよ…」
「そうだろうな」
「…でも、お互いを変わってるって思っても……好きなものは同じことって、あるんだね」
ひとりごとのように、私は呟いた。
また、風が吹く。
木々が揺れ、ざわざわと波のような音をたてて青葉が荒ぶる。
風で髪がゆれた。目の前に黒いカーテンがかかったみたいに、頰に髪が垂れてくる。
自分でそれを払おうとするより先に、来栖くんの手が髪に触れる。
びっくりして固まる私に、来栖くんは繊細な手つきで髪を横に払った。
明るくなった視界の先で、絹糸のような髪が風になびくのを見た。
鼻先に来栖くんの冷たい指先が当たると、どうしてか胸の奥がぎゅっとなった。
「…お前と話すのは、べつに嫌いじゃねぇ」
「…!」
「この場所も、悪くない。また来てもいいと思えるくらいには、気に入った」
私の髪をそっと耳にかけたあと、その手は離れていった。
低くつぶやいた声は、来栖くんらしくどことなく不機嫌そうに聞こえた。
その不機嫌さが、今まで話してきた声音と同じで、ひどく安心する響きだった。
「…また誘ったら、一緒に来てくれる?」
「まぁ、気が向いたら」
「そ、そこはハッキリしたYESが欲しいところなんですけれど」
「毎日誘われでもしたらめんどくせぇし」
「さすがにそんなに誘いません!」
「どうだか……」
来栖くんはにやっと笑みを浮かべたあと、視線を下げて私の膝元を見る。
「つーか、それ」
「え? ………あ」
言われて私も見下ろして、声をあげる。
お弁当。まだ途中だった。
思い出すと、途端に空腹が蘇ってきた。
お昼じゃなくて、もうおやつの時間になっちゃったよ…。
「い、急いで食べるから! ちょっと待って」
「急ぐことねえだろ」
「けど…」
のんびり食べてる間に来栖くんが飽きて帰ってしまったら悲しい。
「いい。お前が食い終わるまでは、いてやる」
目を瞬かせる。
意外な言葉にキョトン…とすると、彼はムッとしたように私を睨んだ。
「んだよ」
「う、ううん。優しいなって…」
「………………いいから早く食え」
「は、はいっ」
早くしてほしいのか、急がなくていいのかどっちだろうと困惑しながら、私はお弁当のおかずを口に詰め込んでいく。
空腹のせいか、自然に囲まれた空気のせいか、いつもより美味しい。
お弁当に集中している間、なんとなく横から視線を感じた。
見られているとわかったけど、極力気にしないようにする。だってきっと笑ってるんだろうから。
今日の来栖くんの笑顔は、なんだかすごく、私の心臓に悪いのだ。