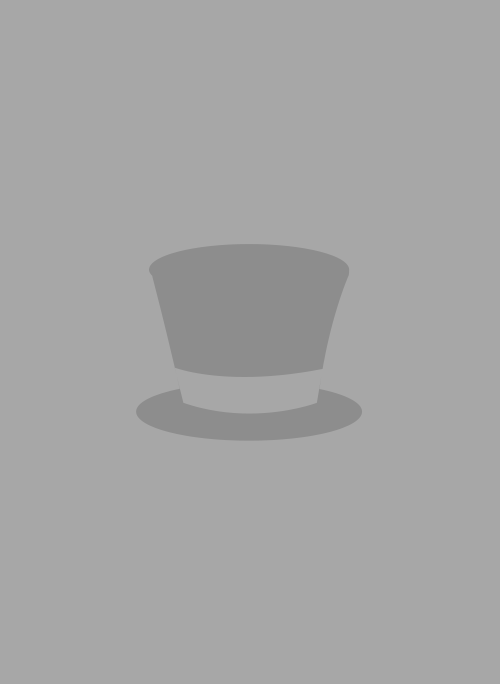「…ねえ、蒼佳」
顔を上げると、雅ちゃんの顔は険しさが増していた。
私が考えていることを見透かすようにまっすぐに見つめてくる。そのまなざしが私を諫めているように感じて、口にしようとした言葉をのみ込んだ。
「念のため言っておくけど、不良とヤクザはイコールじゃないよ。この学校にいる不良と同じレベルで考えてたら、それはやめときな。倍の倍はヤバい存在だと思っといたほうがいい」
「う、うん…。でもどうして?」
「ヤクザなんてマジで裏で生きてる人間なんだよ? 金のためなら平気で人を騙すし、女なんか店に売り飛ばしたりもする。そんな奴と平気で話してる来栖を、蒼佳はどう思うのよ」
「…それは…、怖いって、思うけど…」
ついはっきりしない言い方で言ってしまうが、雅ちゃんは険しい顔のまま言う。
「ヤクザの中にもいい人はいるんじゃないかとか思ってる?」
「…………」
ほぼ図星。
私の答えを察したのか、雅ちゃんは盛大にため息をついた。
「百歩譲ってマシな人間はいるかもしれないけどね、表面的にいい人に見えてもヤクザ業に加担してるなら結局は同じだと思うよ。来栖が話してた相手がそうだとか断言はできないけど、あいつと関わるにはリスクを念頭に置いといた方がいいと思う」
「うん…、そう…だよね…」
雅ちゃんの言っていることは間違ってない。
ヤクザは危険。
反社会勢力。
犯罪者グループ。
さまざまな言い方をされて、世間から一線置かれている存在。
わかってはいるつもりだ。ヤクザを怖いと思わないわけはない。できれば一生関わりたくなんかないものだ。
でも、じゃあ……、
来栖くんのことも、もっと警戒しながら接したほうがいいってこと?
今までみたいに気軽に話したりしてはだめってこと?
昨日みたいに一緒に勉強したりすることも?
―――あれ、私、なんかショックうけてる……。
なんだろう、これ、なんか…もやもやする。
ここ2日間で、少しだけ来栖くんと打ち解けられてきたような気がしてた。できればもっと話してみて、いろんな表情をする彼が見てみたいってそう思い始めていた。なのに、
来栖くんとの距離が、途端に最初に逆戻りしてしまった気がする。
来栖くんとは友達みたいになりたい。無意識にそんなふうに思ってた。
好きなときに話せて、好きなときに一緒にいられる、フランクな関係になれたらって。
昨日来栖くんと一緒にいて、面白かったし楽しかったから。
でも、それってよくないことなの?
ファイルに目を落としたまま、顔があげられなくなった。頭が重たくなる。
教室にはもうほとんど生徒は残っておらず、騒がしかった教室の中はすっかり静かになっていた。
「…ごめん」
ふいに、雅ちゃんが声を落として言った。
「ちょっとデリカシーなかった。あんたは来栖を優しいっていったのに、それを全否定するようなこと言ったね…」
「あ…ううん! 雅ちゃんが謝ることない! 雅ちゃんは正しいと思う。私って危機感が足りないんだ。無知なせいで、当たり前のことも理解できないで…」
「あたしの意見を鵜呑みにはしないでいいよ。あくまで個人の意見だって思って」
自分が言ったことを後悔しているかのように、雅ちゃんはきまりが悪そうに眉を困らせている。
……私を心配して、気を遣ってくれてるんだよね。
雅ちゃんは現場を見ているから、来栖くんに対しての印象は良くない方に傾くのは当然ことだ。加えてこんなに危機感に欠けている私を見れば、なおさらやきもきするんだろう。
「ありがとう、雅ちゃん。心配していってくれたんだよね?」
安心させるように私は笑った。
さっきみたいに、否定的な意見もはっきりというのは、雅ちゃんの一番の長所。
私のために言ってくれたんだってことはわかってる。
少し、時間が欲しい。頭が混乱してる。
新しい情報ばかりが入ってきて、それに引っ張られて大事なことを忘れそうになってるかもしれない。
雅ちゃんがスクールバッグを背負いなおし、軽く咳払いをした。
「あたしは帰るけど、蒼佳は勉強してくんだよね?」
「あ、うん!」
「あたしから言っておいてなんだけどさ…今の話、軽く頭の隅に置いておけばいいってだけだから。深く考えすぎなくていいからね」
念をおすように言ってくる雅ちゃんに、私は頷いた。
手を振って教室を後にする雅ちゃんの背を見送り、私は机のプリントを眺めて小さく息をついた。
放心しそうになる気持ちを叱咤して、筆箱からシャープペンを取り出して勉強にとりかかる。
目の前の古文の文章が、ことごとく「ヤクザ」に変換していき、私は1人きりになった教室で低く呻いた。