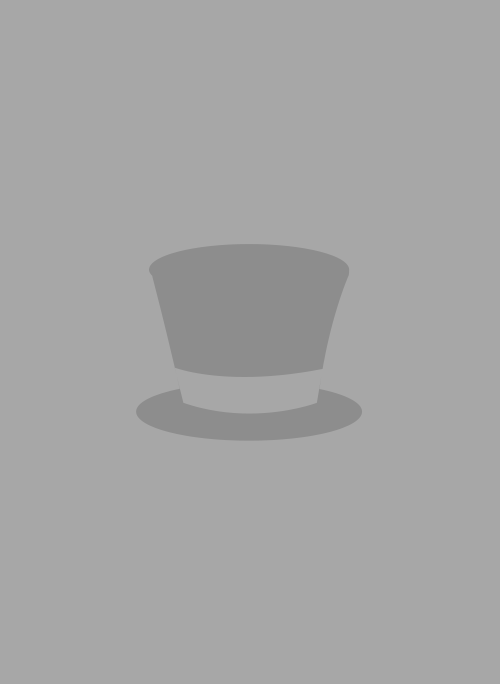*
「悪いな、水樹。テスト前だってのに雑用なんか頼んで…。勉強したいだろうが、どうしても人手が足りなくてな」
放課後。
鮫島先生に言われた通り、私は職員室の入り口まで来た。
先生、だいぶ疲れてるみたい…。
鮫島先生は体育の先生だし、テストはないから忙しくはならなさそうなのに、担任を持ってるからか常になにかに追われている。
本当に教師って大変な仕事だな。
言うことは聞かない、暴言は吐く、物は壊す、喧嘩は耐えない…こんな生徒をまとめるのってどんなに大変だろう。
「気にしないでください、先生。私にできることならいつでもお手伝いしますから」
せめてもの気持ちで、私は笑って明るく声を出した。
とたんに鮫島先生は「うっ…!」と口元を手で押さえて何やら涙ぐんだ。
鮫島先生って反応がオーバーというか……、身体も大きいし日に焼けてるから一見厳しそうに見えるのに、なんだか憎めない先生だよなぁ。若いせいか他の先生よりも親しみやすく感じる。
涙の滲む目元をぐいっと拭ってから、先生は持っていた白いロール紙と小さなメモ用紙を私に渡した。
「この用紙を黒板に貼っておいてほしいんだ。それから、このメモに書いた内容を黒板に書きこんでおいてくれ。うちのクラスと、それからB組とC組の教室にも同じことを頼みたいんだが…」
私はロール紙が3つあることを確認して、頷いた。
「わかりました」
「本当にすまん。助かるよ水樹! もし誰か助っ人をつかまえられたらすぐに寄こすから!」
先生はほっとしたように笑うと、他の先生に呼ばれた声に応じて職員室へ入っていった。
放課後とはいえまだ13時を過ぎたばかりだから、どの教室にもぱらぱらと生徒が残っている。
他の組の教室に入るのって、まだちょっと緊張する…。
だけど任されたからにはそんなこと気にしてはいられない。
私はまずC組に入った。
じろじろと無遠慮な視線を感じる。
気にしない、気にしない…。
心を無にして私は黙々と言われた通りに作業する。
C組を問題なく終え、B組でも同じ作業に取り掛かろうとするが、黒板に用紙を広げたところで、磁石がないことに気づく。
周りを探しても、目のつくところには見当たらなかった。
他のクラスだと勝手が違うから困るな…。どうしよう?
他のクラスにいるという緊張と、磁石がない焦り。教卓の前を無意味にうろうろしていると、残っていた生徒の一人が近寄ってきた。
「ねえ、お前どこの組の奴?」
「えっ……」
どきっとして手に力が入り、思わず持っていたロール紙を握りつぶしそうになる。
「うちのクラスじゃないよな」
「知らねー。こんな女子うちの学年にいたっけ?」
1人が来るともう1人、とあっという間に3人の男の子たちが私を囲んだ。
興味津々にまるで未確認生物を見るような目で私をじろじろと見てくる。
3体1。男に女。圧倒的不利。
やっぱり他のクラスの人って怖い…!
自分のクラスのメンバーなら見慣れているから怖くないのに、他クラスとなると途端に人見知りバリアが発動してしまう。
「あ、あの、磁石を使わせてもらいたいんですが見当たらなくて…どこにあるんでしょうか…?」
「ああ? 磁石ぅ?」
「知らね~、何に使うんだよそんなもん」
「この紙、黒板に貼らなくちゃいけないんです」
私がロール紙を持ち上げて言うと、男の子たちは「なにそれ、でっけー!」と興味を示して声を上げた。
「みんなでお絵かき大会でもしようって? 楽しそ~」
「二本あるしチャンバラできんじゃん、おい、やろうぜ」
「あっ、ち、ちょっと!」
ひったくられるようにしてロール紙を奪われる。
止める間もなく、彼らは紙を振り回してあそびはじめてしまう。
高校生にもなってロール紙でチャンバラって! 考えることがもう小学生。
ど、どうしよう、このままにするわけにいかないのに。
2本も奪われてしまったせいで、私のクラスに貼る紙もない。
こういうとき、雅ちゃんならビシッと注意できるんだろうけど、彼女はもうとっくに帰ってしまった。
最近雅ちゃんはゲームセンターのリズムゲームにハマっているらしく、毎日通いつめてパーフェクトクリアを目指しているらしい。今日もHRが終わったらいつの間にか消えていたので、きっと今頃センター内のスクリーンとにらみ合いをしている頃だろう。
自分でなんとかしなきゃ。つい雅ちゃんをいつも頼ってしまう。悪い癖だ。自分の意見を主張できない性格は昔から一向になおらない。
私は手をぐっとにぎりしめる。
腹をくくり、声を張った。
「すっ…、す、すみません!! それ、返してもらわないと困―――」
瞬間、
ばしんッ!
頬に、振り回されたロール紙の先が直撃した。
ツッと熱く鋭い痛みが頬を刺す。
「あ、やっべ」
詫びれた様子もない声がつぶやくのが聞こえた。
当たった頬に手をあてる。
痛い…。
ひりひりする。
何か、言い返してやりたかった。
でも頭が真っ白で、棒立ちのまま固まって動けなかった。
「悪ぃ、ちょっと手がすべっ―――」
男の子の1人がそう言いかけた次の瞬間、
その人の身体が、派手な物音と共に床に倒れ込んだ。
一瞬、目に見えない力で急にその人が吹き飛ばされたように見え、私含めその場にいた全員が目を見張った。
私のすぐ横に誰かがたった。
思わず見上げて、真っ先に目に入った金髪の髪に小さく声をあげる。
「く………」
来栖くん…!?
「ガキみてえなことしてんじゃねえよ、ガキ」
呼びかけようとした声は、本人の声によって阻まれる。
倒れ込んだ男の子と立ち尽くす2人も、目を見開いたまま驚愕の表情を浮かべていた。
「A組の、来栖礼央…!?」
なぜB組に彼がいるのか、なぜこの場に現れたのか、驚く要素はたくさんあるだろうけれど、きっとそれ以上に彼らが驚いたのは、『彼が自分から喋った』ことに違いない。
「こ、こいつ、喋れんのかよ」
情けない声で誰かが呟く。
こんな状況でそんな言葉がでるくらいだ。
来栖くんはこの場の全員の注目を受け、舌打ちする。倒れ込んだままの男の子を顎でしゃくった。
「そいつ、邪魔。おめぇらも目障り。さっさと消えろ」
淡々とした声。その単調さが逆に彼の怒りを感じさせ、助けられたはずの私まで変な汗が出た。
昨日有須さんへ向けて発した声とはまた違う声色。部屋全体がピリピリと緊張感に満ちる。
来栖くんのただならぬ気迫に男の子たちはサッと顔を青ざめて、倒れこんだ男の子を引きずるようにしてあたふたと教室を出ていってしまった。
乱れた机と椅子と、床には無造作に放られたくしゃくしゃのロール紙が残る。
来栖くんは無言でそれを拾った。
私の前を通り過ぎて、黒板の前に立つ。
見つけられずにいた磁石を彼は簡単に探し出してしまうと、何も言わないまま紙を黒板に貼りはじめた。
なにがなんだかわからなくて、ぼけっと突っ立ったまま彼の動作を目で追っていた。だけどすぐに我に返り、彼の横に立ちメモの内容をチョークでかき込んでいった。
私がメモを書き終えると、そのタイミングを見計らったように来栖くんは残りのロール紙を持ってすたすたと教室を後にしてしまう。
私は慌てて追いかけた。