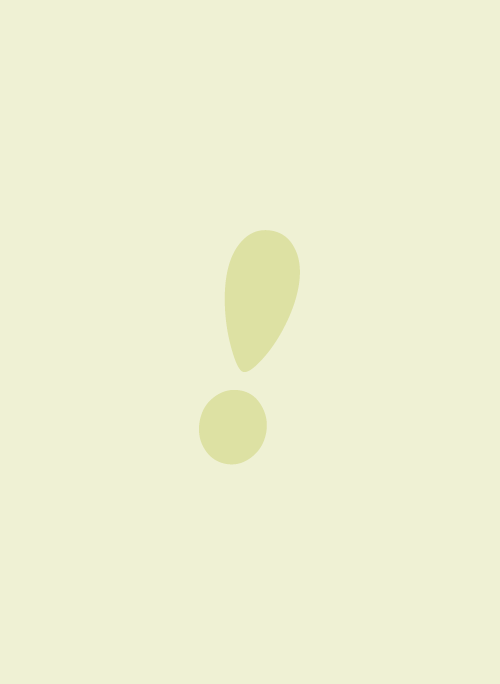癖というのは、なかなか治らないものである。
古いベッドに座り込み壁に身を預ける彼の指
は、今日も変わらずボロボロだ。特別、肌が弱いだとか皮膚病だとか、そういうことではなかった。所謂、癖である。彼には自身の爪や皮膚をむしったり噛んだりしてしまう、そういった癖が昔から変わらずあったのだ。
彼は今日も、難解なパズルのピースを一つ一つ埋めるように、自らの指の皮むけを弄っていた。薄暗い部屋で1人、自傷とも言えるその癖に勤しんでいるとふと、部屋にあるたった一つの窓が少しだけ開いていることに気がついた。
その申し訳程度に設置してある小さな窓からは暗く淀んだ空が顔を覗かせる。今にも雨が降り出しそうで、そういえば何だか空気も水っぽい匂いだな、と彼は思った。風もいつもよりは少し強く、恐らく台風かなとまた思って、そのほんの少し開いた窓を閉めようかと重い腰を上げた。
カタカタと細かく揺れる窓に手をかけると、左にスライドする。おかしい。上手く閉まらなかった。立て付けが悪いのだろうか?かなり古い家屋だからしょうがないといえばしょうがないのだが。彼はより一層の力を込め引っ張るように窓に力を込めた。
しかし、閉まらない。変だな、とは彼も感じたのだろうが、彼は別にそこまで窓に固執することも無くすぐにベッドに戻った。閉められないのならしょうがない。そうしてまたくすんだ白い壁に背中を押し付けた。
彼の今いる部屋は簡単に言えば物凄く質素で、壁は全面雪のように白かった。日がみえず暗い日に見る雪はこういう感じで青くくすんだ白色だったな。と彼はこの部屋に初めて入った時に言った。床はフローリングだが、こちらはなかなかに手入れされており艶やかな木目が今のこの重い雰囲気とは相対的だ。
何も無い、ベッドしかないこの部屋に彼は何日も居座っていた。いや、居座るというよりは、むしろ部屋そのものに、ここから出るなと支配されている感覚すらあった。
陰鬱な表情でまた爪を眺めているその時だった。
「こんにちは」
突如として聞こえてきたその声に彼は少しだけ肩を跳ねさせた。
中性的で抑揚のあるいい声だった。彼は直ぐに、先程閉めようとしていた窓に視線を移す。この部屋で人が出入りできるのはそこだけなのだから。見ると、窓の外に人影があるのに気がついた。窓が閉まらなかったのは、て彼女が強く抑えていたからのようだと、窓枠にある華奢な手で合点がいった。
「久しぶりだね」
正体のわからぬ誰かがまた口を開く。
─誰?
「やだ、忘れちゃったの?…ああ、それとも今は…違うのか。」
可笑しそうに笑う。口調からして女性だろうか?いや、女性のような話し方する男性という可能性もある。
─いいから、姿を見せろよ。
彼は少しだけ口調を荒らげていってみた。ようやくそれで自分の姿を見せる気になったのだろうか、彼女─恐らくだが─は窓に触れていた手を左にずらして窓を開けてみせた。
「こんにちは」
2回目の挨拶を口にする彼女。
「私はミサキだよ。見覚えないかな。」
ミサキ…。彼女はそうなのった。ミサキというのが本名なのか、それとも仮名なのかは別として彼には全く聞き覚えがなく、特に何も言えずに黙りこくった。
結局彼は行き場のないセリフを飲み込み、ミサキという人間を観察することに決めた。まず、顔をじっくりとみつめる。
ミサキはやはり女性であった。体は女性らしく丸みを帯びたラインが可愛らしい。胸部には膨らみもあった。ショートヘアはふんわりと美しくセットされていて、透けるような漆黒の
古いベッドに座り込み壁に身を預ける彼の指
は、今日も変わらずボロボロだ。特別、肌が弱いだとか皮膚病だとか、そういうことではなかった。所謂、癖である。彼には自身の爪や皮膚をむしったり噛んだりしてしまう、そういった癖が昔から変わらずあったのだ。
彼は今日も、難解なパズルのピースを一つ一つ埋めるように、自らの指の皮むけを弄っていた。薄暗い部屋で1人、自傷とも言えるその癖に勤しんでいるとふと、部屋にあるたった一つの窓が少しだけ開いていることに気がついた。
その申し訳程度に設置してある小さな窓からは暗く淀んだ空が顔を覗かせる。今にも雨が降り出しそうで、そういえば何だか空気も水っぽい匂いだな、と彼は思った。風もいつもよりは少し強く、恐らく台風かなとまた思って、そのほんの少し開いた窓を閉めようかと重い腰を上げた。
カタカタと細かく揺れる窓に手をかけると、左にスライドする。おかしい。上手く閉まらなかった。立て付けが悪いのだろうか?かなり古い家屋だからしょうがないといえばしょうがないのだが。彼はより一層の力を込め引っ張るように窓に力を込めた。
しかし、閉まらない。変だな、とは彼も感じたのだろうが、彼は別にそこまで窓に固執することも無くすぐにベッドに戻った。閉められないのならしょうがない。そうしてまたくすんだ白い壁に背中を押し付けた。
彼の今いる部屋は簡単に言えば物凄く質素で、壁は全面雪のように白かった。日がみえず暗い日に見る雪はこういう感じで青くくすんだ白色だったな。と彼はこの部屋に初めて入った時に言った。床はフローリングだが、こちらはなかなかに手入れされており艶やかな木目が今のこの重い雰囲気とは相対的だ。
何も無い、ベッドしかないこの部屋に彼は何日も居座っていた。いや、居座るというよりは、むしろ部屋そのものに、ここから出るなと支配されている感覚すらあった。
陰鬱な表情でまた爪を眺めているその時だった。
「こんにちは」
突如として聞こえてきたその声に彼は少しだけ肩を跳ねさせた。
中性的で抑揚のあるいい声だった。彼は直ぐに、先程閉めようとしていた窓に視線を移す。この部屋で人が出入りできるのはそこだけなのだから。見ると、窓の外に人影があるのに気がついた。窓が閉まらなかったのは、て彼女が強く抑えていたからのようだと、窓枠にある華奢な手で合点がいった。
「久しぶりだね」
正体のわからぬ誰かがまた口を開く。
─誰?
「やだ、忘れちゃったの?…ああ、それとも今は…違うのか。」
可笑しそうに笑う。口調からして女性だろうか?いや、女性のような話し方する男性という可能性もある。
─いいから、姿を見せろよ。
彼は少しだけ口調を荒らげていってみた。ようやくそれで自分の姿を見せる気になったのだろうか、彼女─恐らくだが─は窓に触れていた手を左にずらして窓を開けてみせた。
「こんにちは」
2回目の挨拶を口にする彼女。
「私はミサキだよ。見覚えないかな。」
ミサキ…。彼女はそうなのった。ミサキというのが本名なのか、それとも仮名なのかは別として彼には全く聞き覚えがなく、特に何も言えずに黙りこくった。
結局彼は行き場のないセリフを飲み込み、ミサキという人間を観察することに決めた。まず、顔をじっくりとみつめる。
ミサキはやはり女性であった。体は女性らしく丸みを帯びたラインが可愛らしい。胸部には膨らみもあった。ショートヘアはふんわりと美しくセットされていて、透けるような漆黒の