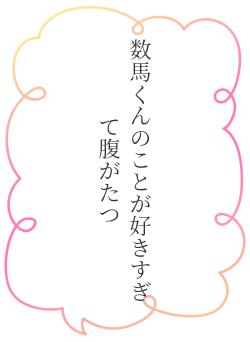「蓮──、私、できるだけ部活早く切り上げて帰るからって、大丈夫だって話してたのに……。来てくれてたんだ!」
「ああ、うん。んじゃっ、俺、すぐ帰るわ」
その後、お姉ちゃんの看病は蓮くんと比べると少し手荒いように感じた。
「ほら、温めた梅干し粥。スプーン持って自分でしっかり食べな!」
ドンと目の前に熱々のお粥を置かれ、スプーンをしっかりと握らされる。
ああ、ありがたや。
「お姉ちゃん、お粥、フーフーしてくれないの?」
無理だとは分かっているけれど、お姉ちゃんにねだってみる。
「あんた、何……、甘えてんの?!」
お姉ちゃんの目つきが急に鋭くなる。
さっき、自分がねだったことを少し後悔をする。
「まさか……、また、今日もさっき蓮に甘えてたんじゃないでしょうね?」
「甘えてないよ……」
「本当に?」
「……うん」
「あやしい。蓮に聞くよ?」
「お姉ちゃん、まるで取り調べしてる人みたいだよ!」
「ほんと、蓮はいつも彩歌には甘いからね……」
翌日の朝、私の熱がすっかり下がり、元気に学校へ行くことができた。
私は、蓮くんが好きな人を知っている。
たぶん、あの人だ。
蓮くんがいつも目で追っている人。
そう、それは、きっと私のお姉ちゃんだ──。
私はお姉ちゃんと好きな人が重なってしまったことが今は本当に辛い。
なら、今のうちに自分の気持ちは誰にも秘めたまま静かに身を引こう。
まずは、私はこの広い地球で蓮くんと出会えた奇跡に感謝をして。
そして、今もこうやって幼馴染でいられることに感謝。
これ以上のことを望むと何だかバチが当たりそうな気がして。
「ああ、うん。んじゃっ、俺、すぐ帰るわ」
その後、お姉ちゃんの看病は蓮くんと比べると少し手荒いように感じた。
「ほら、温めた梅干し粥。スプーン持って自分でしっかり食べな!」
ドンと目の前に熱々のお粥を置かれ、スプーンをしっかりと握らされる。
ああ、ありがたや。
「お姉ちゃん、お粥、フーフーしてくれないの?」
無理だとは分かっているけれど、お姉ちゃんにねだってみる。
「あんた、何……、甘えてんの?!」
お姉ちゃんの目つきが急に鋭くなる。
さっき、自分がねだったことを少し後悔をする。
「まさか……、また、今日もさっき蓮に甘えてたんじゃないでしょうね?」
「甘えてないよ……」
「本当に?」
「……うん」
「あやしい。蓮に聞くよ?」
「お姉ちゃん、まるで取り調べしてる人みたいだよ!」
「ほんと、蓮はいつも彩歌には甘いからね……」
翌日の朝、私の熱がすっかり下がり、元気に学校へ行くことができた。
私は、蓮くんが好きな人を知っている。
たぶん、あの人だ。
蓮くんがいつも目で追っている人。
そう、それは、きっと私のお姉ちゃんだ──。
私はお姉ちゃんと好きな人が重なってしまったことが今は本当に辛い。
なら、今のうちに自分の気持ちは誰にも秘めたまま静かに身を引こう。
まずは、私はこの広い地球で蓮くんと出会えた奇跡に感謝をして。
そして、今もこうやって幼馴染でいられることに感謝。
これ以上のことを望むと何だかバチが当たりそうな気がして。