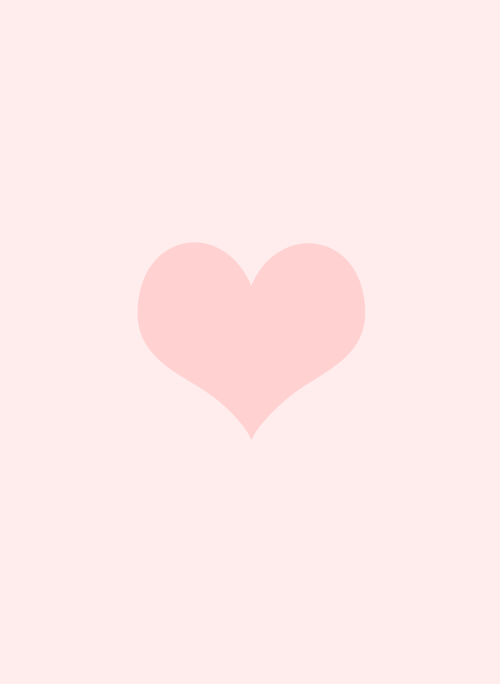「これだったら………撒けるな。おい、空澄。俺に掴まってろ」
「え………?」
「そんなんじゃダメだ。腕を首にまわして」
「は、はい……」
「いくぞッ!」
この魔王は何故、自分を助けてくれたのか。
母から教わった呪文は何だったのか。
そして、目の前の男はどうして自分の名前を知っているのか。
そんな疑問が頭をよぎった。けれど、その考えは一気に消えてしまう。
ジェットコースターのように、突然体が勢いよく動き出したのだ。
「ーーーーっっ!!」
あまりに高速で、叫び声も出なかった。
必死に彼にしがみつくと、男が「くくくっ」と笑う声が聞こえてきたけれど、それに文句を言っている暇もなく、空澄は苦しさと恐怖に耐えたのだった。
けれど、それもあっという間の体験だった。
男は空澄の家に戻り、鍵がしまっているはずのドアに手を差しのべ「-----------」と、聞いたこともない言葉を発すると、ガチャンとドアの鍵をかけ、そして今度ほ長い呪文を唱えた。
「これで、今日は諦めるだろうが……」
と、男は独り言を呟いていた。
沼の水で濡れた冷たい体を抱きしめながら、恐る恐る彼を見上げる。
すると、その黒の男は空澄の方を向き、安堵した表情で優しく微笑んだ。
「やっとあの呪文を言ってくれたんだな」
その声と表情を見てしまったら、空澄はその男が怖いとは思えなくなってしまった。
それぐらいに優しく、そして懐かしい微笑みだった。