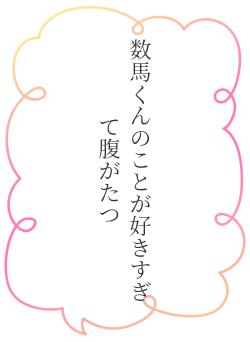だから、両親に本当のことは言っていない。
学校が嫌いなこと。
いじめられていることも。
自分の耳が本当は嫌なことも。
普通に聞こえる人達を羨ましく、妬ましく思ったことも。
どうして、私だけ、……ってことも。
だけど、今まで言えなかったことを太宰さんには打ち明けられた。
きっと、太宰さんと私は何の繋がりもないからなのかもしれない。
ちょうど良い関係。
素直な気持ちで伝えられた。
なんの迷いもなく。
──不思議だ。
気づくと筆談用のノートに私の涙がボタボタとこぼれ落ちていた。
太宰さんが無言のままティッシュを私に差し出した。
【今まで、本当に色々と辛かったんだね。ありがとう、僕に話してくれて】
【……ありがとう?】
【話しにくいことなのに、僕にこうしてきちんと話をしてくれたことが嬉しかったんだよ】
太宰さんが優しく微笑んだ。
それはまるで陽だまりのような微笑みだった。
「辛いと思っていたのは、僕だけじゃなかったんだ──」
太宰さんがそう呟いたのがわかった。
私にはこういう人が必要だったんだとこの時実感した。
時計を見るともうすぐ日付がかわろうとしていた。
翌朝に備えて私と太宰さんはそれぞれの自分の部屋に戻った。