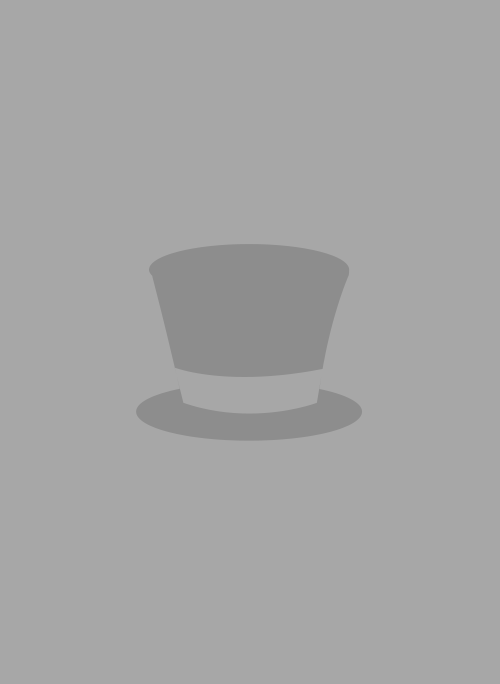第1話 傷痕に降り注ぐ雨
しとしとと薄暗い雲から、今日もまた雨が落ちてきた。誰かが空の上で泣いているのだろうか?どれほどの時間をそんな馬鹿馬鹿しい、妄想に浸ってやり過ごしただろう。
嗚呼、まだ雨は止まないのだな。いつもこうだ。嫌な過去を引き連れてくるから、雨が嫌いだった。しばらく屋根のついたベンチで、横殴りの雨と突風をその身に受け止めていた。
が、突然それが途絶えた。朦朧と消え失せそうな意識を必死に、引き戻そうと目を凝らすが、視界がぼやけたままだ。焦点が定まらない。
誰かが俺・青柳龍一(あおやぎりゅういち)に何か言いながら、揺り起こそうとするが、その人物の姿を捉える前に俺の意識が水底に沈むのが早かった。
「ーーーん、えっ、どこだここ?」
昨日のことを思い出そうとするが、どうやってここまで移動したのか、そもそもここがどこなのか、全く身に覚えがない。
客用かと思われるふかふかの羽毛ぶとん、枕や布団カバーは、小花が散りばめられた、いかにも女物だと伺える。
さらに布団の枕元にある、姿見には綺麗に傷が処置されていた。瀕死の大怪我を負っていたはず、これは明らかにプロだ。一般人とは考えられないほど、完璧に傷が塞がっていた。
家主はどこだ?という疑問がふと浮かんだ。医療関係者である可能性は高いが、なぜ助けたのだろうか。街ゆく人らは誰も遠巻きに避けて、近付こうともしなかった。
「あ、気がついた?」
まるで友人と話をするように、彼女はノックもせず部屋に入ってきた。自然体で柔らかく包み込むような声の持ち主だった。間違いない。俺が気絶する前に、聞いた声だ。
「誰だお前!」
「そんなに警戒しなくていいよ。他には誰もいないから。それとも、傷塞いではおいたけどまだ痛む?」
「いや」
俺の素っ気ない、警戒心むき出しの返答にも、怯むことなく涼しげに微笑みで、さらりと受け流した。
ただの世話焼きではなく、どうやら肝が座っているようだ。あまり彼女は物怖じしない性格の持ち主なのだろう。
「お前何者なんだ。医療知識があるのか?」
「そりゃあ、医学生だから。怪我人をあんな雨の中放置できないよ」
俺の背中には刺青があり、ヤクザであることは一目瞭然だ。それでも俺がただ負傷しているという理由だけで、彼女は保護したと言うのか。全く理解できなかった。
まさかヤクザだと知らないまま、連れてきただけなのだろうか?と訝り、彼女に確認しようとした。
しかし、その前に遮るように、奥からガタンッと何かが落ちる音がした。俺にはそれが何か分からなかったが、その音で呆れながらも、取り敢えずゆっくり養生するように言うと、彼女はすぐに出て行った。
その後を追って、俺はとんでもない光景を目の当たりにした。
雑種と思われる猫が五匹が彼女の周りを取り囲み、猫が陣取っているためか、少しだけ離れた位置にドーベルマンやゴールデンレトリバーなどの大型犬が三頭は床に突っ伏したまま微動だにしない。さらに茶色とブルーがかったデグーが二匹、三匹のコツメカワウソに追いかけられ、逃げ惑っていた。
ここは動物園かと、突っ込みたくなるほどの騒々しさだ。俺を保護したのと同じように、ここにきたのだろうか。
「あれ、まだ休んでいても良かったのに」
床に座って猫を優しい手つきで撫でながら、こちらには顔も向けずに、声をかけてきた。肝が座りすぎていると感じたのは、刺青を見ていないからではないかと思って直接聞くことにした。
「聞きたいことがある。背中の彫り物ーーー」
「ああ、見たよ。生き生きとした見事な桜吹雪と、死を連想させる紫色の蝶々だっけ。生と死の狭間って感じだよね。まあ見えないところに刺青があっても保護したと思うよ」
知っていた。彼女は全てを知っていながら、ここまで手厚く看病したのだ。益々分からない。他の通行人がそうしたように、我関せず素通りすることもできたはずだ。何故そうしなかったのか。
どうにも答えになっているようで、上手くはぐらかされたような、なんとも言えない答えだった。
しとしとと薄暗い雲から、今日もまた雨が落ちてきた。誰かが空の上で泣いているのだろうか?どれほどの時間をそんな馬鹿馬鹿しい、妄想に浸ってやり過ごしただろう。
嗚呼、まだ雨は止まないのだな。いつもこうだ。嫌な過去を引き連れてくるから、雨が嫌いだった。しばらく屋根のついたベンチで、横殴りの雨と突風をその身に受け止めていた。
が、突然それが途絶えた。朦朧と消え失せそうな意識を必死に、引き戻そうと目を凝らすが、視界がぼやけたままだ。焦点が定まらない。
誰かが俺・青柳龍一(あおやぎりゅういち)に何か言いながら、揺り起こそうとするが、その人物の姿を捉える前に俺の意識が水底に沈むのが早かった。
「ーーーん、えっ、どこだここ?」
昨日のことを思い出そうとするが、どうやってここまで移動したのか、そもそもここがどこなのか、全く身に覚えがない。
客用かと思われるふかふかの羽毛ぶとん、枕や布団カバーは、小花が散りばめられた、いかにも女物だと伺える。
さらに布団の枕元にある、姿見には綺麗に傷が処置されていた。瀕死の大怪我を負っていたはず、これは明らかにプロだ。一般人とは考えられないほど、完璧に傷が塞がっていた。
家主はどこだ?という疑問がふと浮かんだ。医療関係者である可能性は高いが、なぜ助けたのだろうか。街ゆく人らは誰も遠巻きに避けて、近付こうともしなかった。
「あ、気がついた?」
まるで友人と話をするように、彼女はノックもせず部屋に入ってきた。自然体で柔らかく包み込むような声の持ち主だった。間違いない。俺が気絶する前に、聞いた声だ。
「誰だお前!」
「そんなに警戒しなくていいよ。他には誰もいないから。それとも、傷塞いではおいたけどまだ痛む?」
「いや」
俺の素っ気ない、警戒心むき出しの返答にも、怯むことなく涼しげに微笑みで、さらりと受け流した。
ただの世話焼きではなく、どうやら肝が座っているようだ。あまり彼女は物怖じしない性格の持ち主なのだろう。
「お前何者なんだ。医療知識があるのか?」
「そりゃあ、医学生だから。怪我人をあんな雨の中放置できないよ」
俺の背中には刺青があり、ヤクザであることは一目瞭然だ。それでも俺がただ負傷しているという理由だけで、彼女は保護したと言うのか。全く理解できなかった。
まさかヤクザだと知らないまま、連れてきただけなのだろうか?と訝り、彼女に確認しようとした。
しかし、その前に遮るように、奥からガタンッと何かが落ちる音がした。俺にはそれが何か分からなかったが、その音で呆れながらも、取り敢えずゆっくり養生するように言うと、彼女はすぐに出て行った。
その後を追って、俺はとんでもない光景を目の当たりにした。
雑種と思われる猫が五匹が彼女の周りを取り囲み、猫が陣取っているためか、少しだけ離れた位置にドーベルマンやゴールデンレトリバーなどの大型犬が三頭は床に突っ伏したまま微動だにしない。さらに茶色とブルーがかったデグーが二匹、三匹のコツメカワウソに追いかけられ、逃げ惑っていた。
ここは動物園かと、突っ込みたくなるほどの騒々しさだ。俺を保護したのと同じように、ここにきたのだろうか。
「あれ、まだ休んでいても良かったのに」
床に座って猫を優しい手つきで撫でながら、こちらには顔も向けずに、声をかけてきた。肝が座りすぎていると感じたのは、刺青を見ていないからではないかと思って直接聞くことにした。
「聞きたいことがある。背中の彫り物ーーー」
「ああ、見たよ。生き生きとした見事な桜吹雪と、死を連想させる紫色の蝶々だっけ。生と死の狭間って感じだよね。まあ見えないところに刺青があっても保護したと思うよ」
知っていた。彼女は全てを知っていながら、ここまで手厚く看病したのだ。益々分からない。他の通行人がそうしたように、我関せず素通りすることもできたはずだ。何故そうしなかったのか。
どうにも答えになっているようで、上手くはぐらかされたような、なんとも言えない答えだった。