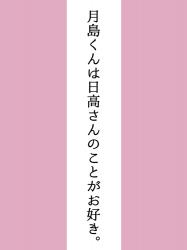***
彼女がいつものように来店した。もうそこは特等席と化したカウンターの1番奥の席。
注文したのはもちろんホットコーヒー。
僕は毎週火曜日と木曜日の夜に彼女が訪れていることに気づいた。年齢は同じくらいだと思うけれど、名前も何も分からない。話しかけてみようかな、なんて幾度となく思ったが上手く話が切り出せないのだ。自分は男子中学生かよと呆れる。
他のお客さんのように世間話や天気の話をしたらいいのに。そのもどかしさを抱えたままここ最近は働いている。
とにかく、今日も彼女を笑顔にしよう。
気合を入れていつもの器具を手にかける。淹れているこのコーヒーを今から彼女が飲むのだと考えたら、少し手が震えた。
早くコーヒーを飲んで欲しい、彼女が最初のひと口を運ぶ間、ドキドキしていた。あともう少し。あともう少し。早くその笑顔を見せてほしい。
そして、彼女はまた笑った。
すると僕の胸の内側からポカポカと暖かくなる。嬉しくなる。顔が緩んでしまう。どうかして彼女と話してみたい。
いつも昼間の時間に訪れる腐れ縁の由紀に相談してみた。一応小説家の端くれだし、高校大学とずっと一緒に過ごしてきたのは彼だから。相談を持ちかけた時、彼は少し驚いたような顔をしていたけれど、ちゃんとアドバイスをくれた。
***
今日は彼女が来店する日。でも、まだこない。時間はもう過ぎているのに。
接客をしている時も、コーヒーを淹れている時も、ドアの方を気にして仕事にならなかった。もしかして他のお店に行ってしまったのではないか、なんて彼女には関係ないことなのにただ不安になってしまった。好きなこの喫茶「ベコニア」の場所さえ、少し色褪せて見える。
彼女がいつきた時でも座れるように、「予約席」なんて暇な時間帯に作ってみたプレートが寂しくカウンターの一番奥の席にポツンと置かれている。
やがて彼女はやってきた。同時に僕の視界は彩度が上がる。
少し疲労を見せた表情をしていた。きっと残業でもしてきたのだろう。ホッとした気分になった。良かった、また会えて。
そして彼女が注文したのはやっぱりホットコーヒー。
笑顔にさせたい、そう思いながら淹れていたコーヒー。今日、話しかけてみようかな。早く、早く、と気持ちばかりが先を行く。今日きたらサービスしようと思っていたクッキーもそろそろ焼ける頃だろう。
皿洗いや明日の準備なんて全て後回しにして、全力で彼女のコーヒーのために動く。効率なんて二の次だ。今の僕には必要ない。
僕が淹れたコーヒーをひと口。
彼女はやっぱり笑顔になった。合わせて僕も笑顔になる。
ひと息ついた時、意気込んで僕は彼女に話しかけてた。
「今日の香りは気にいってくれましたか?」と。
この時、初めて彼女の目をしっかり見ることができた。何の濁りもないその瞳に僕が映っている。そう思うだけで体温が上がるのを感じた。
そしてようやく彼女の名前を知ることができた。橋本奈央さんと言うらしい。心の中で何度か刻み込むように唱える。やはり今日は残業のため遅くなってしまったらしい。
クッキーを差し出すと、申し訳なさそうにしながらも受け取ってくれた。すぐに「おいひい…」と声に出し目をキラキラさせている彼女に見入ってしまう。そのままこちらを向いた彼女と目が合い、何とも言えない感情が湧き上がってきた。
橋本さんのことが知りたくなり、仕事のことを聞いてみると普通のOLだと言った。それもこの一杯のコーヒーを楽しみにしているただのOLだと。
本当に彼女はコーヒーが好きらしい。僕も嬉しくなる。
そして話を進めていく中で、彼女はこう言った。
「桐山さんの淹れるコーヒーって、誰が淹れたものよりも美味しいんですよね」
僕の中の何かの枷が外れた。
彼女が初めて来たあの日からの記憶が走馬灯のように頭の中を駆け巡っていく。
思い出すのは彼女の笑顔、笑顔、笑顔。
そして今、自分の目の前で笑みを浮かべる彼女にドクドクと聞こえそうなくらい心臓が騒ぎ始めた。
あぁ、そういうことなんだ。
なぜこの仕事をしようと思ったのか。彼女から聞かれた質問。
それは幼き日から始まる、話せばとてもシンプルな理由だった。
でも今回はちょっと違うみたいだ。
「僕が淹れたコーヒーで、大切な人を笑顔にしたい。今はそれだけです」
僕は彼女を笑顔にさせるためにコーヒーを淹れていたんじゃない。
彼女の笑顔が見たくて僕はコーヒーを淹れたい。
ただ名前を知っただけなのに、ただお付き合いしていない人がいないと知っただけなのに。それだけで彼女との未来を想像してしまった。コーヒーを片手にガラス張りの壁から商店街を見下ろす彼女の横顔を見つめる。己の瞳に熱がこもっていくのを感じてふと笑みがこぼれる。
あの日、僕は彼女の笑顔に一目惚れをしていたのだ。