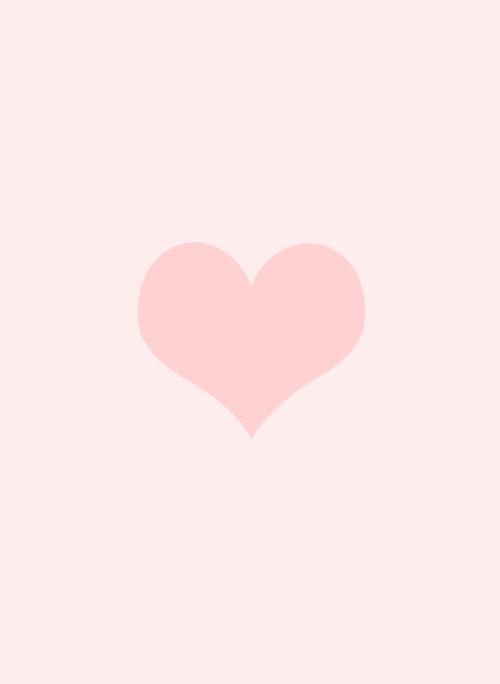「お母さんとお父さん、心配しているだろうなぁ」
「いねぇよ。父さんなんか」
「そうなのか?」
「ああ。俺には、父さんなんていない」
なんでこんなこと、
こんなやつに話しているんだろうか。
ポツリと落ちた言葉は苦しくも辛くもなかった。
お父さんとお母さんが心配している。
それは俺に当てはまるのか?
母さんも父さんも、俺を見てはいない。
全部自分たちのために俺を見ているだけだ。
俺は独りだ。完全に独りなんだ。
「俺にも、両親はいない」
「えっ」
「ずっとばあちゃんと二人暮らしだった。
そのばあちゃんも、高校の頃に亡くなって、
それからは俺はずっと一人だ。
楓くんの寂しさは、俺にはよく分かる」
両親がいないと言ったおっさんは
少し悲しそうに眉を下げた。
でも、その口ぶりはその寂しさは
遠い昔のことなんだと物語っている。
だって、淡々と話すから。
「別に、寂しくなんかねぇよ」
舌打ちをしてポケットに手を突っ込む。
するとおっさんは、ははっと笑った。
「そうか。俺は、寂しかった。
毎日親がいない現実に打ちひしがれて、泣いたよ。
どうしてこんな俺を置いていってしまったんだって。
毎日思わなくちゃいけなかった」
「そんなに毎日泣いてたのかよ。だっせぇ」
「だっせぇことかもしんないけど、
俺にとっては大事なことだったんだ。
記憶の整理をして、現実を知る。
それはすごく苦しいし、辛かったし、寂しかった」
何言ってんだ、このおっさん。
おっさんの言葉が分からなくて黙った。
記憶の整理なんかしなくたって、
嫌でも思い知る。
俺には父さんがいなくて、母さんは裏切り者だ。
その現実にいちいち寂しいも何もあるか。
あるのはただ、憎しみだけ。
「だから、これからはなんでも俺に話すといい。
俺だけは、楓くんの味方だから」
「はっ。気持ちわりぃな。誰があんたに話すかよ!」
「それでもいい。心のどこかで、拠り所は
ここにあるって知っておいてもらうだけでいい。
きっと、俺は君の力になると思うよ」
おっさんが笑う。
俺はその笑顔を、もう気持ち悪いと思うことはなかった。