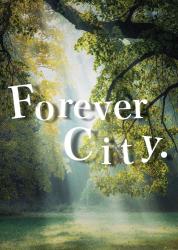あの時、私達は一体、彼にどんな言葉を返すべきだったのだろう。
「 透過くん、おはよう! 」
「 …よ、透過。 」
次の日、既に席に座っていた透過くんに私と碧が明るく声を掛けると、クラスメイトは皆驚いてこちらに目を向けた。
当の本人は窓の外を見つめたままで、返事はもちろん返ってこない。
「 碧藍さん、榎葉くん! 」
返事どころか、全くこちらを見ない透過くん。
昨日、理事長室の前であの話を聞いていた彼は、すでに私達の名前を知っていた。
そんな彼をじっと見つめていると、窓際とは離れた、廊下側の方から女の子の声が聞こえてきた。
名前を呼ばれてそちらへ行くと、彼女は「 やめた方がいいよ 」と、小さい声で私達に言う。
「 やめた方がいいって、何が? 」
「 何が、って…あの人に関わるの。色も無い人間に関わるなんて、絶対にやめた方がいいって。 」
「 そうだよ…!それにあの人、なんかおかしいもん。 」
それとも、誰かにあの人のことで依頼されたの?と続ける女の子の言葉を、碧が「 やべ、数学の課題忘れた 」と呟いて遮った。
既に、他のクラスメイトも勘づいてはいるんだと思う。けれど、誰も触れてこない。
それは…例えどんな理由があろうと、皆、透過くんには絶対に関わりたくない、という事だ。
そして、いくら色が無いとは言えど、透過くんの場合は異例だった。
色を持たない人間の多くは、社会に認められず、社会に出ることすら出来ず、自分だけの殻に閉じこもっている。けれど彼の場合、こうして学校に来ているということ。
学校に来たくない、という気持ちは無さそうだし、殻に閉じこもっていると言われれば閉じこもっているけれど、引きこもりという訳でもないのだ。