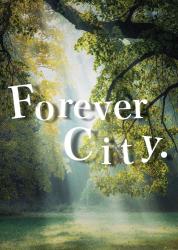自ら干からびた蚯蚓に水を掛けて、それを私達の真似だと言い、その蚯蚓に対して「 可哀想 」だと。
どういうことなのか、さっぱり分からなかったけれど、彼は蚯蚓を見つめたまま、再び口を開く。
『 ほら。俺に似てるでしょ、これ。 』
彼は、蚯蚓に目を向けたまま、私達にそう言った。
無視しなかっただとか、答えてくれただとか、そんなことは頭に無い。
ただ、この言葉にならない感情にどう名前を付けようか、これは一体なんなのか、その気持ち悪さに思考を奪われたままで。
蚯蚓は弱々しく畝り始め、その微かな水分のみでこれからを生きようと必死に這いつくばる。でもきっと、生きていられるのは、残り僅か。
彼はその姿を見つめて、自分に似ている、と。
『 あと少しで死ねたのに、他人の手で強制的に生かされて…可哀想な奴。 』
「 …あの、 」
『 でも、弱いから拒むことも出来ない。そういう自分も悪いよな。 』
「 透過く…、 」
『 ねぇ、こいつにも色ってあんの? 』
…答えられなかった。
それに、その場にいた誰も、彼の言葉に答えようとはしなかった。
彼の言葉を理解するのに時間が掛かって、それを理解出来たと思った時には、それは本当に " 理解出来た " と言えるものなのか、と、自問自答を繰り返す。
どうすれば彼を刺激せずに済むのか、どうすれば彼の言葉を理解出来るのか。
探偵部としての務めを、完全に忘れてしまっていた。
『 碧藍 夢冰、榎葉 碧、冴夜 緋音、探偵部。君らでしょ、俺の色を探せって依頼されてたのは。 』
どういうことなのか、さっぱり分からなかったけれど、彼は蚯蚓を見つめたまま、再び口を開く。
『 ほら。俺に似てるでしょ、これ。 』
彼は、蚯蚓に目を向けたまま、私達にそう言った。
無視しなかっただとか、答えてくれただとか、そんなことは頭に無い。
ただ、この言葉にならない感情にどう名前を付けようか、これは一体なんなのか、その気持ち悪さに思考を奪われたままで。
蚯蚓は弱々しく畝り始め、その微かな水分のみでこれからを生きようと必死に這いつくばる。でもきっと、生きていられるのは、残り僅か。
彼はその姿を見つめて、自分に似ている、と。
『 あと少しで死ねたのに、他人の手で強制的に生かされて…可哀想な奴。 』
「 …あの、 」
『 でも、弱いから拒むことも出来ない。そういう自分も悪いよな。 』
「 透過く…、 」
『 ねぇ、こいつにも色ってあんの? 』
…答えられなかった。
それに、その場にいた誰も、彼の言葉に答えようとはしなかった。
彼の言葉を理解するのに時間が掛かって、それを理解出来たと思った時には、それは本当に " 理解出来た " と言えるものなのか、と、自問自答を繰り返す。
どうすれば彼を刺激せずに済むのか、どうすれば彼の言葉を理解出来るのか。
探偵部としての務めを、完全に忘れてしまっていた。
『 碧藍 夢冰、榎葉 碧、冴夜 緋音、探偵部。君らでしょ、俺の色を探せって依頼されてたのは。 』