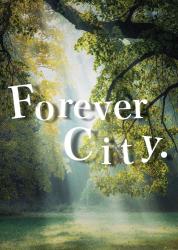「 …居ない、ね。 」
「 ですね〜…やっぱり、もう帰っちゃったんスかね? 」
靴をちゃんと履き直しながら呟くと、緋音ちゃんも残念そうにそう呟いて、明るい色の傘を畳直していた。
やっぱり、今日はもう諦めるしかない。
そう思って後ろを振り返ると、それと同時に、碧が「 おい、あそこ 」と、三年生が使用している昇降口の方を指さした。
「 …あ、 」
そこには、傘を指して座り込む、男子生徒の姿があった。雨も降っていないのに、無色透明の傘を指している、彼の姿が。
その瞬間、私達の中で時間が止まったような感覚に襲われて、何故か凄く緊張した。
今朝の彼の目と声。そして、その声で発せられた " 碧藍 " という私の名前。
それら全てが同時に、頭の中をグルグル駆け巡る。
水色の傘を握り締めて、そっと彼の元へと歩く。
「 透過くん、だよね? 」
三人で彼の傍に行き、恐る恐るそう聞いてみた。
けれど、返事は無い。
「 …何、してるの? 」
捻られたままの蛇口から、弱々しく流れ続ける水。
それを掬った透過くんは、乾きかけた地面に、その水を零すようにして落とす。
そこには、干からびた蚯蚓が居た。
『 え?何って、君らの真似っ子。 』
するとその瞬間、生気のない声が返ってきた。
…なんとも言えない空気だった。
この汗は、気持ち悪い湿気のせいなのか。それとも、この言葉に出来ないような緊張感のせいなのか。それとも、その両方か。
それが分からないまま、返す言葉を見つけられないまま。
そして、その蚯蚓がそれが元の姿に戻って、再び弱々しく動き始めた時。
『 …あぁ、可哀想に。 』
彼はその蚯蚓見つめて、そう呟いた。