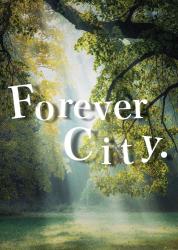…そんな私が、彼に迷惑を掛けられない。
ずっとそう思ってきたけれど、今はそんなことがどうでもよく感じてしまっていた。
研究者達に見つかる恐怖よりも、あの温もりをもう一度感じたかったから。
「 ……ッ、」
だから力を振り絞って立ち上がり、暒くんのいる街へと、懸命に足を動かした。
大きな森の中で何度も道に迷いながら、空が少しずつ低くなりながらも、森の外へ外へと目指し、歩き続ける。やっとの思いで森を抜ければ、橙色に染った空の下には、桃色の花が咲き誇っていた。
卒業シーズンが過ぎ、入学シーズンの今。あと少しもすれば、この花弁達が枯れてなくなってしまうだろう。
空腹のあまり頭が回らず、景色も少しずつ霞んでいき、白いワンピースから覗く手足には、折れた茎や花がまだ根を生やしていて。足元が覚束無いまま歩いて顔を上げると、周りの視線が私へと集まっていることに気が付いた。
…そうだ。私、追われてるんだった。
回らない頭に正しい判断力を奪われていた私は、今ここで、やっとそのことを自覚する。
どうしてこんな格好で来てしまったんだろう、彼に会いたいが為に何も考えずに、自ら危険を犯してしまったんだろう。
「 ぁ……あ、あぁ、あああ、」
駄目だ。こんな姿、暒くんになんて見せられない。
それに、こんな異様な姿をした傷だらけの女を見れば、誰かしらどこかへ通報するかもしれない。そんなことをされたら、私のこの体質が多くの人に知られてしまう。
…そんなの、絶対に嫌だ。
『 …椿煌?あ、おい!椿煌!! 』
花が咲いた手の平によって全ての音が塞がれてしまった耳には、そんな暒くんの声なんて届かなかった。