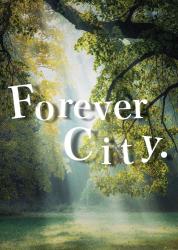それから何日が経ったのだろうか。
花を噛みちぎり、川の水を飲み、それでなんとか凌いできた。けれど、時間が経過する度、どうしようもない不安と恐怖に駆られていた。
研究者に見つかったらどうしよう、私はどうされてしまうのだろう。
…ああ、また花が咲いた。
空腹と恐怖で力の入らない身体は震え、呆然とした頭の中で、たった一つの温もりを思い出す。
「 ……暒、くん。 」
そして無意識に口にしたのは、私にとって唯一の存在である彼の名前。
輝桜 暒國。
家族ぐるみの付き合いではないものの、幼馴染みである彼とは、小学生の頃からずっと仲良くしていた。
私より二つ上の彼は、将来医師を目指していて、今は頭のいい大学院に通っている大学生。
愛する親も、友達と呼べる存在も居ない私には、彼だけが唯一の救いだった。彼と話している時が一番心が落ち着いて、安心して、花が萎れていくような気がしたんだ。
でも、そんな彼にもこの体質のことが話せないでいた。
どうして話せなかったのか。それは、彼がこのことを知ったら、と、彼のことを疑っているわけではなかった。
暒くんは、とても優しい人だ。
少し冷たく見えてしまうところもあるけれど、私のことは実の妹のようにして可愛がってくれた。だから私も、彼のことを実の兄のように思ってきた。
強引なところもあるし、昔はよく、私が怪我をすると直ぐに心配して駆けつけてくれていたっけ。
…だからこそ、彼には話せなかったんだ。
きっとこの体質のことを話せば、余計な心配を、何より迷惑を掛けてしまう。
暒くんは私と違って、皆の人気者。それに大学だって忙しいだろう。それに比べ、高校を卒業したばかりの私は、ただのフリーター。