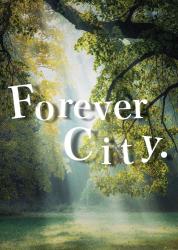だから止めた。すると狂盛は、一瞬だけ目を丸くした。
…こいつは、本当に感情を知らないんだな。
互いに取り乱しているからこそ、面白い程に伝わってくる。
『 愛が理解出来ない、愛に興味が無いみたいな顔してるけど。本当は理解したいんでしょ?興味を持ってるんでしょ? 』
年下相手に、大人げないことを言ってしまっただろうか。
けど、これは本当のことでしょ?
紅苺ちゃんから紗來ちゃんを消してしまったこと、誰よりも後悔してるのは狂盛の癖に。無意識に自分のことを責めてる癖に。
本当は、泪だって愛が知りたいんでしょ?
目の前にいるのは、狂盛では無くて泪だった。
明らかに動揺しているその姿に、少しだけまた余裕を感じる。
「 俺は満足してるよ。紅苺ちゃんも同じ、今のままでいい。偽物だろうが何だろうが、俺達の中での愛はそれだから。 」
だから、そんな嘘をついてしまった。
俺も紅苺ちゃんも、今すぐにでもこんなことはやめたい。
楽しくなんかないし、身体を重ねる度に苦しさは増すばかり。こんなことをしていたって、愛なんか一生知れないってこと、俺が一番分かってる。
泪は、そのまま何も言わずに目を逸らした。
胸ぐらから手を離すと、更に視線を落とす。そんな泪にバレないように、下唇を噛み締めた。
嗚咽混じりの乾いた笑いが、微かに漏れた。
駄目だ、このままじゃ涙が落ちてしまう。
もう泣きたくない。
あの頃には、絶対に戻りたくない。
俺は、そのまま昔の自分を押し殺すように、リビングから出ていった。
「 …何やってんだ、俺。 」
廊下に、酷く震えただらしない声が微かに響く。
そんな夜も、俺は紗來ちゃんに " 遊びをやめよう " の一言が言えなかった。