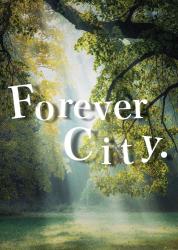なのに、今こいつからは " 苦しみ " と " 怒り " を感じる。
…いや。正しく言えば、憎しみ?
感情を、微かにだけど顕にした狂盛を見て、少し余裕が出来てしまったのかもしれない。それとも、逆に追い詰められて焦ってしまうような気がしたのかもしれない。
それは、分からないけど。
『 …そんなことしても、愛なんて、知れるわけがないじゃないですか。 』
でも狂盛は、それの胸ぐらから手を離して、そう言いながら笑った。
既に自覚している事実に、嘘臭い笑顔。
まるで、自分の感情を隠すかのように貼り付けられた笑顔。
俺の真似をしていると、嫌な程に伝わってきた。
『 游鬼さんよりも、烏禅くんの方が紅苺に愛を教えてあげられるんじゃないですか? 』
その言葉を聞いた瞬間、俺は衝動的に狂盛の胸ぐらを掴んだ。黙れ、と、自分でも聞いたことがないくらいの低い声で。
衝動的にしてしまったからか、自分でも少しだけ驚いていた。
狂盛を睨むこの目も、怒りで震えるこの拳も。
そんなこと、俺だって分かってる。
こんなこと、俺も紅苺ちゃんも、幸せになんかなれない。
狂盛が…泪が、親から充分な愛を注がれて生きてきたことなんて知ってる。血は繋がっていない親だけど、確かにこいつは愛されてきた。
それなのに、愛が理解出来ないたとか、何だとか。
俺は、俺は。
「 俺と紅苺ちゃんの遊びなんだから、狂盛には関係ないよね。 」
そう言って、笑った。
父親に殴られて、泣き叫んでいた頃の自分を殺すように。
あの頃の自分を、殺すように。
『 …そのままじゃ、愛なんて一生、 』
その言葉の続きは、どうしても聞きたくなかった。
「 それは狂盛でしょ? 」